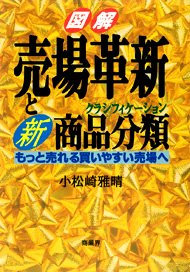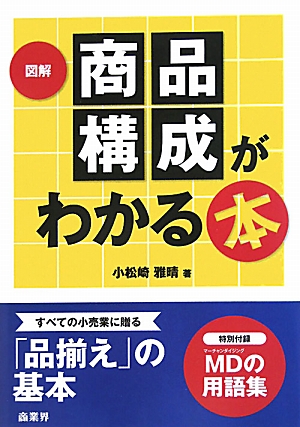1.類似の特性のものをまとめることの本質と効用
(1)類似する『もの』をまとめる
我々が何気なく過している毎日の生活も,よく観ると実にさまざまな工夫がなされている。例えば,洗面所では歯磨き,歯ブラシなど毎日使う使用頻度の高いものを一箇所にまとめ,取り出しやすく,戻しやすいよう置き方にも工夫している。
ハンカチ,靴下,腕時計,財布,携帯電話など毎日使う小物類は,まとめて取り出しやすい高さに置けば短時間で準備ができるし,忘れることの予防にもなる。
使用場面・用途・目的などの類似性によって『ものをまとめる』ことは,昔から生活の知恵として日常的に行われている。
同様に仕事の場面でも,使用頻度,目的,進捗状況,納期,手続きなどの類似性に着目し,『ひとつのまとまり単位』として管理することは一般的によく行われている。
改めて意識することは少ないが,『一定の秩序』に従って類似するものをまとめることは,我々の思考や行動にとってとても便利である。
物事の仕組みや法則性を見出すための科学的方法として『分類概念の適用』『グルーピングとモデル化』という手順が非常に重要な意味を持つことは、さまざまな形で指摘されている通りである。
種々雑多なものが混在し,相互に干渉することで一見無秩序で分かりにくく思えるものも,適切な分類概念によって上手いグルーピングができれば,内包する秩序や仕組み,メカニズムなどの他,表面からは見えにくい法則性を見出すことも容易になる。
日常的な生活,仕事の処理,製品や製造工程の設計・改善,情報システムの設計・改善,それらに関するマネジメント,さまざまな物事に関する認識・思考,・・・総て同様である。
類似するものをまとめること=分類・層別の効用は,物事を一定の秩序に基いてスクリーニングし,体系的に整理して見やすくすることである。分類・層別することによって得られるメリットは計り知れない。
(2)類似するものをまとめたGT(Group Technology;グループ・テクノロジー)
生産分野では,1963年以降,多品種少量生産・個別生産などの生産性向上,コストダウンを目的として 西ドイツ アーヘン工業大学のH.オーピッツ教授らによる『部品グループ加工』に関する実践的研究が行われている。
少品種大量生産の時代から多品種少量生産の時代に変わり,従来の生産方式(生産のやり方に関する思想,具体化する上での考え方,具体的方法)に代わる新たな生産方式開発の必要性が高まっていた。
少品種大量生産を支えた3S(①Simplification;単純化,②Standardization;標準化,③Specialization;専門化)は,T型フォードの生産に代表される流れ作業方式のベースにある思想,考え方,手法である。100年近く経つ現在も,マネジメントをはじめ,さまざまな分野に深く影響を与え続けるほど普遍性の高い思想でもある。(もっとも時代は大きく変わり,根底にあるこの思想から抜け出せずに喘いでいるケースも多々見られるが……)。
①製造工程を細かく分けて一つ一つの工程を単純化し,単純化した工程に対して②最もよいと考えられる方法を標準として採用する。誰でもできるほどに単純化したそれぞれの工程に③作業者を専門的に配置することで習熟性を高め,全体の効率化を図る。品種を絞って生産量を集中させ,専用工程を採用することで高い効果を発揮する。
一方,多品種少量生産や個別生産では,専用工程を採用する程の生産量はない。
品種によって製造工程・加工方法が異なるため,ラインを組み替える段取り替えが頻繁に発生する。原材料・部品の種類は増え,発注,在庫管理,工程管理などあらゆる面で少品種大量生産とは比べものにならないほどの手間が掛かる。しかも生産量が少ないために管理コストの占める割合が増大し,利益を圧迫する。
H.オーピッツ教授らは,製品を品種毎に個別管理するのを止め,複数の品種をまとめて製品を群単位で捉えるようにした。製品群の加工ロットは,加工工程,加工方法,素材,部品形状など類似する特性によってフレキシブルに編成し直し,部分的に『擬似 少品種大量生産』に変換することで3Sのメリットが得られるようにした。
このやり方は,煩雑で効率が悪いとされていた多品種少量生産・個別生産に対して有効な考え方,手法として数多くの実績を上げ,研究成果はGT(Group Technologyグループ・テクノロジー)として広く一般に知られるようなになった。
その後,GTはヨーロッパ中心に普及し,我国でも数多くの企業が導入している。
しかし,残念なことにGTに関する考え方,手法の普及は製造分野だけにとどまり,それ以上の発展,広がりを見るには至っていない。
(3)現在のように煩雑な時代にこそ必要な『類似するものをまとめる=分類・層別』
物事を構成する要素,影響を与える要因は,製造業が多品種少量生産へ移行した時代とは比べものにならないほど増え,さらにIT化によって情報量は級数的に増え続けている。我々を取り巻く環境,対象として捉えなければならない状況は,はるかに複雑化している。
このような環境下で正しい認識,正しい判断をするためには,増え続ける情報,表層で複雑に絡み合う要素をそのままの形で見るのではなく,類似する要素をまとめる=分類・層別することで体系的に整理し,その裏に隠れた本質を的確に読み取る必要がある。
例えば,『ある物事に関して何らかの可能性を探りたい』のであれば,物事を構成する個々の要素を,目的である『可能性』に対してプラス(直接的・間接的),マイナス(直接的・間接的),中立,その他(条件によって変動,あるいは無関係)というように分類・層別すると分かりやすい。
分類・層別することの効用は次のように整理できる。
①目的に応じて特性の似たまとまり単位をつくることで,個別要素に惑わされることなく,プラス,マイナス,中立,その他のウエイトがどうなっているかなど,マクロ的な視点から物事を観ることができる。構成要素を分類・層別するために一度個別に識別する必要はあるが,特性の似たまとまり単位に集約することで,全体的な状況・本質を見極める作業効率が飛躍的に高まる。
②『マイナス要素をどうにかしたい』といった場合では,対策を打ちやすくするために原因別,あるいはコントロール可能/不能というようにまとめ直すことで,まとまり単位に対して共通する管理方式,対応策などを当てはめることが可能となる。
個別要素毎に対応する煩雑さから開放され,効率は飛躍的に高まる。
③煩雑な状況下では,機械的に総て画一か,効率を無視して個別対応という二者択一の対応になりがちである。類似する特性のまとまり単位をつくることで,それぞれのまとまり単位の性質に応じて的確,かつ効果的な対応が可能となる。
2.クラシフィケーション(Classification;有形・無形のものが持つさまざまな特性に着目して適切なグルーピングを探し出し,物事の状況・本質を的確に読み取るための分類・層別に関する考え方・方法)
GTでは,製造工程に『擬似 少品種大量生産』をつくり出すことを目的として,さまざまな特性の類似性に着目してグルーピングをした。
一方,クラシフィケーション(Classification)は,一見複雑で無秩序に見える物事の全体的状況,内包する秩序,仕組み,法則性,メカニズム,問題点などを見出すことを目的として,さまざまなグルーピング=分類・層別を行う。
『ものの特性に着目して類似するものをまとめる』という点で両者は共通するが,その目的は基本的に異なる。
GTが工場内の製品を対象とするのに対し,クラシフィケーションは有形,無形の『もの』総てを対象とする。目的は,『秩序,仕組み,法則性,メカニズム,問題点などを見出すこと』であるから,例えGTと同じ製品を対象とした場合でも検討する特性の範囲は異なる。有形なものでは素材,二次加工品,製品など形あるさまざまな物を対象とするが,グルーピングのために用いる特性は,素材の調達エリア・調達方法・調達の容易性から製品の使用場面・使用方法・購買対象・購買動機・リサイクルの仕方など多岐に渡る。
目的に応じて有効と考えられるあらゆる特性についてさまざまな角度から検討する。
(1)クラシフィケーションの考え方と適用の手順
物事を的確に認識することが,総ての原点である。
クラシフィケーションでは,まとまり単位が持つ秩序,仕組み,法則性,メカニズム,問題点などを見出すために,次のような手順を採る。
①対象とする物事が持つ特性の整理と理解
物事の本質を理解するためには,表面的な理解ではなく,物事を構成するさまざまな要素が持つ特性に対して理解することからはじめる必要がある。
図表-1 は,『有形なもの(例;製品)』と『無形なもの(例;業務)』を対象として通常考え得る特性を整理したものである。特性は,図表‐1に示すように実にさまざまであるが,目的に対して総ての特性が有効であるわけではない。通常であれば2~3の特性が重要な意味を持ち,他の特性は目的に対してほとんど意味を持たない。
したがって,特性を整理すると同時にそれぞれの特性がどのような目的に対して重要な特性であるかということも同時に理解する必要がある。
②目的と特性
多くの場合,『目的』は煩雑で混沌とした状況に対して適切な対応策を策定することである。そのためには,物事の持つさまざまな側面を特性によってスクリーニングし,ノイズを排除した状態でその特徴・性質を見出していく必要がある。
重要なことは,目的とスクリーニングに用いる特性との関連付けである。
例えば,製品の場合,物理的特性として素材・成分,構造・機構などの特性がある。
素材は,製品の強度や加工方法を決める上で重要であり,構造は,加工工程や製品の機能・性能を決める上で重要な特性である。しかし,設計や製造段階で重要となるこれらの特性も,使用段階では必ずしも重要な特性とは限らない。むしろ,使い勝手や耐久性・保守性が重要なケースも考えられる。
また,業務では,業務設計などマクロで見る場合には業務目的・業務機能が重要な特性になるが,日常の業務遂行では,『実施』に直接関係する手続き上の特性,人的特性,時間的特性などが重要になる。
このようにさまざまな特性も,目的によって重要度が変わり,場合によっては全く意味をなさないケースもある。
したがって,クラシフィケーションでは目的と特性の関連付けは欠かせない。
③目的と特性の関連付け
クラシフィケーションに限らず,GTでも同様であるが,最も難しいのが,目的に応じて特性を特定することである。
同じ目的であっても,企業や職場の状況によって全く同じ特性を使えないケースは多い。例え使えたとしても,個別の構成要素を識別する際に固有の状況や制約条件などにより,修正する必要がある。
目的と特性の関係を抽象化・一般化して表現することは可能であるが,上記のような理由で具体的な適用にはほとんど意味をなさない。
したがって,実際に適用する際には,仮設を立て,さまざまなケースについて個々にシミュレーションで確認しながら進める必要がある。
(2)クラシフィケーションによるものの見方
クラシフィケーションの訓練には,『有形なもの』を対象にした方が分かりやすい。
図表-2は,製品ライフサイクルによって重要な特性が変化していく様子を表したものである。重要なことは,『生産』では『物としての製品・製品の基本機能に関する特性』が中心であるが,その前後の段階では『中間的な特性』『製品の意味・価値など二次機能に関する特性』のウエイトが高まっている点である。全く同じ製品でありながら,ライフサイクルの各段階で捉え方が異なり,製品の『意味・価値』が変わることを表している。
このように,物事には有形・無形を問わず『絶対』いうことがなく,視点を変えることで意味・価値は変わる。一つの限定された視点だけで物事を観ていては見えないことも,さまざまな角度から視点を変えて観ることで物事の持つ別な側面を見出すことができる。
クラシフィケーションは,そのために『ものの持つさまざまな特性』に着目している。
基本は,物事をただ漠然と捉えるのではなく,さまざまな特性に着目して分類・層別し,限られた視点から見直してみることである。
おそらく,漠然と捉えていた時とは全く違った側面が観えてくるはずである。
このようにして,それまで見えなかった秩序,仕組み,法則性,メカニズム,問題点などが見えてくれば対応は比較的容易である。
物事を特性という視点から見る訓練をすることで,それまで機械的・画一的に処理されていたことの乱暴さや一々個別に対応していたムダも見えてくるだろう。
クラシフィケーションを用いることで,物事の本質が明確に見えてくるはずである。