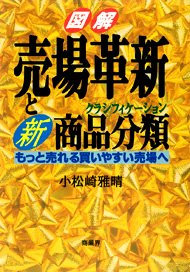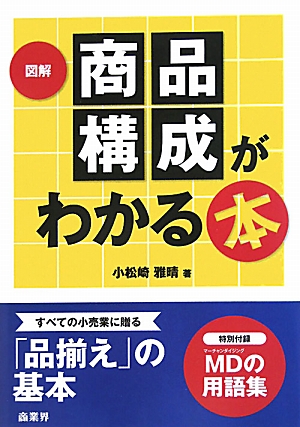詳細は省くが、テレビ東京のホームページ(http://www.tv-tokyo.co.jp/travel/entry/bwImF/31877/)によると「全振連が47都道府県の商店街振興組合を対象に行った調査で は、名称に“銀座”が入る商店街の数は345件ありました。ただし、平成16年6月に行った調査結果なので、今は数が前後しているかもしれません」(広報担当者)とある。 345が多いか少ないかは別にして、日本国内にこれだけの数の〇〇銀座があるのであれば、〇〇竹下通りがあっても不思議ではないだろう。 商標の権利関係がどうなるのかは分からないが、SCの形に仕立てあげることができれば、一つのビジネスの形としてフランチャイズ展開をすることも可能である。 できればパリやニューヨークに輸出してみたいビジネスモデルの一つであるがどうだろうか。 そう考えると、日本のシーズはまだまだたくさんあるし、料理の仕方次第で化ける可能性のあるテーマもたくさんあるのだろう。 技術があっても戦略とアイデアがなかったために家電事業は海外企業に買収されているが、地方の町や文化まで買われてしまわないように、事業化するアイデア、スキル、ノウハウなどを高めていく必要がある。
Archive for wpmaster
竹下通りを輸出しよう‼
平成27年国勢調査の速報値が発表された‼
2月26日に平成27年国勢調査 人口速報集計結果が発表されたこともあり、これまで「推計」とされていた状況がよりリアルなものとして認識されるようになっている。 平成27年10月1日現在の人口は1億2711万人、前回(平成 22 年)より94.7万人減少、大正9年の調査開始以来、初めての人口減少となっている。 都道府県別にみると、東京都が 1351.4万人と最も多く、全国の 10.6%を占める。以下、神奈川県(912.7万人)、大阪府(883.9万人)、愛知県(748.4万人)、埼玉県(726.1万人)、千葉県(622.4万人)、 兵庫県(553.7万人)、北海道(538.4万人)、福岡県(510.3万人)であり、人口上位9都道府県で6847.3万人、全国の53.9%を占める。また、東京圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)の人口は3612.6万人で、全国の28.4%を占めており、5年前に比べ 50.8万人増加している。最も少ない鳥取県の人口57.4万人に近い人口が5年間で増えたことになり、人口集中はさらに進んでいることになる。 人口増加は8都県、39道府県で人口減少している。また、全人口が増加した市町村は1、719市町村のうち303(17.6%)、減少した市町村は1、416(82.4%)と8割を超える。5%以上減少した市町村も約半数(48.2%)まで拡大している。 数値を見る限りでは、東京一極集中はますます進んでいる。過去に推計された状況がよりリアルなものとなっているから対応を急ぐ必要があるが、まだ形式的な動きが中心であり、なかなか結果につなげることができないでいる。 思い切ったというよりは、これまでの常識を超えて当たり前のことを当たり前に実行する必要があるだろう。 重要なことは、財政的なゆとりがないと思い切った策が打てないことであるから、常識を超えた生産性を実現するしかない。 マーケティング戦略、IoT、ICT、ロボット、AIなどデジタル技術の応用とバイオ技術などを活用した農業や水産業の革命的な変革を実現する必要がある。 資源も技術も眠っているものが多いから、いかに事業化するかが重要になる。
第50回スーパーマーケットトレードショー2016に行ってきた
第50回スーパーマーケットトレードショー2016に行ってきたが相変わらずの盛況であった。
特に地方創生で力が入っていることもあり、各地方から出店しているブースを意識して見てまわった。残念だが、同様な素材、同様な加工方法を用いた類似商品が多いのが気になる。しかも、規模が小さい企業では、せっかく展示会に出展しても、まとまった注文が入ると対応できないという。
常々思っていることであるが、さまざまな地域で、数多くの企業が、同じような素材を使い、それぞれで企画をし、試行錯誤しながら、それぞれで商品開発して、それぞれで販売を行っている。皆が知恵を絞って一生懸命にやっているのだろうが、それでも出来上がる商品は類似しており、ずば抜けて競争力がある商品が出てくる確率はそれほど高いとも思えない。
たとえ同じような工程で作る商品であったとしても、それぞれで工程設計を行い、それぞれで生産しているから、どこかで失敗した経験があったとしても共有することなく、同じような間違いをまたどこかの企業が繰り返すのだろう。量もまとまらないから小規模な工場がたくさん存在し、生産効率ばかりでなく、商品開発に関連するすべての業務効率が上がらないという状況にあることは想像に難くない。
地方創生では、それぞれの地方でアイデアを出して競争することを奨励していたようだが、人口減少・高齢化が急速に進む日本全体の状況を考えれば、かなりロスが多いと考えるべきではないだろうか。
地域が違っても、類似する素材(例えば柑橘類)を作っているところがあれば、できる商品も、加工方法も似てくるから、「地域ごと」にこだわるのではなく、「類似する素材を使う地域・企業が連携して取組む」ように切り替えたほうが、重複する工程・作業が一本化でき、集約できるから生産効率、販売効率が高まり、多くのメリットがあるはずである。
全てをそうしろというのではなく、そういう取り組みをした方がよいものに関しては、集約して効果を確認し、徐々に拡大していくような方法がとられてもよいだろうということである。
このような取り組みが上手くいけば、ボランタリーチェーンやフランチャイズチェーンのような形態をとることも可能であり、さまざまな知識・技術・ノウハウ、人材などの交流が図られれば質的量的に充実するから、パワーも増す。いろいろな面でメリットがあるだろう。
重要なことは「生産性を高める」ことであるから、量をまとめることは有効な手段になる。知識・経験・技術・ノウハウなどを集約し、共有することも有効である。何よりも地域以外から収益を上げない限り、地域が潤うことはないから、グローバル化を図れるだけの規模にまとめるという意味からも地域が協力して集約していくことは有効と考えられる。
R&D(研究開発)などの手法を応用することができれば、異業種が持つ技術を相互に活用するような方法も考えられるから、それぞれの企業の持つ強いところをうまい具合に組み合わせることも可能になるだろう。
国勢調査の速報値が発表されているが、高齢化と人口減少の速度が増していることは明らかである。時間的な余裕がないことを含め、知恵を有効に使い、スピード感を持って対処していくことが重要になるだろう。
「節約志向」という勘違い?
テレビで経済番組を見ていたら、安さを訴求している店を事例として紹介し、盛んに「節約志向」「節約志向」とアナウンサーが言っていた。解説の専門家も盛んに「節約志向」「節約志向」と解説していたから、そういう番組なのかと思ってみていたが、「???...」「本当???」「なぜ、表面しか見ない⁉」と不思議に思った。 ずいぶん前になるが、ディスカウントストアの駐車場を見るとベンツ、アウディ、BMWなど外車が数多く止まっていた。 日本は、階級社会ではないから、収入と住んでいる地域、乗っているクルマ、買物する店などが必ずしも一致しない。 アメリカのように、この道路から向こうの住宅は〇〇万ドル以上で、年収いくら以上の人達が住んでいる。こちらはアジア系が多く、向こうはヒスパニックが多い地域、....などということもない。 年収1000万円以上の人でも当たり前に100円均一ショップで買い物するし、ディスカウントストアで買い物することも、食品スーパー、ドラッグストア、ホームセンター、総合スーパー、百貨店で買い物することもある。 それでは100円均一で買い物をするのは、節約志向なのか? ディスカウントストアで買い物をするのも節約志向なのか? あるいはドン・キホーテで買い物をするのも節約志向なのか? というと大いに疑問が残る。 「買物をする」という行為は、必ずしも経済原則と一致しない。特に日本の場合には、いわゆる昔から言われているような収入と買物の間にきれいな相関関係が成り立たない。外資の企業が日本に進出して戸惑うのは、彼らが知る経済原則、マーケティング理論だけでは日本の消費者(購買行動、価値観)を理解することがなかなか難しいからだろう。 同じ商品を高く売っている店と安く売っている店があれば、わざわざ高く売っている店に行く必要はないだろうし、どこでも価格競争をやっている時代だから、単に商品が安いというだけでお客を引き付けることも難しくなっている。 むかし、ジョイフル本田の店長が、自店の魅力を「発見の喜び=何があるか分からないから、何かを見つけて買えた時の喜びが大きい、それが魅力」と言っていたことがあるが、ドン・キホーテについても、全く同様に「どこに何があるか分からないから、それを探すのが楽しい」と魅力を語ってくれた人がいた。 ダイソーの大型店、ピンクダイソーなどを見れば、他の店には売っていない商品が数多く並んでいるから、別に100円均一(いまは価格帯が広がっているが...)でなくても十分にお客にとっては「行く価値」のある、魅力ある店ということになる。 ピルケース(薬のケース)やネイル関連商品など見ればドラッグストアの品揃えをはるかにしのぐし、プラスチック成型品などでもホームセンターをしのぐ品揃えがある。 低価格を訴求することは、どんな業態、企業でも当り前に行われているから、消費者を引き付けているのは、単に価格だけではないはずである。そこを追求するような番組があれば、大いに参考になるのだと思うが、表面をなめただけで分かったような解説をしていたのでは、いつまで経っても高いか安いだけの話から抜け出せない。 本質からどんどんかけ離れた方向へ進んでいってしまうのでは、困ったものである。
リテイル・エンジニアリング-2 いま、もう一度オールドIEと小集団の改善活動
いまはもうIEやQCサークル、小集団活動などと言って通じる人はほとんどいなくなっている。盛んに行われていたのが、30年以上も前だから、当時中心になって活動していた人もリタイアし、いま現役で企業の中心にいる人は未だ物心ついていないか、あるいは生まれてないといったところだろう。 なぜ、こんなものをいまさら引っ張り出すのかといえば、中小零細規模を中心としたさまざまな業種、あるいは地方創生で町興しに躍起になっている地方自治体や企業、団体の活動にとって非常に有効と考えられるからである。 当時と違って、ICT、デジタル化が著しく進んではいるがIEやQCサークル、小集団活動などは、基本的な活動、物を対象とした様々な活動にとって非常に有効な手法であるにもかかわらず、現在では全く忘れ去られてるからである。 たとえば、おばあちゃん達が葉っぱを売って何百万円もの収入を上げていることで有名な「株式会社いろどり」がどのようにして出来上がってきたかという発表資料を見たことがあるが、かつてのQCサークルそのものと言ってもよい内容であった。 関係する人達が個人個人、みなバラバラな状態では、統一して高いレベルの活動は実現しない。重要なことは、全体を指導するリーダー、全体の活動を統一的に説明する理論、個々の活動の確実に結果へと結びつける手法、そして全員に対する動機づけとメンバーの参画意識などが非常に重要になる。 30年前には筆者もホームセンターを中心にそのような改善活動を指導していたが、さまざまな企業のチームでいろいろなテーマに取り組み、多くの成果を上げている。 中には、1年間の活動で10倍以上売上を伸ばした商品などもあり、部門売上が2倍を超えたところもあったから、やり遂げたメンバー達は自信を深め、大きく成長している。 製造業で実績のあるIE、QC、VEなどの改善手法、現場で改善を行うQCサークルや小集団活動という活動形態は、現場スタッフの能力を引き出し、モチベーションを高めて、組織として大きく成長するという点で中小零細規模の企業や団体に向いている。 実際にこのような活動に参加して成果を上げたことで、それまで組織にもあまり馴染めず、いつも辞表を胸にしのばせていたという人が、S、A、B、C、Dの5段階評価のD評価から一気にS評価まで変わったというケースもある。 基本的に人はある程度の能力を持っているが、実際に仕事の場面でその能力を十分に発揮している人は少ない。しかし、何かのきっかけがあって、上手いやり方を自ら工夫して試し、成果を上げることができると、それを楽しめるようになり、能力をどんどん発揮するように変わる。 同じ時間、その職場で過ごすのであれば、つまらないと思って過ごすよりは、楽しみながら良い結果を出した方が自分も組織も進化できるし、成果が上がれば報酬という形でも反映されるから、良いことばかりである。 今後は急激に人口が減り、高齢化するから限られた人達で効率よく成果を出していく必要がある。現在、人工知能やロボットによって将来取って代わられると考えられる職種が盛んにニュースとしてとり上げられているが、新しいことを工夫して創りだすことは人間にとって重要なことであるし、そのような能力を高めていくことは今後とも重要なことである。 難しい状況に直面しているからこそ、もう一度IEやQCサークル、小集団活動などに取り組んでみることも大切だろう。むかし流行ったから古いというのではなく、いつの時代も工夫をして進化することが重要だから、やってみる価値はある思うが、どうだろうか。
時代の変化は意味・価値の変化 それが理解できなければ次のステージには進めない
時代の変化を感じるのは、モノ・コトの意味がそれまでとは変わり、価値が変わった時である。 例えば、園芸の世界を見ると、昔の人は身近にある草木を楽しんでいた。盆栽やサツキなどは一部のマニアが楽しむ特別な趣味であり、品種改良や品評会に出すことが主な目的であった。 園芸が大きく意味を変えたのは、観葉植物が「インテリアグリーン」としてインテリア=装飾というポジションに変わった時である。 マンションの普及から洋室が増え、畳からカーペット、フローリングと室内のつくりが変わったことで、インテリアグリーン、インテリアミラー、絵画などヘアを装飾する商品のニーズが高まった。 品種改良や品評会は特殊な一部のマニアのモノでしかないが、インテリアであれば、広く一般の人が日常生活の一部として取り込むことができる。 ホームセンターが急激に成長し、店数を増やしたのとタイミング的にも一致している。テレビ、雑誌などで盛んに特集されたこともあって広く一般に普及していった。 一部の人の特殊で専門的なモノから、誰でも取り入れることのできる一般的なモノに意味を変えたことが、園芸マーケットの拡大、主なチャネルであるホームセンターの拡大に大きく影響している。 その後、いったんブームは収束するが、新たに「ガーデニング」「イングリッシュガーデン」となって、クラフト(手工芸)のポジションでブームを巻き起こす。インテリアはイミテーションでも成り立つ静止物という性格が強いが、ガーデニングは植物の特性を理解した上で、さらにさまざまな花苗、カラーリーフ、器や装飾小物を組合せて一つの形を創り上げるという点でクラフト的な要素が強い。ハンギングバスケット、コンテナガーデン、アレンジメントなど花苗やカラーリーフを使って創り上げることに大きな意味があり、中高年女性中心に支持されてブーム化した。 現在は、そのブームも収束し、東日本大震災以降の省エネからはじまった家庭菜園が広く定着しているという状況にある。 一時期ブームになった年末のイルミネーションと同じで、ある程度盛り上がっても行きつくところまで行くと、多くの人は疲れてしまい、高齢化と共に徐々に離れていってしまう。 アクアリウムも同じである。金魚や錦鯉と違って、アクアリウムという名前、オシャレな曲面ガラスの水槽などが「インテリア」というポジションでとり上げられ、テレビドラマでも盛んに放映されたことから、これもまたホームセンターチャネルをベースにして広く普及していった。 一部のマニアのものであったものが、広く一般に受け入れられる時は、特別な趣味の世界から、誰もが日常生活の中で当たり前に取り扱えるモノへと意味を変えるからマーケットは大きく拡大する。 品種改良、品評会からインテリア、クラフトと意味を変えた園芸、品種改良、品評会からインテリアへと意味を変えたアクアリウム、...、これらは意味を変えたことで広く普及し、それに伴いチャネルも変わっている。 時代の変化は、商品を含めたモノの意味、価値が変わることによって広く一般に普及したり、逆にブームが収束したりすることと一致する。 sightseeingがsight doingに変われば、ただ見て歩く観光は衰退し、食べ歩き、買物ツアー、体験ツアーといったdoing要素が入らないと見向きもされなくなる。 なぜマーケット情報が重要なのか、マーケティングが重要なのか、と考えた時、この意味の変化=時代の変化を読み取り、ビジネスのフィールドを修正したり、ビジネスモデルを修正したりすることで、次の時代へのシフトをスムースに行えるようにする必要があるからである。 それができなければ、いつまでも もう無くなってしまった意味、過ぎ去ってしまった価値観に引きずられて縮小するマーケットを追いかけることになる。それを売れなくなったと嘆いても意味がない。マーケットが常に変化するのは当たり前のことである。 いまの時代も、またいろいろなモノ・コトの意味が大きく変わろうとしている時代である。爆買いでさえ、物からコトへ移りはじめていると言われ、温泉に入ったり、治療や美容整形を受けに来たりというように、さまざまなサービスへと消費の方向がシフトし始めている。 国内でも、既にカーシェア、バイクシェア、アパレルのレンタルは当たり前であり、購入し、所有するよりも必要な時に必要なものを借りて使うという消費スタイルが広く定着し始めている。 物を所有すること(ストック)から使うこと(フロー)へと消費の意味が変わり始めていることは、大きな流通構造の変化(物の供給の仕方)=チャネルシフトが起こることを意味している。 小売がレンタルに変われば、人口に対して同じ商品をたくさん必要としなくなる。一方、飽きないように多くの種類が必要になるから、現在よりもさらに多品種少量生産が必要になる。購入するわけではないから、商品そのものの価格は販売用よりも高額にシフトする。 物づくりそのものに対するニーズが大きく変わることになる。 さらにUberに象徴されるようなシェアリング・エコノミーが当り前になれば、大量の物にこだわることは、過去の遺物と言われても仕方ない状況になるだろう。 時代の変化は、物の意味を大きく変える。それに伴いビジネスのフィールド、ビジネスモデルも変わっていかなければ、企業はいずれ自然淘汰される。 人口が減少し、高齢化することによって消費量も減少する。さらに物消費からコト消費へと消費者の志向、ライフスタイルが変わり、シェアリング・エコノミーによって、これまでであれば何もせずにムダにしてきた能力の空き、隙間を使って新たなビジネスが生まれる。 機械・設備など新たな物への投資がなくても稼働率を高め、生産性を高めることで新たなビジネスが生まれる。 たくさんの物をつくり、たくさんの物を売ることでしか成り立たない構造が変わろうとしている。大量生産、大量販売に依存するビジネスモデルにこだわっていては、生き残ることは難しくなる。 変化の方向、変化の仕方はある程度見えているから、問題はこれまで構築してきた物ベースのインフラにどのように対処するかだろう。 いつまでも捨てられなければ、次のステップは踏み出せない。意思決定することが重要になる。そう考えると頭の切り替えが最も重要になる。
「人間観察バラエティ モニタリング」で見えた消費者の志向の変化 総合スーパー(GMS)再生の救世主になる?
YBS系の「人間観察バラエティ モニタリング」という番組で、食堂に家族で夕食を食べに来たお客に対し、自分でテーブルセットをすると100円引き、食材を準備すると〇〇円引き、調理まですると〇〇円引き、洗い物をすると〇〇円引きという仕掛けをやっていた。 企画の狙いとしては、普通の食堂に食事をしに来たお客が「割引き」に対してどう反応するのかを見たかったのだろうが、意に反してお客が喜んで取り組んでしまったことで、いささか拍子抜けしているようであった。 以前から言っている観光業界では、sightseeingではなく、sight doing出ないと売れなくなっている、という状況が、飲食、小売りなどいろいろな場面で起こっているだけなのだが、古い感覚だけで見ていると、何か異常な状態が目の前で起こっているようにも見えるのだろう。 特に面白かったのが、祖父母、母親、子供という家族の例だった。子供たちは何でもやりたがるし、お母さんもそのうち夢中になる。おじいちゃんは孫たちが一生懸命に調理する姿に目を細める。出来上がった料理も特別美味しく感じたようである。 以前、テレビのインタビュで若い男の子が「物にお金を使うのなら、思い出に使いたい」と言っていた。 物が溢れ、物を入手するチャネルも実店舗以外にスマホ、PC、一般小売にオークションとさまざまであるから、買物(物を入手する)という行為に対する価値観、消費に対する価値観も大きく変わっていると考えるべきである。 そう考えれば、総合スーパー(GMS)も、ただ広い売場を持て余しているのではなく、建物全体を体験型消費だけにしてしまうくらいのことをやれば、多くの人達が遊びに来て、楽しみながら買い物するように変わるかもしれない。 そもそもイトーヨーカドーではバーベキュースペースを提供して利用客数も肉の売上も伸ばしたという実績を持っているから、それを発展させて、さまざまな商品分野に応用するところまで持っていけば面白いのに...と思うが、どうだろうか。これまでの常識から外れない限り、これまでとは大きく異なる結果は得られない。 いつまでも商品をたくさん売ろうとするから、コモディティ商品ばかりになり、競争も価格競争中心に激しくなって、商圏も狭まるから、状況はどんどん悪化する。望むのとは反対の方向へ向かっていく。何十年も繰り返してきたことである。 広い面積を持つ総合スーパー(GMS)が体験型消費だけの売場に変わることができれば、商圏は確実に拡大するし、客単価も確実に上がるだろう。 日常生活に必要な商品を買う店でなく、家族、学生のグループ、会社の同僚などが「集う」ことができるスペースになれば、足元商圏以外からでも集客は可能になる。人が集まれば、イベント的な消費に変わるから、確実に客単価は上がる。企画まで提案すれば、バリエーション、商品もある程度コントロールでき、予約の比率を高めればロスも減るから粗利率は確実に上がる。 物売りにこだわらなければ、まだまだできることはたくさんあるはずである。 変化の方向は決まっている。体験型、参加型、自己実現型である。 食も衣も住も「できるようになれば本人は変わる・成長する・進化する」、皆が集えば「楽しい時間が共有でき、グループ内の状況は変わる」。 これ以上の「物の充足」は必要ではなく、いま必要なことは「状況の充足=進化・改善」である。
総合スーパー(GMS)の立て直しに関する「イオンとセブン&アイの、戦略の違いどちらに軍配?」という視点はマーケットを見ていない?
総合スーパー(GMS)の立て直しに関する「イオンとセブン&アイの、戦略の違いどちらに軍配?」という記事をヤフーニュースで見かけた。 目を引くタイトルではあるが、残念なことに、このタイトルにはマーケティングの概念がすっぽり抜けているように思えてならない。 そもそも総合スーパー(GMS)と一口に言っても、出店時期によって立地も違えば、規模も違うし、商圏構造、経費構造なども違う。要するに商圏人口だけを想定してできているから必ずしもマーケット、商圏に共通性があるわけではない。したがって、業績が不振だからと言って、全てを同じ手法で対処することには、どう考えても無理がある。 イオンリテールが「イオンスタイル」に切り替えて上手くいっている店があるというが、条件が違う店がそれで全て同じように解決するとも思えない。 イトーヨーカ堂が「ザ・プライス」への業態転換を図った時には、あえて条件の異なる店ばかりを業態転換するということをやっていた。結果的には上手くいく店・部門とそうでない店・部門があったから、一つの手法だけでは対応が難しかったようだが、いずれにせよ、マーケットの状況に応じて多くの引き出しを用意する必要があることだけは確かだろう。 地元とのこともあるが、少なくとも20年以上いろいろなことに取り組んできたこと、今後10年の間に起こる急激な高齢化と人口減少が地域によっては状況を様変わりさせてしまう場合があること、アジア、世界のハブシティ(国策)としての東京への一極集中がますます加速すること、....などを考えれば、地方都市で大規模な総合スーパー(GMS)が残ることはかなり難しいと考えるべきだろう。 現在、都市部に小型店舗が集中しているのは、大型物件の入手が難しいこともあるが、業績のことを含めて短期間にシェア・規模を確保したいこと、高齢化によって移動距離が短くなり、商圏が縮小していることなどが大きな理由であるが、結果としてコモディティニーズは高密度の閉鎖型小商圏を形成し、その中で完結するような方向に向かっていると考えてよいだろう。 一方、地方は広域のまま商圏密度が薄まる傾向にあるから、鹿児島県のA-Zスーパーセンターのように超大型店舗で超広域商圏を確保するか、中小規模で損益分岐点を極端に低く抑え、生産と一体化するなどして高利益率、高生産性を確保するなどしか生き延びる方法は考えられない。 最も難しいのが、コモディティニーズを対象とした大型店であり、経費構造が大きく変わらない限り、地域一番店でありながら経費負担に耐えられずに撤退ということもないとは言えない。ホームセンターのような専門性、特殊性とローコスト体質を持ち合わせていれば別だが、特徴のないことが特徴とも言える総合スーパー(GMS)では、固定費がネックになり、維持することが難しい。まさにこのような条件にあてはまるのが、総合スーパー(GMS)ということになる。 きれいな店舗、オシャレな商品も一時的には目先を変える意味でよいかもしれないが、いずれ飽きられることになるだろう。 インターネットやスマートフォンにはSNSや多くのプラットフォームが次々と生まれているから、さまざまな切り口で買い物ができるし、飽きることもない。また、交通機関の乗り入れや新線の開通で東京までの時間的距離が著しく短縮されているから、地元で我慢しなくても簡単に銀座や渋谷、青山、表参道などの「本物」へ行って買い物することができる。 重要なことは、イオンとセブン&アイのどちらに軍配が上がるかではなく、マーケットに対する読みと損益計算を考えた上で、条件ごとにどのような対応が有効かということだろう。 いずれ総合スーパー(GMS)単独店だけではなく、地方に数多く立地する総合スーパー(GMS)ベースのショッピングセンター、NSC(近隣型ショッピングセンター)なども似たような状況に陥る可能性がある。 アジア各国が、急激な高齢化と人口減少に直面する日本がどのようにこの状況を乗り切るのか、熱い視線で見守っているのと同様に、総合スーパー(GMS)が、この状況を如何に切り抜けるのかで、その後の中大型商業施設の方向は大きく変わると考えてよいだろう。 日本全国の市区町村についてもかなり詳細な分析をしているつもりだが、これからの10年を考えると地方の主要都市で、現在65歳以上の人口が20%代後半以上にある都市は、現在の人口規模に関係なく、総人口、生産年齢人口とも大きく減少することが分かっている。この傾向は政令指定都市といえども例外なく起こるから人口規模だけで安心することは禁物である。 場合によっては、人口が多い方がむしろインパクトが大きいかもしれない。また、大都市周辺にある衛星都市も大きな影響を受ける。東京都の求人倍率が直近で1.8台で推移しているのに対し、埼玉県と神奈川県は1.0未満である。他に1.0を切るのが北海道、青森県、鹿児島県、沖縄県だけであることを考えても大都市近郊にある衛星都市が受ける影響がどのようなものであるか分かるだろう。これと同じような縮図が市区町村レベルでも起こっているから、状況を冷静に把握しておく必要がある。 いずれにせよ、基本的な情報をベースにしてマーケットをシミュレーションした上で対応を考えていくことが重要である。
「いい大学を卒業すると将来、幸せになれる」と考える小・中・高校生が増加(ベネッセ教育総合研究所)という調査結果をどう考えるか。
第5回学習基本調査(ベネッセ教育総合研究所)が公表されている。(2016年1月28日)
多岐に渡る総合的な調査結果であるが、その中のChapter 3 意識 3-4[社会観・将来観]の項のタイトル(キャプチャー?)に『「いい大学を卒業すると将来、幸せになれる」と考える小・中・高校生が増加』というのがある。
確かにデータを見ると先回の調査(06年)から小・中・高校生とも10%以上数値が上がっており、特に小学生でその傾向が顕著である。
大学は4年間しかないから、実は小・中・高の12年間も大学同様以上に重要なのだが、その12年間は大学に入るための準備であり、大学に入って初めてそこで成果が得られるような錯覚があるのではないかと思う。
実際に大学と言っても就職試験などを考えれば、実質的には3年くらいしかないから、小中高の12年間と合わせた15年間を大切にするべきなのだが、小・中・高の12年間は「よい大学に入学する」という目的達成のための下積み生活、我慢の時間と位置付けられているように思えてくる。
スポーツ科学などでも、脳・神経系の発達は幼児期が盛んであり、6歳ぐらいで成人の約90%にまで達するという。12歳くらいからは心肺などの呼吸循環機能が発達し、筋量もほぼ大人と同じになるが、骨の発育にバラツキがあるため、成長障害を起こしやすい時期だという。
小さいからできないとか、大きくなったらもっとハードにというのではなく、発育の年齢に応じて適したトレーニングをすることが有効とされている。
脳の発達や人格形成を考えても小・中・高と年齢に応じて良い環境で刺激を受けて育つのと、枠にはめられて育つのでは大きく違ってくるだろう。
大学を卒業してもその後社会に出て40年以上は何らかの形で社会貢献し、収入を得ていかなければならないし、定年退職してもその後まだ15~20年は余命がある。そう考えれば、もっと社会とのつながりを想定した小・中・高・大学にしていかなければならないと思うが、実際には社会とは隔離され、教えている側・仕組を作っている側も一般的な社会経験に乏しい人達に偏っている。最近報道される多くのニュースを見れば、その内容からもムラ社会といって良いほど一般的な社会常識からは逸脱している。
大学に入ることが目的になる教育ではなく、自分らしさを確立し、社会に出ても自分らしく生きられる知恵を身につける教育が必要だろう。
特にこれからの時代を考えれば、人口が減少し、急激に高齢化が進んで、家族形態も単身世帯が大きく増えると予測されている。一生涯結婚しない男性が2割、女性も1割という状況にあり、これまでのような家庭環境を維持することは難しくなる。
一方では、デジタル化とグローバル化の進展がものすごい速度で進むことが予測されるから、大学だけを目標にしてタコツボに閉じこもって12年間を過ごしてしまうのでは、その後の状況に対応できない子供ばかりが育ってしまうという懸念がある。大人になって社会に出た後を想定した教育をしないと、皆が大変になるだろう。
何か違うモノを求めて大切な時間、取り返しのつかない時間と巨額な費用を費やすことはいろいろな意味で勿体無いことであるし、個人、社会、国家など様々なレベルでも大きな損失だろう。
サービス革命は20世紀型ビジネスモデルと21世紀型ビジネスモデルの交代を意味する!
インダストリー4.0、IoT、ICT、ビッグデータ、..、聞いたことがある人もない人も、知らないうちにいつの間にか自分がそのような世界の中いることを認識する必要がある。 トイレにセンサーを付けることで日常的に健康管理をする、あるいは冷蔵庫にセンサーを付けることで食材の在庫管理や日付管理をする、更に進化すれば、健康状態と合わせて、冷蔵庫にある食材や賞味期限を考慮して献立の提案や不足する食材、調味料などの自動発注まで行うというように、全てを自動管理してしまおうというような発想である。
すでにAIスピーカーによる入口の陣取り合戦がはじまっているが、昔は店舗の場所取りだったものが、今では個々人の日常生活の中にどれだけ密着できるかというインターフェイスの取り合いに変わっている。
24時間、365日、日常生活のあらゆる場面を想定すれば、対象となる範囲は非常に広い。しかも今までは物理的な物というパラレルなモノ・コトがデータ・情報によって密接につながっていくから、デバイス、センサー、データ・情報とサービスを組合わせてシステム化した企業が圧倒的多くを握ることになる。
様々な家電製品の使用状況から最適な使用状況、トータルなエネルギーコスト低減、メンテナンスなどを自動的にコントロールしたり、キッチン、バス、トイレに関する機器や使用方法に関するコントロール、自動車や家屋のメンテナンスに関するアドバイスなどは初歩的な話で、まだ20世紀のもの発想の延長線上でしかない。
家庭に常備するような消耗品は、改めて店舗に買いに行くことがなくなる、あるいは様々な物事は日常的にセンサーによってモニタリングしているので、改めて調べたり、調整したりする必要がなくなるなど、「生活の仕方=ライフスタイル」そのものが変わる。
ライフスタイル変化はある時急に始まり、気が付いた時にはそれが当り前になるような変化だろう。例えば、携帯電話、スマートフォンは日常的に手放せないほど重要な便利デバイスとして定着しているし、音楽はCDではなくWebからダウンロードして聞くのが当り前になっている。基本的に、これまで身近にあった「物」「媒体」がデジタル化することで「物」と「機能」は分離する。音楽は「CDという媒体に記録された信号を買って聞く」のではなく、「Webから聞く権利を購入する」ようにに変わった。「物を売る店」という物理的な建物は不要になり、それに代わって「サービス提供をするサイト」が必要になる。
物販はサービスに変わり、リアル店舗はWebに変わる。
いろいろなモノがWeb上のプラットフォームで繋がれば、プラットフォーム上でニーズとシーズのマッチングが可能になる。小さなニーズと小さな空き(隙間的な能力の余分)をマッチングすれば、改めて大きな投資をしなくても小さな空きをかき集めて巨大な能力として機能させることも可能になる。
ウーバー(タクシーもドライバーも持たないタクシー会社)、ラクスル(印刷工場を持たない印刷屋)などのマッチングビジネスがあらゆる分野に拡大すれば、巨大な投資をしないローコスト、高収益のビジネスモデルがたくさん出現する。
まさにサービス革命といえる状況が出来上がることになるが、その時には「店舗や工場などの設備という物」を事業の前提とするビジネスモデルは、物を持たないローコスト、高収益なビジネスモデルに脅かされることになる。
日本だけではなく、様々な国の成長にサービス革命が必要になることは確かだが、それとは引き換えに20世紀型の産業は大打撃を受けることになる。
すでにデジタル化によって物理的な物がなくなっている分野が増えているように、サービス革命は物中心の20世紀型ビジネスモデルとサービス中心の21世紀型ビジネスモデルの交代を意味している。
東京近郊に位置するベッドタウンの市長は、ホワイトカラーが多く住む当該市の将来を危惧している。ホワイトカラーが最も多くAIやロボットにとって代わられるとされているからである。大きな成長と引き換えに大きな犠牲が生じると考えている人は少なくない。 いま20~30歳代の人達は、自分たちが50歳代になった時、自分の業種・職種が存続可能なのか否かをよく考えてキャリアプランを組み立てる必要がある。
経営者は、新卒採用の責務として、彼らが無事定年を迎えられるよう、逆算してビジネスプランを組み立てる必要がある。
難しい選択であるが、どこかで意思決定しないと乗り遅れる。