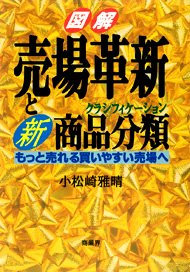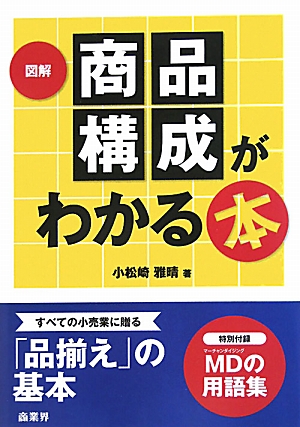平成27年3月2日、「生産性運動60周年記念パーティー(主催;日本生産性本部)」の席上で阿部首相がサービス生産性革命の必要性を訴えた。
サービス産業は「GDPと雇用の約7割」を占めるまでになっており、さらなる市場の創造、拡大が見込まれる重要な分野である。しかし、サービス産業の生産性は製造業や諸外国のそれと比べても低い状況にある。新たな成長を目指すには、ウエイトを高めるサービス産業の生産性を「革命」といえるほどに向上させることが不可欠になる。
ただでさえ我国は急激な人口減少・高齢化(生産人口減少)に直面しており、成長を持続するにはあらゆる分野の生産性向上が喫緊の課題である。
進化著しいIT、ロボットなど最先端技術の導入も期待されるが、中小零細企業が多いサービス産業の現状を考えれば、資金、人材面など現場導入にはハードルが多い。
そのような認識もあってか、6月18日「第1回サービス生産性向上協議会」では「小売」「飲食」「宿泊」「介護・福祉」「運送」の5分野について経営者、所管省庁担当者の参加に加え、トヨタ自動車など生産性の高い企業からの専門家派遣も決めている。
問題は、人口減少・高齢化の速度=生産性向上に与えられた猶予期間である。
いくら生産性が高い企業から派遣される専門家が世界レベルにあったとしても、受け手側であるサービス産業は、製造業とは全く異なる進化の仕方をしている。
例えば小売業であれば、パート・アルバイトという安価な労働力の比率を高めたこともあり、離職率が高く、勤続期間は短い。また、消費者との距離が近く、店舗間競争はダイレクトで変化が早いため、迅速な対応が求められる。
時間とコストをかけて人を教育するよりは、改装・増床して大型化、商品入替え、出店、新業態開発をする方が結果は早いし、数値も読みやすい。経費削減は、社員をパート・アルバイトに置き換え、さらに人数も減らす。粗利率を上げるには生産国を移す、大量発注する、PB比率を上げる。
チェーンストアという特性、経験から得られた経営スタイルは、個々の現場よりは全社的な仕組みを優先する。業界特有の状況、歴史、意識・感覚、価値観、制約条件、経営上の優先順位など様々な環境与件の違いは大きい。
いずれにせよ、限られた時間内で世界のトップクラスに登りつめるには、既存の事業、組織、体制、方法を改善するよりは、全く新しい事業を創出する方が明らかに早い。
現在、必要と考えられるのは、① 個別分野に関する高度な専門知識・技術(当該事業者だから専門知識・技術に詳しいとは限らない)、② IT(デジタル・ネットワーク技術)、自動化・ロボット技術、③ ①と②、あるいは異分野を結び付けて新たな価値・事業を創出するアイデア、企画力、④ ③を実現するための具現化技術、リアルネットワークを含む組織(実行部隊)などであるが、この中で唯一進んでいるのは②だけである。
他は全て一世代前のバージョンと言ってもよい状況にある。
最先端技術の導入、次世代を担うビジネスモデルを考えた時、当該分野の事業者・研究者の意識、経験・知識・技術・ノウハウでは不足する部分も多く、それを埋めるためには③、④の人材・事業者の育成が急務である。
シーズはあるが、シーズの活かし方が分からない・活かせる組織がない。プロデューサー、ディレクター、エンジニアが必要である。
流通革命時のチェーンストア、インターネット普及時のアマゾン、楽天市場、ヤフーなど、時代が大きく動いた時、変革者として業界に新風を吹き込み、過去の常識を覆して新たな成長の中心になったのは異分野からの参入者である。
既存事業者は店舗などの資産、人員(経験・知識・技術)、過去の経験・知識・価値観・判断基準・手法などが足枷となって、ドラスティックな転換ができない。
足枷となる資産も先入観もない新規参入者が新しい事業の中心となれる所以=持つ者の弱み、持たない者の強みである。
そう考えると、新規事業参入の推奨、参入者の育成、参入障壁の撤廃こそが新たな成長へのカギを握ると考えるべきだろう。
全く新しい視点から、サービスを科学していく必要がある。
◆「サービス」「サービス業」「サービス産業」
第一次産業(農林水産業)、第二次産業(鉱工業)に分類されるもの以外、商業、金融・保険、情報通信、運輸、不動産、飲食・宿泊、医療・福祉、教育、サービスなどの全てが第三次産業に分類される。
ただし、第3次産業以外にも「農業サービス業」「園芸サービス業」「専門サービス業」「技術サービス業」など様々なサービス業(請負)があり、それらは請負う本業の分類に入るから、第一次産業、第二次産業の中にも事業としてのサービス業が存在する。
また、産業分類にかかわらず、企業・組織には「サービス(間接)部門」があり、「サービス業務(作業・動作)」を行うことで「サービス(機能/効用)」を提供している。
「サービス」「サービス業」「サービス産業」「サービス部門」「サービス業務」…等々、いろいろな物事を「サービス」という一つの言葉で全て表わしているため、対象範囲、意味などは全く整理されていない状況にある。
一般的にサービス=サービス産業=第3次産業はGDP(国内総生産)と雇用の7割を占めるとされているが、それはあくまでも統計上の集計であって、様々な分野に分散するサービス業務、サービス事業まで含めれば、おそらく8~9割の間にあると考えてよいだろう。
サービスに関しては、事業、業務形態、機能から整理すると、大きく①水道、ガス、電気、運輸、通信など事業者が敷設した設備を用いた便益提供、②器具・備品・設備、自動車、会議室・ホール、ソフトウエアなどの使用権利の供与、③クリーニング、ヘアカットなどの機能代行(消費者・クライアントに代わって行う)、あるいは塾・教室などの機能支援(教育する、補助する)という3つに分けることができる。
統計処理上、集計単位としての産業分類は重要だが、業務の生産性向上を考えるには、上記のように事業、業務形態、機能をベースにして分けた方が分かりやすい。
特に生産性向上を目指すには、①~③のタイプにより、アプローチの仕方は変わるから、クラシフィケーションの考え方に基づいて、それぞれの特性に応じて類似するパターンをグルーピングし、対処する方が効率的である。
*現状では、サービスの定義もあいまいであり、様々な分野の研究者が、様々な立場から発言している。まさに百家争鳴といった状況にある。
確実に「科学する」必要がある。