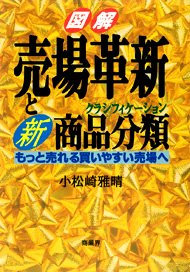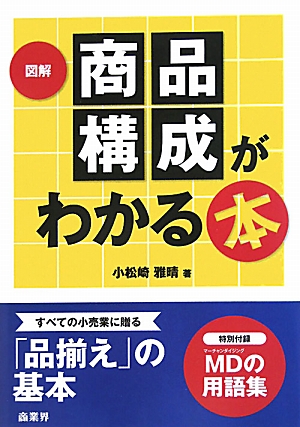チームプレーで成り立つスポーツを見ていると、組織として強いチームとそうでないチームがはっきりと見て取れる。
面白いのは、スポーツの世界では単に年齢や経験ではなく、能力が重要視されることである。たとえ中高生でもワールドクラスであれば、インタビューに答える内容、話し方、態度は下手な大人よりもよほどしっかりしているし、高校を出たばかりの20歳の選手が物怖じすることもなく、チームの中心となってタクトを振ることも珍しくはない。
能力を認められ、それなりの仕事を任せられると、早くから能力は開花する。若くして経験を積むことができればそれなりに進化もする。
若いから…、まだ早い、…と何もさせてもらえないよりは、持てるポテンシャルを十分に引き出すことができるから、本人にとっても組織にとってもメリットがある。
できる人でも一匹狼的な動きをしてきた人は、そのようなタイプのプロ集団なら能力を発揮する(それ以外は辛い)。同じようなタイプ、価値観の人達だけで結果を追求すれば、知らず知らずのうちに最善の方法を選択していく。理屈抜きで最後はどうにか結果を出すプロ集団である。
問題は、できない人、できるのに任せてもらえな人などが混在した混沌とした集団で、「規律」が与えられないケースである。
プロ集団は暗黙の了解という規律を持っているし、能力を認められ、若くして第一線で活躍する人も一定の秩序を見出している。相互にリスペクトしているし、阿吽の呼吸も持ち合わせている。
規律を与えないと自らを制御できない人達に規律を与えなければ、ただの寄せ集めでしかないから組織としては成立しない。
このような寄せ集めの共通点は、リーダー不在で規律がなく、組織以前に集団としても成り立っていないことである。
例えは悪いかもしれないが、「カリスマドッグトレーナー シーザー・ミラン」というアメリカのテレビ番組(YouTubuなどで見られる)に、この辺の真理が凝縮している。
すぐに吠えたり、噛みついたり、すぐに喧嘩を仕掛けたり、いじけていて他の犬と触れることができなかったり、…という問題を抱えた犬が、明確な規律と躾を与えらることで、とても穏やかな犬に変わり、他の犬とも仲良く一緒に過ごせるようになる。組織における自分の居場所とふるまい方を身につけることで安心できるのだという。
もともと社会的な動物であるから、群れのリーダーや序列が曖昧な状態でいると精神的に不安定になり、そのことが原因で問題行動を引き起こす。精神的に不安定な結果が問題行動として現れる。
まさに現代の人間社会、学校やママ友のいじめといった現象のメカニズムと解決法を「犬」の世界を通して解説されているような気がする。
群れをつくる社会的動物に共通する真理なのだろう。
この番組を見ている(シリーズはたくさんあってなかなか奥が深い)と、少なくとも強い組織を作るには、①リーダー、②規律、③自制という意味での躾、そして④相互にリスペクトできる状況が必要だということが分かる。
ポジティブな環境の中にいれば、黙っていても人は向上するから、無駄に「教育だ」「マニュアルだ」などと騒ぐよりは、組織としての良い環境を整備することに集中した方がはるかに有効と考えることもできる。
勉強は「工夫すること」だから、常に問題意識をもって工夫できる環境さえあれば、組織も個人も大きく進化する。下手に枠にはめ込んで強制しなくてもモチベーションが多くの物事を解決してしまう。
構成する人の能力を最大限引き出すことができる組織が強い組織と考えれば、まだまだ組織の能力を高め、強い組織を作ることはできるだろう。自分で進化できるだけでなく、組織の能力を引き出すことも重要な要素である。
Archive for wpmaster
強い組織をつくろう
チェーンシステムは小売業の財産 フランチャイズシステムで日本再生
「チェーンストアのコア技術は?」と訊かれて「チェーンシステム」と答えることができるのは、おそらくコンビニエンスストアの人達くらいだろう。
他の業態で、しかも店舗数があまり多くない、あるいは標準化(画一化ではない)できていない企業では「チェーンシステム」と言っても実感としてあまりピンとこないかも知れない。
チェーンストアの中にいると、それが当り前になるから、改めて意識することはないかもしれないが、チェーンシステムを他の分野に応用することができると、様々なことが画期的に変わる。
例えば、農業にフランチャイズシステムを応用すれば、個人を巻き込んで急速にシステム化することも可能になる。システムは、全て画一である必要はないから、地域特性に応じて、年間の作物を全国ネットでコントロールすることが可能になるだろう。
農機具、農薬、肥料、種苗、出荷などあらゆる分野に最先端のシステムを持ち込むこともできるようになる。
資本、システム、様々な研究成果をシステム的に運用し、さらにマーケティング、販売先などが統合されれば、ビジネスとしての生産性は高まり、競争力、進化速度も増す。
また、地域興しを前提とした各地域の農業試験場の持つノウハウを交流することで、グローバルな産業にすることも容易になるだろう。
同様に魚の養殖に活用しても高い効果が望める。
さまざまなネットワークを活用し、コンビニエンスストアが一大産業になったように小規模事業を統合することができれば、農業も水産業も近代化し、一大産業とすることも可能だろう。まさに日本再生を目指す上でキーを握るシステムと言ってもよいだろう。
チェーンシステムが持つ内容を改めて整理してみれば、マーケティング、販促、商品企画・開発、商品流通チャネル、物流、情報システム、販売、店舗運営、多くの事業所を統括するマネジメントとオペレーション、教育・マニュアル、….等々、短期間のうちに事業をシステム化し、拡大することができる要素が全て揃っている。
急激な高齢化と人口減少によって、固定された数多くの店舗の運営が難しくなることは容易に想像できる。
自社の重要な資産でもあるチェーントステムを店舗と共に陳腐化させてしまうのが、全く別の分野で有効活用するのか、経営としての先見性、経営の力が試されることになるだろう。
OTB(Open to Buy)で売場経営
放っておくと、勝手に発注するからどんどん在庫が増える。在庫が多すぎるから発注を減らせというと、一気に発注を減らすから欠品ばかり増えて売上が落ち、在庫は全然減らない。 何十年も前から繰り返してきたことであるが、いまだに同じことが起きているから、小売業はほとんど進歩はしていないことになる。 バイヤーが自分が仕入れる商品、自分が組み上げた商品構成に自信がないとアイテム数が増える。発注担当者が自分の発注に自信がないと、発注数量を必要以上に増やすから、やたらと在庫が増える。 何十年経っても変わらないのは、人間の本質がそこにあるからだろう。 発注して商品を取り、売れて残ったのが在庫、というのは時間の流れから言えば正しいが、仕事として売場で商品を販売するのであれば、はじめに商品の販売計画が必要になる。 販売計画通りに売上を上げるのに必要となる在庫数量、それだけの在庫を持つために必要となる発注数量という手順で発注が行われる必要がある。 「はじめに販売(売上)計画ありき」である。どれだけ売るのかという目標、計画もないのに在庫数量を設定できるわけがないし、いつ、在庫を切り上げるのかという目標、計画もないのに発注ができるわけはない。 OTB(Open to Buy)の理屈はいたって単純である。これだけ売りたい、だから在庫はこれだけ必要になる。不足する在庫は、これだけだから、その分を発注する。これだけの話である。 ただし、販売(売上)は必ずしも計画通りにはいかない。予定より増えることもあれば減ることもある。売上が増えれば、在庫が予定よりも減るから、その分発注を増やす。逆に売上が予定よりも少なければ、在庫がオーバーするから、その分発注を減らして在庫と売上のバランスを調整する。 OTBは、仕入枠管理のための在庫管理手法と紹介されている本も多いが、実際に使ってみれば、売上と在庫のバランスを維持するための手法であることはすぐにわかる。
具体的には図表「OTBとは何か」に詳細に示したので、実際に試してみると理解しやすいだろう。また、Excelフォーマットについても「OTBフォーマット例」に示したので、参考にするとよい。
Zチャートなどもそうだが、実際に使ったことのない人が、知識だけで本を書くとZを1つか2つ書いて説明する。実際にやってみれば分かるが、それではZチャートの意味をなさない(トレンドを見る移動総和のデータが少なすぎる)。 OTBも全く同じで、売上、在庫、仕入の関係を理解した上で、売上と在庫のバランスを調整する手段として仕入=発注を用いる。 したがって、OTBによって管理するのは売場の健康管理=売上と在庫のバランスであり、仕入枠管理でも在庫管理でもない。 バランスは、売上が増える際には先行して在庫を増やし(当然仕入れ、発注も増える)、売上が減る時には先行して在庫を減らす(当然仕入れ、発注も減る)ことによって維持する。 売上が増えたら発注を増やし、売上が減ったら発注を減らすというやり方では、在庫は増えたまま減ることはない。多くの人が一度や二度はこのような失敗を経験する。 気持ちとしては、分かるが数値化してみると、それでは在庫がコントロールできないことが分かる。エクセルを使ってシミュレーションしてみればすぐにわかるが、売上と発注を同じように増減させると在庫はほぼ一定で推移する。このようなことをしてもよいのは、在庫を持たない生鮮食品だけである。 OTBは売場経営の一番の基本であり、もし基本を知らずに運用されている売場があればすぐに修正すべきである。 いまは、数量で説明をしたが、実際の商品仕入れと支払いの関係(金額)を考えれば、在庫が過度にオーバーすれば、支払う金額が不足するし、逆に少なくなり過ぎれば、売上が減りすぎて、固定費の負担に支障をきたす。 数値を見て「難しい」という人もいるが、難しいがどうかという話ではなく、これが小売業そのものであるから避けては通れないだけの話である。
POSの進化を50年遅らせたJANコード
◆事務効率化、SKU識別が目的のシステム設計
JANコード13桁を見てわかることは、SKUの識別=事務の効率化を目的としたシステムであるということである。
情報システムには大きく分けて、オペレーション用のシステムとマネジメント用のシステムがある。
オペレーション用のシステムは、一度入力すれば、再入力する必要がないという情報システムの特徴を生かして、大量に処理する事務手続きの効率化を目的としたシステムである。
現在のJANコードによって運用されるEOS、EOB、POSなどのシステムがまさにこれである。
JANコードによって、発注、納品、運搬などに関わる伝票発行、検収、レジ登録などにおける手作業が自動化され、事務効率は著しく向上した。
一方、マネジメント用のシステムは、様々なデータを加工することによって、管理する上で有効な情報、意思決定をサポートする情報を提供する。
例えば、商品構成改善、レイアウト改善、人員配置改善、生鮮食品などの生産スケジュール改善などのサポートである。
ただし、情報システムでは、予めどのような単位でどのような集計をするのかを決めてフラッグを立てておかなければ、集計することはできない。
JANコードの13桁が集計に用いることができるフラッグということになる。ただし、JANコードでは、マネジメント用に集計して有効と思われる桁は皆無と言ってよい。
POSが一般にまだ普及する前、タグシステムを使っていた時代にバイヤーをやっていたが、自由に使える5桁(色・サイズ・取引先コード以外)を使って、商品のグルーピングを行い、売れた商品を管理していた。
5桁あれば、素材、デザイン、商品シリーズ、….、プラス通しNo.など、自分で管理しやすいようにコードを設定することができ、少なくともバイヤーが知りたい要素の中から、特にその商品で重要となる要素を抜き出してコーディングすることができた。また、そのような工夫をしていた人間が現場には数多くいたし、そのようなノウハウが現場にはたくさんあった。
POSが普及し、コードは13ケタに増えたが、ほとんど意味をなさないコードが並んでいるから、商品をSKUとしては機械的に識別できるが、目的に応じてフレキシブルに集計するということがができなくなった。
5桁の時に分かっていたことが、13桁になった途端、何もわからなくなってしまった。
一時期、SA(stoa automation)という言葉が盛んに使われ、POSが普及すれば、売れる商品、良い商品構成が自動判別、あるいは自動作成され、売場はSA化によって見違えるように変わるという淡い期待と錯覚があった。しかし、機械化が進むにつれて、進化したのは機械的なオペレーションだけであり、売れる商品を見つけ出す現場の工夫、ノウハウは、機械化=JANコードの普及と共に失われて行ってしまった。
基本的に情報システムには、「手でできる仕組みをつくってから機械化」と言われるように、手作業で出来るもの以外、形作ることは難しい。
POS=JANコードではマネジメント用の情報システムはできないという問題点は指摘されることなく数十年が経とうとしている。
ここまでくれば、あとはビッグデータとAIの世界ということになるが、ここでもデータサイエンティストの不足が指摘されているように、「手でできる仕組み」を創れる人間は大きく不足しているから、本質に迫ることはなかなかできないだろう。
もし、タグシステムが5桁でできていたことの一部でも、POS、JANコードを設定する際に考慮されていれば、現在、日本の小売業とPOSシステム、そしてビッグデータとAIの進化の仕方は全く違ったものになっていただろう。
一つの選択が時代を大きく変えてしまったことは残念なことである。
マネジメントに不可欠な商品属性を排除、
47都道府県を含む全国1858の自治体の人口減少と高齢化の状況②
2010年人口が3万人、5万人、7万人、10万人、15万人、20万人、25万人、30万人規模の自治体の中から2040年の総人口指数(2010年=100)が100超(人口が増える)と60~70の自治体をランダムに選んで比較してみた結果、人口減少、高齢者の増減については、自治体の人口規模よりは65歳以上人口率(年齢構成)の方が影響が強いようである。
小売業が店舗配置をする際、人口規模を基準として行ってきたように、多くの人達が都市の評価を人口規模によって行ってきたというのが一般的だろう。
しかし、どうやら重要になるのは、年少、生産年齢、老年の年齢3区分の人口構成であって、現在の人口規模だけで将来の自治体の姿をイメージすることは間違いのようである。
今回、試しに2015年65歳以上人口率(総人口に占める割合)をベースにして2025年時点の人口増減(2010年=100)を調べてみた。
2015年65歳以上人口率ごとに見ていくと、◆65歳以上人口率18.0%以下、2025年人口指数91.0-118.1、2015年人口191-237,451人・平均79,333人(22都市)、◆同19.5-20.4%、同94.2-114.1、同6,518-1,468,329人・221,133人(32都市)、◆同24.5-25.4%、同84.4-105.7、同6,284-2,288,845人・194,208人(90都市)、◆同29.5-30.4%、同80.1-97.7、同1,195-961,748人・69,492人(90都市)、◆同34.5-35.4%、同73.6-89.7、同1,442-115,972人・26,216人(77都市)、◆同39.5-40.4%、同69.5-86.4、同1,751-57,909人・13,016人(40都市)、◆同44.5-45.4%、同62.6-78.6、同325-37,052人・8161人(23都市)、◆同50.0%以上、同50.1-60.9、同441-16,838人・3,252人(17都市)
これから分かることは、以下の点である。
①2015年時点で65歳以上人口率が集中している都市(上記の都市数が多い)は、25%、30%、35%であるが、平均人口が多いのは20%、25%であり、30%を超えるにしたがって平均人口は少なくなる。また18.0%以下も平均人口は30.0%と同程度であり、決して大都市というわけではない。
②65歳以上人口率が高まるにつれて、2025年人口指数が低下する(人口の減り方が大きい)。また、平均人口も小さくなる(小規模都市)傾向が明確である。
③2025年という10年後を見る限り、人口の減り方は、ほぼ現在の65歳以上人口率に比例する。もともと都市の規模は小さい方が多いので、それに比例した形で現れる傾向にあるが、今回、特に都市数が多かった25.0では5万人以下、30.0%では2万人以下、35.0%では6万人以下が多くなっており、2025年総人口指数の平均値に近いところに集中する傾向が見られた。
言い換えると、2015年65歳以上人口率の似た都市を集めてみると、人口規模に関係なく、2025年には同じような人口の減り方をするということになる。
個別には、いろいろと都市の状況があると考えられるが、基本的に自分が住むエリア、ビジネスを展開しているエリアを評価する際には、現在の人口規模よりは、むしろ現在の65歳以上人口率をベースに見た方がよいということになる。
その時々で変わる「良い」商品構成
◆客層、お客の目的・オケージョン(時、場合)で変わる「良い商品構成」
商品構成の良し悪しは、客層(性別、年齢、職業、所得、家族構成、ライフスタイルなど)やお客の目的・オケージョン(時、場合)などによって変わる。
例えば、日常的な生活必需品の買い物とただ目的もなくお店を見て回るウインドウ・ショッピングでは、明らかに買物の目的が違うから「良い」という意味・基準が違うのは当然である。
日常的な買い物では、自分が当事者であり、自分にとって必要な商品、買いたい商品が品揃えされていることが第一になる。
一方、ウインドウ・ショッピングでは第三者的な立場から見ているため、自分が買う、買わないということとは関係なく、見て「良い商品」「楽しい商品」があることが重要になる。したがって、第3者的な立場から見て良い商品があると評価することと自分が買うということは一致しない。
日常的な買い物の中でも客層、お客の目的・オケージョン(時、場合)違いによっての「良い商品構成」の基準は変わる。
例えば、靴下でも、中学生と高齢者では欲しいと思う商品は違うし、同じ中学生でも通学時に履く靴下とオシャレをして出かける時に履きたい靴下では明らかに違う。
対象となるお客が変わることでニーズが変わり、同じお客でも目的・用途が変われば、またニーズが変わる。
したがって、総てのお客、総てのニーズに対して必ず応えられる「商品構成」を実現することはほぼ不可能と言ってもよい。
特に限られた売場面積、限られた在庫予算枠の中で総てのことに対応しようとすれば、結局どれも中途半端になるから、予め目的を明確にし、商品構成で対応する範囲を明確にすることが「良い商品構成」を実現するポイントになる。
◆物発想か、マーケット発想か
従来の商品構成に対する考え方、やり方は、どちらかと言えば仕入れる側、商品側から見ており、物発想と言うことができる。そのため、POSデータだけを拠り所として販売点数の多い商品中心に品揃えを強化したり、低価格で数多く売れる商品中心に品揃えしたりという偏った品揃えをする傾向が強くなっている。
見方を変え、買う側のお客がどのような人(性別、年齢、職業、所得、家族構成、ライフスタイルなど)で、どのようなオケージョン=ニーズを持っているのか、というマーケット発想の視点から見ると、また違った「良い商品構成」が見えてくる。
例えば、客層に高齢者が多い場合、予めゴムを緩目に設定し、脱ぎ履きしやすいだけでなく、履いている時にも足首を締め付けないような工夫がしてある靴下、あるいは保温性が高く、かつ吸湿性、速乾性に優れた素材の靴下、..など、機能品中心に商品構成をするということも重要になる。
しかし、もしこれらの商品が扱われていなければ、どんなに精度の高いPOSデータを駆使しても、そこから良い商品構成を見出すことはできない。
言い換えれば、お客側の視点から見た「良い商品構成」をPOSデータだけでつくり出すことは実質的に不可能ということになる。
◆時間とともに変わる「良い商品構成」
商品構成の良し悪しは、時間によっても変わる。多くの時間をかけ、データもたくさん分析し、綿密に商品構成の計画をつくったとしても、一番重要なタイミングを逸してしまえば、せっかくの努力も意味がなくなってしまう。
例えば、一般に良く知られるのが惣菜売場である。昼の米飯、夜の惣菜と言われるように昼は弁当の比率が高く、夜は夕飯のおかずとなる揚げ物などの惣菜のニーズが高くなる。
時間帯によってニーズが変わるから、ニーズの変化を的確にとらえた品ぞろえをする必要がある。
*以前、「開店時100%品揃え」ということが食品スーパーではやったことがあった。あるスーパーは、朝10時から刺身の盛り合わせを冷ケースに目いっぱい並べていたが、別のスーパーでは「売れる時に売れる量が100%だから」という理由で朝から刺身の盛り合わせを目いっぱい並べることはしなかった。
①季節商品 ; 暖房用品、冷房用品、入園入学用品、異動・引越し用品などは、様々な理由により、特徴的な動きをする。例えば、入園入学用品の場合、年内にギフト用のセット物や高額品がクリスマスプレゼントやお年玉のタイミングでよく売れ、ピークに入ると自家用の一般的な商品が売れる。また、ノートのように学校が始まってから先生が指定するものもについては、先生の指定を待って、指定されたものだけが売れる。
引越し関連では、引っ越し前と引っ越し後に入居先で買うものは異なる。例えば引っ越し前に必要なのは、掃除用品や梱包用品、入居先で家具を入れる前に敷くカーペット類、照明器具などである。一方、入居後に買う、あるいは買い換えるのは家具、収納用品、照明器具、カーテン、その他小物類などである。
大学の近くでは、入学後少し落ち着いた4月の第2週が自転車のピークになるとお店の担当者に聞いたことがある。
商品の動き方を細かく見ていくと、どの商品にも必ずそのような動き方をする理由がある。理由の多くはお客の状況であり、お客の状況と商品の売れ方の関係が分かれば、同じ季節商品でもタイミングごとにどのような商品構成、売場づくり、売り方をしたらよいかが分かってくる。お客の状況に合わせた商品構成がよい商品構成と言うことができる。
③習熟する商品 ; ペット用品、園芸・ガーデニング用品、レジャー用品などは、消費者が習熟することによって市場が変化していった典型的な商品である。
例えば、1990年ごろからアクアリウム(熱帯魚や水草)のブームが起こり、数多くの人が水槽を買い求め、熱帯魚を飼い始めた。初心者にとって、必要なものはインテリア水槽をはじめとする用具一式であるので、ブームのはじめは水槽や用品類がたくさん売れた。
徐々に慣れてくると、はじめに買った水槽(多くは60cm)では物足りなくなる人も現れ、大型の水槽が売れるようになる。魚も初心者用のグッピー、ネオンテトラからもっとマニアが好むような魚種を求めるようになる。
習熟するにしたがって志向はより専門的になり、誰もが求める一般的な商品から一部の人しか必要としない特殊な商品へとニーズが細分化していく。いつしか、初心者向けの商品構成では、お客を満足させることができなくなる。
つまり、当初はホームセンターなどの量販店が得意とする量販商品中心にマーケットは拡大するが、ある程度専門的になれば量販店だけでは難しくなり、コンセッションやテナントで専門店を入れて商品構成を補うように変わって行く。しかも一通り用品類が普及してしまうと金額がかさむ商品は売れなくなり、単価の低い消耗品中心にマーケットニーズは変化していく。
消費者が習熟していく場合、状況に応じて商品構成を変えていかないと、お客のレベル、ニーズに対応することができなくなる。
そして何よりも難しいことは、一般に普及する時には皆一様で良いためにマーケットは同じ商品が大量に売れて拡大していくが、習熟して細分化し始めると、個々のマーケットも細分化して小さくなってしまうことである。
当然、マーケットが拡大する時に貢献し、潤ったホームセンターなど、一般商品の大量販売を得意とする業態は、消費者の習熟とともに対応できなくなり、ブームの終焉を加速させる要因の一つになってしまう。
ただ単に物を売るだけでは終わらない分野で繰り返されてきた小売業とマーケットの矛盾である。
商品を科学する-② 商品の持つ特性による整理
◆商品のもつ特性による分類
商品には、さまざまな特性がある。商品特性とお客のニーズ、あるいは購買動機などとの関係を整理することができれば、どのようなお客(性別、年齢、職業など)に、どのような商品を提案すればよいのか、ということも分かりやすい。
商品のもつ特性は様々であり、それらは次のように整理することができる。
①衣食住余
a.衣料品
衣料品は、着るもの全般が対象であり、品種(アイテム)、デザイン、素材、色・柄、サイズ、ブランドなどの他、用途・機能、対象(性別・年齢)などの特性がある。全体的には、どんなに消費者ニーズが多様化したと言っても、ひとたびデザイン、素材、色・柄、ブランドなどのブームが起これば、多くの人が似たような商品を買い求める傾向にある。
b.食品
生鮮食品、米、パン、日配商品、惣菜、一般食品、菓子、飲料、酒類など飲食全般である。購買頻度が高く、旬、鮮度、味、産地などが重要となる。
管理面での大きな特徴として、賞味期限などの日付管理、生鮮食品・日配食品・冷凍食品などの温湿度管理などがある。
健康に対する意識の高まり、テレビ・雑誌などマスコミの影響力によって、「血液をサラサラにする」「血圧を下げる」食品として紹介されると、一気に商品の意味が変わり、売上が大きく変わる。「身体に良い」という情報が食材選択に大きな影響を持つようになっている。
生活習慣病の一因でもあり、同時に生活習慣病改善のための有効な手段でもある食品は、高齢化と健康に対する意識の高まりから、大きく意味を変える可能性を秘めた商品である。
c. 住(生活)関連商品・余暇関連商品
経済的に豊かになるにしたがって、食品からスタートしたマーケットは衣料品に移行し、さらに住(生活)関連商品・余暇関連商品へと広がりを見せていると言えるだろう。
ノンフーズという曖昧な位置づけから、「生活・余暇関連」へと概念を広げ、現在では、H&BC(Health and Beauty Care;美容と健康)分野もマーケットが大きく広がっている。
カーテン、カーペットなどのインテリア用品、収納用品、家具、家電製品の他、生活をする上で必要となる寝具、調理・掃除・洗濯などの家事関連用品、浴用品、トイレ用品、衛生用品、文具など学用品、玩具・ホビー、ペット用品、園芸・ガーデニング用品、DIY用品、防犯・安全用品、防災用品、介護用品、カー用品、レジャー用品、スポーツ用品、健康器具、書籍、CD・DVDなどのAVソフト、ゲームソフトなど実に幅広いジャンルを網羅している。
新しい概念・分野が生まれる可能性の高い分野であり、「衣料品、食品を含む生活・余暇・美容・健康・エイジング・情報通信・オフィス全般」というように、消費者を取り巻くあらゆる分野へと概念が広がっている。
住(生活)関連商品の場合、その性格から機能(どのような働きをするか)、用途(どのような使い方をするか)という商品特性に特徴があるが、最近では情緒的な要素(ブランド・デザイン・色・素材など)のウエイトも高まり、より複雑化する傾向にある。
② 年間商品/季節商品
年間商品は、1年を通して安定して売れるので売上のベースをつくる商品、季節商品は短期的に集中して売れるが、天候(冷夏・暖冬など)などに左右されやすいので、季節に応じて売上を上乗せする商品と位置づけることができる。
この2つをうまく組み合わせて使うことで効果的に売上をつくることができる。
a. 年間商品
身近にある商品を見回しただけでも肌着・靴下、調味料、スナック菓子、カップ麺、ティッシュペーパー、食器洗剤など数多くの年間商品がある。これらの商品について1年52週間の売上推移を整理してみるとチラシや季節、気候による売上の変化を見ることができる。以前、日用品を調べた時には、どんなに年間変動の少ないと言われる商品でも、週間販売数量の最大値と最小値の差は2倍以上ある。状況に応じて変動のあることを前提にして取扱う必要がある。
b. 季節商品
衣料品では夏の水着や冬のコート類、食品では季節の果物、竹の子、タラの芽など旬の食材、鍋物商材、クリスマスケーキなど、住(生活)関連商品では殺虫剤、花粉症関連商品、入園入学用品、クリスマス用品、冷暖房用などが季節商品に位置づけられる。
中には、品種改良、温室栽培などによって年間供給されるようになった野菜・果物、ライフスタイルや住環境の変化によって年間消費するようになったアイスクリーム、暖房の普及により年間を通して売れるようになった殺虫剤のように、季節商品であったものが徐々に環境が変わり、年間商品として定着していく商品も増えている。
③ 耐久品/消耗品
耐久品、消耗品という分け方は購買頻度や買上点数を考える上で重要である。
一度買うと、長年使える商品であれば買い替えが起こるまで次の商品を買うことはない。一方、買ってもすぐに、あるいは一定期間経てばなくなってしまう商品は、すぐにまた次の商品を買う必要がある。この違いは購買頻度=客数や買上点数、あるいは単価、販売する際の接客の要・不要などと密接に関係する。どちらを中心に扱うかによって商売の形態は大きく変わる。
a.耐久品(耐久消費財)
テレビ、洗濯機、冷蔵庫など、比較的高額であり、長期間使う商品であるため、商品購入に当たっては、機能・性能・操作性など、十分な理解と納得が重要な意味を持つ。万が一納得しない商品を購入してしまった場合には、不満を抱えながら長年使い続けるか、費用を無駄にしても新たに商品を買い替える必要がある。しかも廃棄時には新たにコストも発生するから、商品購入にも大きなリスクが発生する。したがって、商品決定までに十分な時間をかけ、納得した上で商品を決定する必要がある。
b. 消耗品
洗剤、ティッシュペーパーなどの商品である。購買頻度、量とも多いため、よりよい商品をより安くというのが基本になる。メーカー、ブランドによる商品格差が少ない、あるいは分かりにくいため、チラシ掲載、価格訴求、 陳列・演出・POPなどの売場づくり、売り方が購入商品決定に大きく影響する。
④最寄り品/買い回り品
最寄り品は「消費者が品質・価格をあまり比較検討せず、もよりの店で買うことが多い日用必需品などの商品。(広辞苑)」、買い回り品は「呉服・耐久消費財のように、品質・価格などを顧客が十分に比較検討して買い求める商品。(広辞苑)」と説明されている。
ただし、最寄り品、買い回り品という言葉が成り立ったのは、はるか昔の店も商品も少ない時代のことであり、現在のように店も商品も情報も溢れる時代には、実態にそぐわなくなっている(というのが、一般的な解釈である)。
⑤実用品/嗜好品
実用品、嗜好品という言い方も最寄り品、買い回り品と同様に現状でには、微妙なとらえ方である。
どちらかというと実用品という言葉には「実際に役に立つことが重要で、デザインや色など商品としての他の要素は二の次」といったニュアンスがあり、嗜好品には「栄養摂取を目的とせず、香味や刺激を得るための飲食物。酒・茶・コーヒー・タバコの類。(広辞苑)」というように本来の目的とは異なる意味合いで摂取される飲食物という意味で用いられる。
従来の対立概念から、両方の要素が融合した商品へとお客の志向も商品づくりも変わっており、実用的でありながら嗜好性のある商品、嗜好品でありながら実用的な側面を併せ持つ商品というのが、「新しい商品に対する考え方」である。
「実用品は、皆が買うからたくさん売れる」「嗜好品は限られた人しか買わないからあまり売れない」という考え方も、使用頻度や対象(それを使う人)・用途の広さというとらえ方に変得る必要がある。
⑥NB(National Brand)商品/PB(Private ブランド)商品
ブランド(Brand)は、もともと製造元、所有者、品質・等級などを表わす焼印、刻印を意味する言葉であり、そこから派生して、商標などブランドと呼ぶようになっている。
a. NB(National Brand; ナショナル ブランド)商品
有名メーカーが全国的に統一のブランド名で販売し、消費者にもよく認知され、信頼されている商品である。多くの場合、販売価格、あるいは卸価格に一定の枠組みを設けており、小売段階で自由に販売価格を設定することが難しい。安い価格で販売すれば確実に売上が見込めるため、確実に集客でき、しかも売上が見込める数少ない商品としてチラシに多用される。ただし、NB商品をチラシに多用すれば売上は見込めるが、荒利率が低下するというジレンマがあり、多くの小売業がPB商品のウエイトを高めるきっかけともなっている。
b. PB(Private Brand;プライベート ブランド)商品
小売業などが自社で企画・製造し、自社名で販売する商品であり、そのメリットは、次のように整理することができる。
イ.商品の企画が自由にできるので、他社では扱えない独自の商品をつくることができる。素材、色、デザイン、構造、機能、製造方法などを独自のものにすることで、他よりも優れた商品や他よりもコストの安い商品をつくることができる。
ロ.中間マージンが省けるので、商品原価が下がり、値入率を高く設定することができる。また、自社独自の商品のため、価格を横並びで比較されることもなく、原価についても他からは分かりにくい。価格設定=値入設定が比較的自由になる。
ハ.無印良品が、もともと西友のPB商品からスタートしているように、PB商品をうまく用いることで自社独自のアイデンティティ(自分らしさ)をつくりだすことができ、価格とは全く異なる方法で他社との差別化を図ることができる。
⑦プロパー商品/特売商品/チラシ掲載商品 定番商品/スポット商品
売場で扱う商品には、さまざまなタイプのものがあるが、それらの商品に対する呼称や扱い方は個々の企業によってマチマチである。
商品を「取扱い方」によって体系的に整理すると次のようになる。
a. プロパー商品
プロパー(proper)という言葉には、もともと『…が正しい、正当である、正規の、正式の』という意味があり、プロパー商品は『正規の価格で販売している商品』、特売商品に対して価格を下げていない『通常価格の商品(普通品などとも言う)』という意味で使われる。
商品は、大きくプロパー商品と特売商品という2つに分けることができる。
プロパー商品は、売場イメージや業績を決める骨格とも言える商品であり、通常、売場面積・在庫金額・売上高の80%以上、荒利額ではそれ以上を占める最も重要な商品である。
よく売上が低迷すると、チラシや特売商品によって売上の回復を図ろうとするが、プロパー比率が80%以上あることを考えると、改善する必要があるのは、プロパー商品の内容・在庫の持ち方、売場づくり、売り方などであり、特売ではどんなに頑張っても抜本的な対策にはならない。。
b. 特売商品
価格訴求によって売場にアクセントをつけ、お客の購買意欲を刺激する商品である。中には原価割れをしてまでも強烈な価格を打ち出すことがあるが、一方ではプロパー商品よりも高い値入率の場合もあり、実にさまざまである。
特売商品の主な役割を整理すると次のようになる。
イ.集客アップ。ただし、現状ではよほどのことがない限り、特売商品だけで集客を維持することは難しくなっている。
ロ.衝動買いによる買上点数アップ。ただし、単価の低下を招いたり、プロパー商品の売り上げ低下を招くなどのデメリットもある。
ハ.「得な買い物をした」「よい買い物をした」とお客に満足してもらうことで、買い物の楽しみを知ってもらうと同時にまた買いに来てもらえるような体験をしてもらう。その場の売上も重要だが、次へつなげることも重要である。
c. チラシ掲載商品
チラシ掲載商品=特売商品と思いがちだが、新商品・話題商品・季節商品・改装後の新規取扱商品・イメージづくりのための商品などプロパー商品もチラシ掲載の対象である。
d. 定番商品
定番商品は、商品アイテム、フェイシングなどを固定して継続的に扱う商品である。
プロパー商品の中心を成し、売場を構成する商品の中で最も重要な商品である。定番商品が決まることで自動的に部門の売上金額、在庫金額、荒利率、商品回転率などの大枠が決まる。
定番商品はアイテム単位で追加発注し、常に在庫を一定水準で安定させることができる。また、チラシ掲載、商品入れ替え以外では値下げが発生することも少なく、荒利率も計算しやすい。したがって、定番比率が高く、定番管理がしっかりしているほど売場の商品ロスが少なく、荒利率、商品回転率など効率を表す数値が高くなる。
e. スポット商品
スポット商品は、一定のアソートメント(商品の組合せ)で投入し、基本的に追加発注をしない商品である。スポット商品を多用すると、残った在庫が偏り、売上の低下を招いたり、不良在庫の処分のために値下げが増えたりするので、使い方に注意する必要がある。
商品を科学する-③ 商品の企画、開発
◆商品の企画、開発
商品を企画、開発する上で重要なことは、マーケットのニーズを上手くとらえることである。ニーズというと分かりにくければ、「不便なこと」「困っていること」と考えるとわかりやすい。
例えば、洗濯物を干す時に使う四角ハンガーやピンチ類は色や形が限られている。いろいろやっているうちに一定の形に収束したのかもしれないが、それは一定価格の範囲内に縛っているためとも考えられる。多少、価格が高くても色が変わったものが出ると一時的にでもよく売れるから、消費者は変化を求めていると考えてもよいだろう。
ただし、「ニーズ」という点から考えると、多少色が変わっても「実用的」で「安価」な「使い捨て」商品であることに変わりはない。
問題はいろいろとある。例えば、紫外線の影響で、使っているうちにピンチが割れてボロボロと壊れてしまう。洗濯物を干す際に大きさ、形の似たものをまとめないと綺麗に干せない。干す時も取り入れるときも一々ピンチをつまんで開かなければならないから手間がかかる。…..等々である。
しかし、多くの人が、四角ハンガーやピンチは「こんなもの…」と思っているのだろう。作る側、販売する側も「こんなもの…」と思って同じものを作り、売り続けているから、何十年経ってもそれを超えるようなものは現れない。洗濯機が乾燥まで一貫して行うことで洗濯物を干すことも減ると思えば、改めて開発するほどの価値がある商品ではないのかもしれない。
だいぶ前になるが、テレビ通販で雨の時などにサッと一度で洗濯物を取り入れることができる数千円のハンガーが売られていたことがある。ピンチを回転式にしたことで干す時も外す時もワンタッチでできるというのがポイントである。価格から言えば通常の四角ハンガーの20倍くらいだったと思うが、よく売れていた。(高額品であっても素材は同じだから、紫外線でボロボロになった時には辛いだろう)
日頃の不便を解消する商品は価格に関係なく売れるということが実証されてたことになる。
新しい商品を企画し、開発する際には大きく分けて2つのパターンが考えられる。
一つは、既存商品の改善、改良である。現物があるから、実際に使った結果として悪い点を改良していけばよい。
改善、改良を加える場合、ただ漠然と商品を見ているだけでは良いアイデアは生まれてこない。使い勝手(操作性、重量、形状、大きさ)、耐久性、保全性、収納性、手入れのしやすさ、機能の複合(合わせ技)、…など、具体的な物としての扱いやすさの他、デザイン、色なども重要な要素になる。
例えば、掃除機は吸引力や音の大きさ、排気などが盛んにCMでは比較されるが、使う側の女性からは、置いていても倒れない、部屋において許せる色、デザイン、…などの声もある。立場が変われば視点も変わる。商品開発の最前線で最新技術ばかりを追いかけていては見えないことも多い。
二つ目は、既存にない商品の企画、開発である。物としてこの世に存在していないものを新たに創りだすことは難しいが、ここでも大きく二つのはパターンが存在する。
一つは、日本国内にはないが、海外に存在する、あるいはヒントになるような類似商品があるというケースである。国内で認知されていないだけで便利なモノであれば、大いにチャンスがある。
一方、国内にも海外にも全く何もないゼロの状態から企画し、開発するというケースがある。ある意味、発明品のようなものであるから、珍しいケースともいえるが、蚊を感電させてとる小さなラケットのような器具は上手い具合にニーズに応えた逸品と言えるだろう。
◆商品の企画・開発手順
はじめから「ヒラメキ、思い付きなどアイデア」があって、商品を形作ることはよくあることである。たまたま、偶然など切っ掛けは様々だが、だれでも、いつでもヒラメクわけではないから継続的にやろうとすると難しい。
ある程度仕組みとして、誰がやっても似たようなレベルでできるようにしようとすれば、やる手順、検討する項目などをキチンと決めておく必要がある。
通常、商品を開発するには「機能(はたらき)」を決めることからスタートする。掃除機であれば「ゴミをまとめる」、四角ハンガーならば「洗濯物を干す」というような商品が果たす役割である。目標達成レベルなどの要件、売価などの制約条件も目安としてあった方がよい。次に重要になるのが機能を達成するために「どのような原理」を用いるのか、その原理によって機能を具現化するのに「どのような構造にするのか」が重要になる。
ゴミをまとめるのに空気と一緒に吸い取るのか、静電気によってくっつけてしまうのか、…等々が原理であり、それをどのような構造で達成しようとするのかによって、従来のゴミ袋式やサイクロンなど掃除機としての具体的な構造が決まる。
商品として形作るには、使い勝手(操作性、重量、形状、大きさ)、耐久性、保全性、収納性、手入れのしやすさ、機能の複合(合わせ技)、…など、様々な項目に分ける必要があり、商品としての表かも、またこれらの項目によって行われる。
掃除機のように機械的なものもあれば、アパレルのように機能、性能よりはファッションという感覚的な要素が重要なケースもある。また、ケーキや進物用の和菓子、惣菜などの食品もあるから、プロセスの細かさや要求される精度はマチマチである。ただし、基本的な手順、そこで検討される項目は基本的に同じである。
ただ漠然と個人の技能(普遍化されると技術)として行っている商品の企画、開発も「科学する」ことで普遍化することができ、レベルも安定するし、技術として多くの人に移転することもできる。
技術として100点近いレベルを維持できれば、その上に技能を積み重ねて120点、150点を取る人も現れてくる。安定した強さを持つ組織に共通することである。
単純で簡単なのがいい
なぜか日本では複雑で難しいことが高度で優れており、単純で簡単なのはレベルが低いといった評価が一般に広く定着しているように思う。
東洋経済ONLINEに『仕事ができるアナタが「万年試験バカ」な理由』という記事があったので、少しは似た問題意識を持った人がいたかと思って読んでみたが、全く違っていたのががっかりした。
例えば、高校しか出ていなくても、そして成績があまり良くなくても、とにかく「賢い」「頭がいい」と感嘆を覚える人もいるし、東大で博士号をとっていても、思わず「ウソーッ」と思えてしまう人もいるから、単に学業の成績だけ見たのでは分からないことは多い。
試験の出来不出来だけでいえば、単に価値を見いだせないから集中できないというのが筆者の実感だが、日本の社会では評価されにくい状況にあることは確かである。
例えば、7割と70%と70.0%はどう違うのか、という問題を見て、「いったい何を言っているのか、同じだろう」という人もいれば、「70.0%の方がより正確だから、こちらの方がよい」という人もいるだろう。
どれも同じという乱暴なとらえ方よりは、小数点までとらえた方が、より正確だし、その分だけ優れているという見方の方が、何故か理屈が通っているように思える。
このような思い込みが、多くの偏見を生み、判断を誤らせている。
7割は、1割を単位として物事をとらえており、70%は1%を、70.0%は0.1%を単位として物事をとらえているので、それぞれ物事をとらえる時の細かさが違うというだけでしかない。
どの単位で物事をとらえるべきかは、測定可能な単位や精度、使う時に必要となる精度など、状況によって変わるから、最も適した単位を用いることが望ましい。
分かりやすいのは、地図を作成する際と使う際の精度の違いである。
地図を作成する際に、距離や曲がる角度、方向など、一定以上の精度がないと大変なことになる。1度くらい違ってもいいか、などと思っても10Km、20Km、30Km、…と距離が延びるにつれて、その誤差はどんどん大きくなるから、いい加減なものでは用をなさない。
しかし、使う時には、あまり詳細すぎるとかえって分かりにくくなる。多少デフォルメしてもポイントとなる曲がり角や目標近くの目印が分かった方が見る側には都合がよい。
我々の身近にある物事を見てみると、そんなに厳密な精度を要求するものは見当たらない。
物事の構造、メカニズムに関しても同じである。大手自動車会社の役員をされていた方が、「クルマは、走る、止まる、曲がるだから…」と言われたのがとても印象的であった。物事、本質に近づけば近づくほどシンプルになっていくのだろう。
小売の売場でも、商品をいろいろ分析してみると、いろいろなことが分かってくる。
例えば、昔調べた紳士衣料のサイズ構成を見ると、百貨店S:M:L=1:1:0.5、量販店M:L:2L=1:2:1、専門店M:L:2L=1:2:2、同様にイヤリングとピアスの比率は、百貨店6:4、量販店1:9というように、客層の年齢構成が商品やサイズ構成によく表れている。
難しく考える必要はなく、おおよその目安として、こんなものだということさえ分かっていれば、大きく間違えることはない。
毎日、お客が入れ替わるから売れ方も変動するし、それに伴って在庫も変動するから、全てにおいて厳密にとらえることは不可能だし、過去のデータを厳密にとらえたからと言って、それがそのまま将来に当てはまるとも限らない。
変に物事を難しくするよりは、単純で簡単なモノ・コトとして扱った方が楽でよい。
教育、躾の必要性
いろいろな企業、組織を見ていて感じるのは、企業による組織風土の違い、組織を構成する人達が織りなす特性の違いである。
我々が外部の人間として関与した時、受け入れられやすいのは、フレンドリーで穏やかな組織である。基本的に躾が行き届いており、穏やかで親しみやすい。物事に対する姿勢はポジティブであり、進化することを楽しめるから、変化することに躊躇はない。当然、成果も早く出るから、モチベーションを含めた全ての面で相乗的に改善していく。
一方、どこか緊張感が漂い、外部の人間を警戒してピリピリしている組織は、保守的・排他的であり、変化を嫌う。業務の修正・改善も、自分達が否定されていると感じるのか、感情的になりやすく、攻撃的な態度が目立つ。
「誰々が悪い」、あるいは「○○ができていない」というようなネガティブな発言が多く、批判的で不平不満が多い。多くの人が「自分は悪くない」と思っているから、その分、よそに「悪者」をつくる傾向にある。協調性はなく、それぞれが鎧を着てガードしているからコミュニケーションは図りにくい。インフォーマル組織中心に動くため、公式な決め事も徹底しづらい。異質なものは受け入れず、見えない力によって自然と排除されるから、組織全体がどこかよそよそしい。自浄作用が働かないので、組織は澱み、沈滞化する。
中には、皆が我関せずといった感じで、自分のこと以外、全く関心を示さないケースもある。組織図はあっても、皆バラバラで実質的に組織とは言えない状況にある。
言葉としての意味、解釈は様々あると思うが、一般的な解釈として「躾とは社会・集団の規範、規律、礼儀作法などに合った態度・行動がとれるように訓練すること」という説明が妥当だろう。
人と会ったら挨拶をする、挨拶をする時にはキチンと相手の目を見る、笑顔で挨拶をする、…等々。「決まりだから」「マニュアルにこう書いてあるから」といった表面的、形式的理由によって外部からコントロールされるのとは訳が違う。「責任」「自制」という自らの意識に働きかけることによって、態度、行動レベルは自主的、主体的にコントロールされる。
一般的な知識教育とは本質的に異なる「躾」の持つ意味、重要性である。多少大袈裟かも知れないが、ある意味では経営者の思想、商売に対する哲学、原点といったものを個々人に求めている、と言ってもよいのかもしれない。
物事を発想する上での原点、判断する上での基準が明確になることで、業務上どんなことが起きた場合でも、全てはそこから発想するようになる。
躾が行き届いた上に知識教育がなされるのと、躾をせずにただ知識だけを教育する違いは大きい。単なる知識だけでは分からない、一般常識、規範、道徳、分別、物事の善し悪し、物事の道理などの要素が加わることで、判断の仕方が大きく変わる。
組織を構成する各人がお互いに「リスペクト」し合い、フレンドリーに物事に協力して取り組むことができるか否かは、結果に大きく影響する。
ウィキペディアでは、教育を『教え育てることであり、ある人間を望ましい状態にさせるために、こころとからだの両面に、意図的に働きかけることである。教育を受ける人の知識を増やしたり、技能を身につけさせたり、人間性を養ったりしつつ、その人が持つ能力を引き出そうとすることである。』とし、また訓練は『基本的に、馴れるまで練習させることである。ただの、文字・言葉という形で表現された「知識」を伝えることにとどまる「教授」とは異なり、実際に何かを行わせることで、何かを実際にできるところまで習熟させることである。』としている。
この定義に従えば、実に多くの組織で本当の意味での教育が行われなくなり、機器の操作、手続き、作業などの訓練だけに終始していることになる (例えば、発注機器の操作手順は教えるが、発注の意味、発注数量算出に関連する要素、発注数量の算出方法などは教えないから、発注業務は発注作業だけで終わる) 。
特に、ローコストの名のもとにパート・アルバイト比率を高めた際に、売場業務から多くの要素が排除され、教育は訓練へと大きくシフトした。
しかし、一方では、能力の高いパート社員まで機械的作業に限定してしまい、長い間、本来持てる能力を引き出すことをしなかった。組織だけでなく、個人としても大きな損失である。
本来、ローコスト=ハイパフォーマンス(成果÷投入資源の比が大きい)のはずであるが、なぜか小売業では、長年成果を無視してコストカットだけがローコストとされてきた。結果的に機械的な手続き、作業、機器の操作だけが現場作業として残り、マネジメント要素までも形骸化してしまった。
教育における「こころ」「能力を引き出す」というのは、動機づけ、向上心・目的意識、意欲、自主性・主体性などを重視し、機械的に型にはめるのではなく、個性(得意なこと、長所)を重んじて、潜在能力を開花させるというように解釈できる。
そのように考えると、多くの組織がスタッフの持てる能力の半分も引き出していないように思えてならない。もったいない。