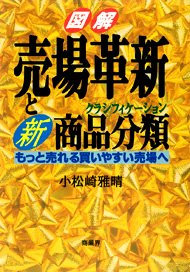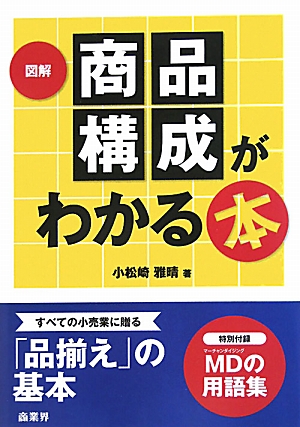観光業界ではsightseeingではなく、sight doingでないと売れない、といわれてから久しい。マズロー(A.H.Maslow)の欲求階層ではないが、アチコチ、ただ見て回るだけではなく、実際に参加、体験、自己実現というようなものでないと満足できなくなっていると考えてよいだろう。
消費の場面でも、ただ物を買って満足する、たくさん所有して満足するという消費の仕方から参加、体験、自己実現という消費の仕方が注目されるようになっている。
すでに数年前から、中元や歳暮のギフトカタログとして、いろいろな教室への参加や体験(物ではなくコト)だけを集めたものが注目を集めている。
また、イトーヨーカドー上尾店では「バーベキューをしたくても、近所のバーベキュー場は予約が取りづらい」というお客の声をもとに、店舗で肉を買ったお客には無料で店舗内のテラスでバーベキューができるようにした結果、4か月で1万人が利用し、肉だけでなく野菜や飲み物などの売上も大きく伸びたという。(NHK News WEB 平成27年5月26日)
また、東京メトロ外苑前駅近くのビルの屋上に「神宮前SORA」というバーベキュースペースがあり、手ぶらで出かけてバーベキューが楽しめるという。(平成27年7月17日日本経済新聞や夕刊)
二子玉川の河原のバーベキュースペースが有料になってからも凄い混みようであることを考えれば、都心に雨、風、紫外線を避けながらバーベキューができる全天候型のスペースがあってもおかしくはないし、会社帰りや学校のサークルなど、皆で調理を分担しながら飲食するという、まるで合宿のような時間が過ごせるスペースがあってもおかしくはない。
物販もただの物売りから、そろそろ脱皮する時期だと思うが、なかなかそのような新しい試み・業態は生まれてこない。
いつも言ってるように、小売業が過当競争と固定費アップでバタバタしている間に、他の業界から参入した企業が美味してところを全て持っていってしまうのではないかと思っているが、どうだろうか….。