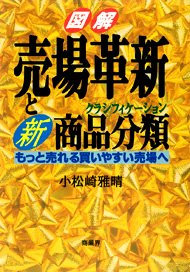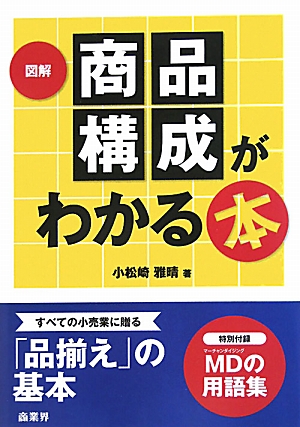2008年に「スモールカンパニーのメリットを活かせ!」の第3部として「現場崩壊」を連載した(HPに原稿を掲載)が、現場だけではなく、その元にある「経営崩壊」とも言うべき状況が目立ち始めている。
原因はいくつか考えられる。
一つは、創業オーナーからの代替わりという難しい状況と急激な高齢化・人口減少、チャネル競合の激化など、環境の劇的変化が同時期に起こっていること。もう一つは、失われた20年、長期に渡るローコスト、生き残りをかけた疲弊戦を続けてきた結果、その状況に慣れてしまった経営者の認識・価値観が、経営幹部を含めたあらゆる階層に対する、本当の意味での教育、人材育成を疎かにしてしまったこと。さらに環境変化は従来の事業の変質=マーケットに対する機能的変化(=具体的にはサービス機能との複合化・IT化・ネットワーク化など)を要求しているにもかかわらず、いつまでも小売業=物売りという形態、既存業態、既存の店舗という概念の中で、従来通り、たくさん物を売ることに固執していること、…などが大きく影響している。
多くの個人・中小零細企業で、店舗(立地・業態)、商品、組織、人、経費構造…など、現状能力では生き延びることが難しくなっている。長年かけて出来上がった問題構造は、すでに近い将来直面するであろう人口減少・高齢化という状況に対処することは難しい。
オーナーの甘さ、優しさ、人のよさというところもあるが、現状がよくないことは認識できても、どう修正すればよいのか、どこへ舵を切ればよいのか、皆目見当もつかないというのでは、「オーナーはいるが経営者は不在」といった状況になってしまう。
小売業は、損益分岐点が高く、経費が固定費的に発生する。売上が伸びている間は多くの利益が出るが、ひとたび売上が低迷すれば、すぐに赤字に転落する。
破綻する企業の多くが、チョッとしたキャッシュフローの不足から崩れ出していることを考えれば、小売業特有の構造に対するリスクヘッジはとても重要である。
固定費、あるいは固定費的に発生する経費を極力小さく抑える必要がある。
経常利益を2倍にするのに、もう1店舗出店していたのは、マーケットが成長し続ける成長期の話である。現在は、すぐ目の前に急激な人口減少と高齢化というリスクを抱えている。
もし1店舗の売上を3~5割上げることができれば、固定費を2倍にしなくても経常利益を2倍にすることは可能である。冷静に状況を判断し、物事の道理に従った経営が必要である。
Archive for wpmaster
オーナーはいるけど経営者がいない 経営崩壊
空家ビジネスをフランチャイズ化したら…
全国に820万個(平成25年)あるという空き家であるが、内訳は賃貸用の住宅430万戸(52.4%)、売却用の住宅31万戸(3.8%)、共同住宅71万戸(8.7%)、二次的住宅41万戸(5.0%)などであり、いわゆる個人所有の一戸建ては181万戸(23.9%)である。
「全国に空家が820万個もあるから大変だ!」と言ってしまうと、確かに5000万世帯しかないのに820万戸(空き家率13.5%)も空き家があるのでは、7~8軒に一軒の割で空き家があることになる。それはそれで問題であることは確かだが、何がどう問題なのかということになると、中身によって随分と状況は変わってくる。
何を問題とするのか、という点が非常に重要であり、最も軒数の多い賃貸用の住宅430万戸(52.4%)を対象として考えるのと個人所有の一戸建て181万戸(23.9%)を対象として考えるのでは、問題の性質も対処方法も大きく変わってくる。
ただ、いずれにせよ言えることは、全国にこれだけの軒数がある空き家について、所在する自治体が、しかも個別に対処するのには限界がある。全国とまでいかなくてもよいが、システム的な対処法を採用しない限り、効率良く、実効の上がる対処は不可能だろう。
Webを使ってデータベース化する動きもあるが、あくまでも情報を整理するという第一段階までであり、そこから先は実態を修正する具体的なシステムが必要になる。
現在、ある地方自治体に「中長期の滞在型セカンドライフ(トライアル)」という形で提案しているが、KitchHike(https://ja.kitchhike.com/ 海外からの旅行者に日本の家庭料理を体験してもらうor日本人に日本在住の外国人宅で家庭料理を体験してもらうマッチング)のような形で、地域の生活、あるいは地域の産業、伝統工芸などを滞在型で経験してもらい、場合によっては移住のトライアルの場としても活用する。その際に空き家を活用するという形である。
いずれにせよ、システムとして空き家活用を考えない限り、まとまった量への対応は難しいし、一つのプロトタイプができあがれば、同様のシステムで別の内容への応用やエリアフランチャイズなどへの展開も可能になる。
量がまとまることで「具体的な対処」の事例が増え、ノウハウが蓄積し、システムの確率もしやすくなる。さらに事業としてのボリュームが大きくなれば資金的な余裕もできるから、地域の雇用、地域の活性化など様々な形で相乗効果が見込める。
実態を動かすには、Webの世界を抜け出さなければならないから、コンビニエンスストアが採用しているようなフランチャイズシステムが有効である。
今後は、飲食や小売だけではなく、農業、水産業、自治体が関与するまち興しビジネスなど、様々な分野でフランチャイズシステムが活用されるべきだろう。
日本で一番大きな市 横浜の人口減少・高齢化と小売店舗のリスク
2025年までの10年間は、マーケットが短期的に大きく変わる重要な時期と考えるべきである。5年後の東京オリンピックを境にして、その前後では多くのモノ・コトの意味が大きく変わる。宴への備えと同時に「宴の後」にどう対処するか・できるかが大きな課題になる。
また、この10年は65歳を超えた団塊の世代が70歳代に入り、75歳以上になっていく時期でもある。これもまた、違った意味で人口ボーナスという「宴の後」が問われることになる。
◆横浜市
2015年4月1日推計の横浜市人口は3,712,170人、世帯数1,638,946、世帯人員2.26人/世帯であり、全国一人口が多い。
人口増減は2011年2,218人(自然増減2,808人、社会増減▲590人)、2012年5,795人(同2,460人、同3,335人)、2013年6,223人(同1,535人、同4,688人)、2014年8,192人(同613人、同7,360人)と年々拡大傾向にあるが、内訳を見こると自然増が減少傾向にあり、社会増のウエイトが高まっている。
①将来の人口推計(日本の地域別将来推計人口平成25年3月推計)
総人口は2010年3,688,773人(100.0)を基準として5年ごとの推移を見ると2015年3,750,938人(101.7)、2020年3,750,511人(101.7)、2025年3,713,787人(100.7)、2030年3,650,671人(99.0)、2035年3,566,897人(96.7)、2040年3,466,837人(94.0)であり、2015年から2020年をピークとして徐々に減少する。
②年齢4区分人口推計(年少、生産年齢、65歳以上、75歳以上(再掲))
2010年から5年ごとに年齢4区分を見ると、年少人口487,302人(100.0)、469,604人(96.4)、438,075人(89.9)、400,935人(82.3)、366,138人(75.1)、347,102人(71.2)、334,733人(68.7)、生産年齢人口2,460,258人(100.0)、2,381,416人(96.8)、2,336,879人(95.0)、2,299,181人(93.5)、2,212,766人(89.9)、2,066,230人(84.0)、1,893,895人(77.0)、65歳以上人口741,214人(100.0)、899,918人(121.4)、975,557人(131.6)、1,013,671人(136.8)、1,071,767人(144.6)、1,153,565人(155.6)、1,238,209人(167.1)、75歳以上人口(再掲)327,737人(100.0)、427555人(130.5)、522,563人(159.4)、619,687人(189.1)、650,430人(198.5)、654,203人(199.6)、686,243人(209.4)であり、年少人口の減少が大きく、それに伴って生産年齢人口の減少幅も大きくなる。
◆世帯数、家族類型別世帯数の推計
平成22年(2010年)国勢調査を基に横浜市が独自に推計した値では世帯数は2025年から2030年にピークを迎え、その後減少する。家族類型別世帯数では、夫婦と子供からなる世帯が大きく減少し(2010年対比2015年▲11千世帯、2020年▲23千世帯、2025年▲37千世帯、2030年▲53千世帯、2035年▲69千世帯)、その他も減少する。大きく増えるのは、夫婦のみの世帯(同+27千世帯、+45千世帯、+58千世帯、+69千世帯、+79千世帯)、単独世帯(同+23千世帯、+44千世帯、+60千世帯、+66千世帯、+63千世帯)であり、男親・女親に限らず片親と子供からなる世帯も増加する。
家族類型は世帯収入、消費支出に大きく関係しており、家族類型別世帯数の構成比変化は、人口の年齢構成とともに消費構造の変化に直結する重要な要素である。
◆小売売上高
第93回横浜市統計書によると、横浜市の平成19年小売業年間商品販売額は371,941,019万円、売場面積2,881,304㎡(同14年361,806,577万円、2,756,641㎡ 「横浜市の商業」 行政運営調整局)、大型小売店130,487,939万円(同14年117,481,673万円、1,186,244㎡、店舗数220 「大型小売店統計調査結果報告」 神奈川県 統計センター)である。⋆平成19年前後に都筑区港北ニュータウン中心に多くのショッピングセンターが開業している。
大型小売店は平成19年店舗数239、売場面積1,312,882㎡から平成25年同258、同1,338,897㎡(対19年比101.98%)と増えていながら年間商品販売額は118,438,415万円(対19年比90.77%)と大きく減少している。(単位面積当り対19年比89.00%)
市の経済計算、市内総生産、民間最終消費支出、家計最終消費支出を見ても平成19年と平成24年で比べると名目、実質とも減少しているから、人口が増えているにもかかわらず、消費支出は全体的に減少傾向にある。
大型小売店を見ると伸びているのは食料品だけである。衣料品、住用品、食堂・喫茶など全般に減少傾向にあり、特に衣料品が3割近い落ち込みとなっている。しかし、多くのショッピングセンターは衣料品中心のテナント構成である。
高齢化によって減少が顕著になる費目が外食や被服及び履物などであること、昼夜間人口比率は西区179.7、中区166.6を除けば90.0以下が18区中11区あることなどを考えると、多くの区で売上が難しくなる可能性が高い。(平成22年10月1日 出典;横浜市政策局統計課)
◆将来のマーケットに影響すると考えられる人口要因
①総人口;総人口は図表1のように2010年を100.0として、2015年~2020年は101.7と微増、その後2025年100.7、2030年99.0、2035年96.7、2040年94.0と減少する。大きく減少が始まるのは2035年以降であるから、年間商品販売額の減少傾向に人口減少の影響が加わるまでには15年ほどの猶予がある。現状で手元にある平成19年(2007年)年間商品販売額37,000億円をベースに人口と年間商品販売額が比例すると考えると、2030年▲370億円、2035年▲1220億円、2040年▲2220億円の減少が考えられる。
②年齢構成;年齢構成の変化には団塊の世代が大きくかかわっている。団塊の世代が65歳以上になった2010年から2015年に65歳以上構成比が3.9%増え、それ以降は2.0%、1.3%と減少して、その後また2.1%、2.9%、3.4%と増えはじめる。75歳以上人口は2010年から2015年2.5%、2020年2.5%、2025年2.8%と増えるが、その後は1.1%、0.5%、1.5%とある程度減少して推移する。生産年齢人口の構成比が大きく下がるのは2030年➡2035年2.7%からである。年少人口は分母が小さいこともあり、2030年まで1%弱とほぼ同じような比率で減少し、その後収束していく。
◆1か月平均の消費支出については、以下のようである。(2014年家計調査)
●過去のデータから、2人以上世帯では、世帯主の年齢が50~59歳、60~69歳、70歳以上と10歳上がるごとに消費支出が約5万円ずつ減少する。また、単独世帯162千円は2人以上世帯291千円より消費支出が約13万円少なく、35~59歳(182千円)から60歳以上(151千円) (65歳以上148千円) になると約3万円減少する。
●全国の大都市(東京都区部含む)52の中では、300千円を超える都市が19あり、横浜市298千円は千葉市299千円に次ぐ21番目に位置する。
●2人以上の世帯のうち勤労者世帯について2004~2014年までの実支出、消費支出の推移を見ると、ほとんどの費目で減少している。特に増加が目立つのは非消費支出であり、光熱・水道、交通・通信など物消費以外だけが増加傾向にある。
③家族類型別世帯数(第3-6表 世帯類型別1世帯当たり1か月間の収入と支出2014年平均 2人以上世帯)では、2人以上の世帯平均291千円、夫婦のみ世帯269千円、夫婦のみ世帯または夫婦と未婚の子供要る世帯294千円、片親と未婚の子からなる世帯209千円、両親と子供夫婦または未婚の孫からなる世帯355千円などであり、前述の単独世帯162千円と合わせて考えると、家族類型別の世帯数構成が変わることで消費全体が大きく変わることが分かる。
1世帯当たり1か月の支出が1万円減少すると、年間12万円、1万世帯で12億円になる。20~30年間の変化ではあるが、1~8万世帯の変化があり、消費支出合計では、月間最大で10万円以上の差があるので、軽く数百億円の変化は想定する必要がある。
1か所に集中して起こることはないとしても、限定された地域での影響は必ずしも軽微なものではないだろう。
家族類型は、世帯人員や有業人員、世帯収入とも関係するため、消費支出の低い世帯数が増えることで、確実に客単価は下がる。高齢化することで交通手段を持たなければ、商圏は狭まり、購買頻度が低下するだけではなく、買上点数=客単価も低下する。
ここでは年齢を考慮していないが、増加する単独世帯では、特に穀類、生鮮食品などへの支出が少なく、調理食品、飲料、種類などのウエイトが高い。また、外食のウエイトが高いなどの傾向も顕著である。
一方、片親と未婚の子からなる世帯、夫婦のみ世帯では世帯人員が少ないこともあるが、食料全般、被服及び履物などの支出額は少なめである。
ただし、一人当たり金額を算出してみると最も世帯支出の高い「両親と子供」、または「未婚の孫からなる世帯」がほとんどの費目で最少であり、逆に「単独世帯」が最大となる。
高齢化すると、また傾向は変わるから、年齢階級別まで落し込んで考慮する必要がある。
また、区ごとの人口減少率や高齢化の度合いの差が大きいので、業態別店舗の状況などと比較して、今後リスクが大きくなる地域を特定することは必要である。
区レベルで見ると、人口減少率が大きいのは、南区、保土ヶ谷区、磯子区、金沢区、港南区、旭区、瀬谷区、栄区の8区、総人口に占める65歳以上人口の割合は南区を除くこれらの区は全般的に高い(泉区が加わる)。実際には町丁目レベルで把握する必要がある。
いろいろな手法、アプローチ
◆分析的アプローチ、設計的アプローチ、創造的アプローチ
①分析的アプローチ
分析的アプローチとは、物事を細かく分析することによって、その詳細の中から問題点を発見し、改善していくというアプローチである。
そもそも分析とは、「ある物事を分解して、それを成立させている成分・要素・側面を明らかにすること」「概念の内容を構成する諸徴表を各個に分けて明らかにすること」「証明すべき命題から、それを成立させる条件へつぎつぎに遡ってゆく証明の仕方」(広辞苑)というものであり、あくまでも細かく分けることである。
したがって、必ずどこかでは、細かく分けたものをもう一度組立て直していく「総合」という作業が必要になる。つまり、分析はあくまでも分析であって、それだけで物事は完結しないと言うことになる。それを忘れると、中途半端で、細かいだけの訳の分からないものが出来上がる。
②設計的アプローチ
分析的アプローチに対して、設計的アプローチというものがある。設計的アプローチでは、理想とする姿を目的的、あるいは、機能的に論理を積重ねることで創り上げていく。
例えば、スーパーマーケットであれば、生鮮食品があり、日配商品、惣菜、菓子、乾物、調味料、一般食品、ソフト・ドリンク、雑貨、という具合に、すでに店舗のイメージは出来上がっている。しかし、既存のスーパーマーケットという概念から離れて目的的に作り上げて行くと、必ずしも現状のスーパーマーケットと同じものができるとは限らない。
例えば現状のスーパーマーケットは必需品・実用品ばかりの品揃えで全く楽しくない。買物をしていてワクワクするような要素が全くない。そこで設計段階で「ワクワクする」「楽しめる」「自分でもできる(doing)」「(料理などが)習える」と言うような要素を加えて設計してみる。
それぞれのキーワードに対して具体的な商品、売り方、販促、什器、レイアウト、イベント、サービスなどをリストアップし、全体を組立ててみる。
東急ハンズの食品版のような店ができるかもしれないし、エンターテイメント+食品・食材+レストラン+インターネット+文化センターのような全く今までの概念とは異なる新しい店舗ができるかもしれない。
分析的アプローチは、細かく分けていった中からおかしな点を見つけて改善するため、部分的な改善が中心であり、本質的な点までは変えにくい。
それに対し、設計的アプローチは、今までの方法にこだわることなく、あくまでも抽象化して目的的に達成手段を組立てていくので、本質的な改善が可能なアプローチと言うことができる。
理想とする姿を明確にした上で現状とのギャップを明らかにし、そのギャップを埋めること=解消することで現状を飛躍的に改善していくのが設計的アプローチである。
③創造的アプローチ
分析的アプローチ、設計的アプローチに加えて創造的アプローチというものがある。
設計的アプローチが目的的、論理的であるのに対して、理想とする姿をアイデアで創り上げていこうというのが創造的アプローチである。あくまでもアイデアが中心であるので良いものができる時は、とてもすばらしいものができるが、アイデアの実現性や、改善案としての効果という点から考えると必ずしも確率が高い方法とは言えない。
このような3つのアプローチがあるわけだが、よくよく考えてみると、この3つのアプローチは、互いに相反するものではなく、一連の流れの中で相互に関連しながら使っていくと便利であることが分かる。
例えば、全体のフレームは、設計的アプローチであっても、現状を把握する時には、分析的アプローチを用いる。理想とする姿を描く時に、基本的には、設計的アプローチでいくが、理想とする姿のヒントは、創造的アプローチを用いてヒントを出す。あるいは、理想と現状とのギャップを解消するためのアイデアは創造的アプローチを用いるが具体的な改善案にまとめあげるのには設計的アプローチと分析的アプローチを合わせて用いる、という具合である。
それぞれの特徴をよく知り、目的や状況に応じてそれらを上手く使いこなすことが重要である。
帰納法と演繹法
帰納法と演繹法という2つのアプローチがある。帰納法が様々な事象を通して一般法則を導くのに対し、演繹法は一般法則を用いて個別の事象を展開しようとするアプローチである。
分析をベースにした改善活動では帰納法的アプローチが主体になり、ある程度改善事例が蓄積し、改善法則が理解できてくると演繹的アプローチをミックスして使うようになる。
それに対し、現在のサービス科学のように全く新しい発想から、これまでにないモノを創り出そうとする場合には、どうしても演繹法的アプローチが主体になる。
いずれにせよ、物事の歴史を考えれば、基本的には帰納-演繹という手順で物事が進化しており、様々な事象と一般法則の関係を理解するにもこのような順序が分かりやすい。
以前、ある食品の製造販売企業で現場改善に取り組もうとした時、どうしても本から入りたがる人がいた。優等生がよく言う「よくわからないから勉強してから…」「よく調べてから…」「皆の意見を聞いてから…」「皆で検討してから…」ということが身体に染みついているのだろうが、そのようなケースでは、まず実現しないケースの方が多い。
理屈としては分からないでもないが、目の前に「現場」という何物にも代えがたい、素晴らしい「題材」があるのに、それを避けて本やセミナーなどの知識に頼ろうとしていたのでは、いつまで経っても主体的に実態を変えることは難しい。
しかも、現場で起こっていることの多くは、特別な知識を必要とせず、常識的に判断していけば、ほとんどのことが解決できる。重要なことは「物事の道理」に従えば、ほとんどの問題が解決できるということを「経験的に分かっていること」「身体で知っていること」である。
人間には知恵があるし、現場には知恵がある。本に書いてあるような特別なことが無くても、その知恵を活用すれば、多くの物事は改善される。本には書いていないようなことも現場ではたくさん起こっているし、本を書いた人も知らないようなことが現場では数多く起こっている。
総てのヒントは現場=事実にあるから、五感を研ぎ澄まして現場=事実に学ぶべきだろう。演繹的アプローチよりは帰納法的アプローチで、現実から一般法則を導くというプロセスを体験すべきである。一度体験し、身につければ、一生の財産になる。
47都道府県を含む全国1858の自治体の人口減少と高齢化の状況
国立社会保障・人口問題研究所が発表した「日本の地域別将来推計人口」で取り上げた47都道府県、および市区町村(福島県は県のみ、市区町村はナシ)を合わせた1858の自治体について、2010年を100とした時の総人口指数(横軸)、および老年(65歳以上)人口指数(縦軸)を用いて2025年、2040年の散布図を作成してみた。全体としては、2025年、2040年とも総人口指数が高くなるほど老年人口指数も高くなる(グラフは右肩上がりの正比例の形)。また、人口減少に伴い、2040年には2025年と比べて総人口指数が100を割り込む自治体数が大きく増加し、全体も右上から左下へと大きくシフトする。
2025年、最も多いのが、総人口指数80―90/老年人口指数100―120、および総人口指数90―100/老年人口指数120―150という自治体であり、その次に総人口指数70―80/老年人口指数100―120、総人口指数70―80/老年人口指数90―100、総人口指数100―120/老年人口指数120―150、総人口指数90―100/老年人口指数100―120が続く。
2040年になると自治体数が集中するマスが、総人口指数が同じでも老年人口指数がワンランク上へとシフトする。最も自治体数の多いのが、総人口指数80―90/老年人口指数120―150、総人口指数70―80/老年人口指数100―120であるが、1マスの中に位置する自治体数は2025年に比べ半分くらいに減少する。自治体固有の状況により、人口構成が分散していると考えられる。
2040年までしか推計値がないため、2050年、2060年と時間が進んだ時にどのような状況になるのか、現時点では想像の域を出ないが、可能性として考えられるのは、①左下に位置する自治体のように日本全体が高齢者の減少とともに総人口も減少し、やがて人口を維持することができなくなって消滅する、②ある時点で年齢構成、人口規模とも一定範囲内に収束してバランスし、その状態が維持される、などが考えられる。
◆左下に位置し、人口が大きく減少する自治体は、年少人口、生産年齢人口に加えて老年人口までも減少することで相乗的に人口減少が加速する。
2025年と2040年のそれぞれについて、総人口指数の減少幅が大きい上位100の自治体を抜き出し、その中から①2025年の総人口指数がほぼ同じでありながら老年人口指数が異なる自治体、②老年人口指数がほぼ同じでありながら総人口指数の異なる自治体、をいくつか抜出し、比較をしてみた。
①2025年の総人口指数がほぼ同じでありながら老年人口指数が異なる自治体
宮崎県西米良村(2010年人口1241人、2025年総人口指数73.4、老年人口指数78.8)、愛媛県愛南町(同24061人、73.1、107.4)、北海道音威子府村(同995人、73.1、124.4)である。
サンプル数、人口の大小、自治体の立地環境、産業、周辺都市との関係など様々な要素があるので一概に人口動態データの比較でどうこう言うことは難しいが、ここで取り上げた3町村に関しては、総人口指数と老年人口指数の比率が西米良村73.4:78.8➡53.8:54.2、愛南町73.1:107.4➡49.6: 81.2、音威子府村73.1:124.4➡49.5: 86.6というように、2025年、2040年ともほぼ同じ比率になっていた。
大きく変わるのは総人口に占める年少人口、生産年齢人口、老年人口の割合であり、音威子府村だけが、総人口が30年間でほぼ半分になっているにもかかわらず、年齢3区分の比率はほぼ同じで推移している。他の2自治体は年少人口比率が減り、生産年齢人口比率も大きく減少して、その分、老年人口の比率が高まるという変化をしている。
②2025年の老年人口指数がほぼ同じでありながら総人口指数の異なる自治体
和歌山県北山村(2010年人口486人、2025年総人口指数72.6、老年人口指数66.9)、高知県大豊町(同4719人、60.4、69.1)の比較では、特に目立った傾向は見られなかったが、北山村が①の音威子府村と同様に年齢3区分の総人口に占める割合がほとんどなかった。
この2自治体に共通しているのは、非常に人口が少ないということであり、年少人口比率がほぼ30年間一定ということが年齢3区分の比率を安定させていると考えられる。 (音威子府村11%前後、北山村6~7%であるから年少人口比率の高低に関係なく、一定であることが重要と思われる)
◆左下に位置する自治体の変化(総人口指数、老年人口指数とも100でグラフを上下左右に分けた)
左下に位置する自治体は、年少人口・生産年齢人口が減少して老年人口が増える、あるいは、年齢3区分の人口比率が30年間ほぼ変わることなく一定という大きく分けて2つのケースが考えられるが、いずれのケースも人口は確実に減少し、2025年の時点で2010年比70%を切る自治体が58、80%未満では448にのぼる。
皮肉なことに人口減少幅の大きい自治体ほど老年人口の増加が少ないから、人口の少ない自治体ほど年齢構成のバランスが維持された状態で人口だけが減少していくことになる。
過疎化する地域で小売業と言えば、コンビニエンスストア、ボランタリーチェーン加盟の地元資本の店舗、生協、Aコープ、道の駅などが中心であり、大きく資本が投下されていない。また、ライフラインとして行政、地元住民、NPOなどが維持することに協力して取り組むため、何らかの形で維持されると考えてよいだろう。
問題があるとすれば、一定規模以上の人口を抱え、近隣自治体を含めて複数の中大型店舗が存在する自治体ということになるだろう。
◆左下から中間に位置する自治体
左下から中間に位置する自治体の状況を整理するため、2010年人口が3万人、5万人、7万人、10万人、15万人、20万人、25万人、30万人規模の自治体の中から2040年の総人口指数(2010年=100)が100超(人口が増える)と60~70の自治体をランダムに選んで比較してみた。
選んだのは◇3万人 愛知県幸田町2010年37930人、2040年総人口指数110.5、岡山県備前市37839人、60.4、◇5万人 沖縄県豊見城市57261人、123.7、富山県南砺市54724人、63.7、◇7万人 滋賀県守山市76560人、112.8、大分県佐伯市76951人、64.9、◇10万人 沖縄県浦添市110351人、105.2、大阪市北区110392人、110.4、岩手県花巻市101438人、70.6、◇15万人 川崎市幸区154212人、106.3、川崎市麻生区169926人、107.5、栃木県足利市154530人、70.3、◇20万人 東京都港区205131人、105.2、福岡市博多区212527人、108.9、静岡県沼津市202304人、71.7、◇25万人 東京都墨田区247606人、100.6、長崎県佐世保市261101人、74.3、北海道函館市279127人、62.6、◇30万人 横浜市港北区329471人、104.7、秋田県秋田市323600人、72.8 である。
これら20都市について見ていくと、2040年の総人口指数が100を超えている自治体は人口規模に関係なく、ほぼ全て2040年老年人口指数が200前後であり、総人口指数が60~70にある自治体は老年人口指数が80~100という結果になった。
ただし、総人口に占める老年人口の割合は後者が2040年38~43%であるのに対し、前者は27~30%、後者の2010年前後の割合とほぼ同じ割合になっていた。
老年人口比率で見ると、ほぼ20~30年、あるいはそれ以上の違いがあることになる。
2040年の総人口が増える自治体は、年少人口の割合が高い、あるいは年少人口の割合が高くない場合は生産年齢人口の割合が、総人口が減少する自治体よりも10%くらい高い。
◆各自治体の状況から分かる状況
まず、人口減少、高齢者の増減については、自治体の人口規模とは関係ないことが分かったことは、いろいろな意味で大きい。
これまで政府は、地方における人口流出のダムとする中核都市を人口規模によって設定しようとしてきた。小売業が店舗を配置する際にも人口規模は重要な要素であった。しかし、どうやら「現在の人口規模だけで将来の自治体の姿をイメージすることはできない」ということが、これらの分析からは言えるようである。
ABC分析 特性を理解し、正しく使おう
◆パレート図 イタリアの経済学者パレート(Vilfredo Federico Damaso Pareto 1848-1923)が富の分布を知るため、富の多い順に並べて累計線とともにグラフ化したのパレート図である。富の分布が平等であれば、累計線は人数に比例して増える直線になるが、実際の累計線ははじめ急に増え、その後増え方が緩やかになる曲線を描く。この直線と曲線の差が富の偏りであると説明した。
◆ABC分析 パレート図を使って、「量」という特性によってグルーピング(層別)し、管理しやすくするために用いられるようになった手法がABC分析である。ABC分析という名は、メーカーが種類の多い部品の在庫管理を効率的に行うため、使用量によってA(0~80%)、B(80~95%)、C(95%~)とグループ分けしたことによるものである(ABC分析例)。使用量の多いAグループは発注頻度・発注量とも多くし、倉庫では出し入れしやすい入口付近、使用量が中くらいのBグループは発注頻度・発注量とも中くらいにし、倉庫の中間、使用量が少ないCグループは発注に手間をかけないように発注量を増やして発注頻度を減らし、倉庫の一番奥に配置するようにした。
小売業では20%のアイテムで80%の売上をつくる20:80の法則として説明されていたが、現在はアイテム数が多いこともあって、20%のアイテムで40~50%の売上というようにそこまで集中していない。
小売業では、POSデータによってアイテムをカットするために使う手法として定着しているが、本来は「量」という特性に注目して、数多くある対象を「層別(特性によりタイプごとに分ける)」し、管理しやすくするため(タイプに適した管理手法を当てはめる)の手法であることを理解して使うべきである。
特にPOSデータは販売データしかわからないため、フェイス数が1:100、在庫数も5:500という状況で、販売数量が5:10なら10の方が大きいという判断しかできない。商品回転率(数量と金額では商品回転率が違う)、スペース効率、荒利貢献(相乗積)など、特に効率を見る評価軸が漏れることが多いので、判断を間違うことがある(or多い)。
また、用途機能があまり一般的でなく、もともと販売数量が少ない商品(品揃えとして扱うことは有効)と類似する売れ筋アイテムに売上が集中するために販売数量が少ない商品(類似商品であるからほとんど意味がない)という2つの意味が異なる商品についても、単に販売数量だけを比べていたのでは明確に識別することができない。前者は品揃えの幅を広げるので取り扱う意味はあるが、後者は単に類似アイテムが多いというだけでしかない。
単純に数量の大小だけで比較することは危険である。本来的な意味、数量の単純比較以外の評価の仕方など、様々な視点を理解した上でABC分析を使うべきである。
ノコギリがクギを打つのに向いていないように、手法にも目的、向き不向き、できることの限界がある。
もし、株式会社いろどりがフランチャイズ化を推進したら
「株式会社いろどり」というと分かりにくいかもしれないが、おばあちゃん達が葉っぱビジネスで年収何百万も稼いでいるという話はテレビや雑誌、Webニュースなど、どこかで聞いたことがあるだろう。
農水省なども成功事例として盛んに露出させているが、よくよくその成功までの道程を見てみると、成功事例ではあるが、だからと言って簡単にどこの自治体でもできるというレベルの内容ではない。
「株式会社いろどり」の成功には、実に様々な条件が揃っている。まず、マスコミがとり上げるのは「おばあちゃん」「葉っぱ」「高収入」というニュースとしての価値を高め、見る人の興味を引く意外な組み合わせであるが、よくよく事例としての記録を見てみると、何十年か前に多くの企業が取り組んで成果を上げていたQCサークルと変わらない内容の説明がなされている。それを指導した人と指導に応えて実現した多くの人がいたことが成功の重要な要因であり、他所からチョッと見学に来て見聞きしただけでは、どうこうできるレベルでないことはすぐ分かる。
もう一つは、規模である。「株式会社いろどり」の事業規模で十分潤うだけの地域であるから、このビジネスが生きている。仮に「株式会社いろどり」の数十倍の収益でなければ支えられないような規模の自治体であったら….と考えると、ビジネスそのものの本質から変えていかないと難しいということになる。
現在は海外にも販路を広げようとアプローチしているということであるが、「株式会社いろどり」を成功事例としてどんなにアピールしても第2、第3の「株式会社いろどり」が現れることは難しいだろう。
まず、そのレベルと成功までのプロセスの大変さを知っただけで引いてしまう自治体がほとんどのはずである。「本当にそんなことが自分たちにもできるのだろうか?」という気持ちが先に出てしまう。
そうであれば、お金をかけてPR資料を印刷するよりも、その資金をフランチャイズ化とマーケット開発のために使った方がはるかに有効だろう。
マーケットが広がれば、生産量を増やすことが必要になる。自社のノウハウをフランチャイズという形で他の地域に移植し、すべてを自社ブランドでまとめて販売するような形をとれば、「株式会社いろどり」の培ってきた知識・経験・技術・ノウハウを何倍にも拡大することができ、それによって潤うことができる自治体も増えることになる。
最も重要なのが「コア技術」であることは確かだが、それを安定化させ、短期間のうちに拡大するためのマネジメントとシステムも同じくらい重要な意味を持つ。
典型的なのがコンビニエンスストアだろう。コーヒー、ドーナッツ、…等々、話題に事欠かないが、もし1店舗しかない店舗の話であれば、社会的にも経済的にも影響力はないから、話だけで終わっている。重要なのはフランチャイズというシステムによって規模を確保したことである。
そう考えると、葉っぱも黒マグロもウナギやウナギ味のナマズも、規模が小さいうちは話題にはなっても影響力は小さい。
重要なことは、いかに短期間で「コア技術」を拡大し、事業ベースに乗せるのかである。
地方創生、農業再生、日本再生、….いろいろと言われているが、IoTやサービス生産性革命など、いろいろなモノ・コトが短期間のうちに結びついて事業として効果を上げるには、先駆した企業のコア技術を安定したレベルで拡散することができるフランチャイズシステムが必ず必要になる。
現状を見る限りでは、最も進んでいるのがセブン-イレブン・ジャパンであると考えられるから、現業のコンビニエンスストアというビジネスモデルの中からチェーンシステム、フランチャイズシステムという枠組みだけを独立させ、様々な対象をその枠組みに当てはめることができれば、日本の農業も水産業も大きく変わるだろう。廃校や空き家問題も発生案件ごとに各自治体が対処するようなことなく、全国ネットで処理できるように変わるはずである。
製造業を中心にモノ•コトを効率的に行う方法、品質、出来栄えを安定させ水平展開しやすくする標準化などの手法は歴史的にも優れている。これらの経験、スキルを活用すれば様々なケースでフランチャイズシステムなどを応用することも可能になる。経験、スキルを持つ団塊の世代を中心とした人材を遊ばせておかずに活用するべきである。
誰がはじめに「王様は裸だ」と言うか
「ティム・ガンのファッションチェック(Tim Gunn`s Guide to style)」というアメリカのテレビ番組がある。以前、NHK教育テレビ(Eテレ)でも放送していたし、BS258 Dlife、CATV(FOX TV)などでも見ることができたから知っている人も多いと思う。
ティム・ガンは、アメリカの著名なファッションコンサルタントであり、毎回、体型コンプレックスや服のセンスに悩む一般女性を洗練されたレディに変身させる。
番組では、3Dスキャンを用いて全身を等身大のCG画像に再現し、体型の特徴を客観的に把握することからスタートする。思い込みや先入観を排除し、改めて自分の体型に合うファッション・ルール、自分という人間を表現するのに適した服装のパターンを確認していく。
ティム・ガンは一方的に意見を押し付け、着せ替え人形にするようなことはしない。ファッション中心に物事の見方・感じ方、アイデンティティ、コーディネイトなど、さまざまな視点から質問し、疑問を投げかけ、時に意見を交わすことで、自らゴールにたどり着けるように導いていく。
一人の女性がファッションに開眼し、変身していくプロセス、その進め方は、筆者が学生に教えている「クエスチョニング(questioning)」とよく似ている。はじめから答えを与える(クエスチョニングに対してアンサリングanswering)ことはせず、自らが答えを導けるように物事の認識の仕方、論理の組み立て方、結論の導き方などを一つ一つ積み重ねていく。
「ファッション」を単なる流行の服、高価な服という物の次元で終わらせることなく、一個人のアイデンティティ、人間そのものという次元でとらえている点は大いに共感できる。
コンプレックスを持つ普通の女性が、自分に合ったスタイルを自ら発見し、自立していくプロセス、自信溢れる一人のレディに変身していく様子は、視聴者に大きな感銘と共感を与える。アメリカの視聴者参加番組に共通する重要な要素である。
アメリカで人気の高い視聴者参加番組には、American IdolやX Factor(米国版)など数々のオーディション番組がある。見ていて日本とつくづく違うと感じるのは、とにかく参加者の個性を大切にする点である。ユニークな個性、持ち味を引き出し、持てる才能を大きく開花させた者が最後に勝ち残る。
審査員の講評、アドバイスは温かく、毎回「すばらしい!」「番組の歴史の中で最高のパフォーマンスだ」「あなたが誇らしい」「あなたこそ優勝するのにふさわしい」「あなたこそ真のアーチストだ」…等々、自信を持たせ、成長を促す言葉が数多く並ぶ。中には厳しい批評もあるが、すぐに観客からのブーイングにかき消されてしまう。
自分が応援するお気に入りに送られる審査員の褒め言葉は観客、視聴者を熱狂させる。参加者のパフォーマンス同様、番組を盛り上げる重要な要素である。
何回かに渡る決勝ラウンドの間に歌、ダンス、衣装、メイクなど、さまざまなプロの指導が入り、参加者は予選の時とは見まがうばかりに成長する。
小さな田舎町から出てきた高校生、歌手になる夢を捨てきれずに細々と歌を続けてきた人が、幾多の試練を乗り越え、最後にはアメリカン・ドリームを手にする。
優勝者は視聴者の投票によって決まるため、まさにアメリカン・ドリームが実現するプロセス、その瞬間を視聴者も当事者の一人として一緒に体験する。
番組によってアメリカン・ドリームを手に入れて歌手デビューする人は多い。さらに家族、親戚、友人、近隣住人、同じ学校・職場の仲間、同じ町の住人、投票したファン、….、直接、間接にアメリカン・ドリームを間近に知る人は増え続ける。
番組全てが常にポジティブであり、夢がある。American Idolのファイナルでは、数千万の投票があるというから全米が熱狂するのも理解できる。実に大がかりな仕掛けである。
◆新たなマーケットに対応するための発想転換、構造転換
ティム・ガンはファッションを単なるモノ(商品)にはしないし、オーディション番組はただ歌が上手いだけでは残れない。その人そのもの=アイデンティティが重視される。
ここに、これからの時代のビジネスに対するヒントがあると考えている。
さまざまな媒体には「拡大するシニアマーケット」「シニアマーケット100兆円」「団塊&シニアマーケット研究」など数々の見出しが並ぶ。
すでに2030年には50歳以上が全人口の50%を超え、平均年齢も51歳台になると推計さるから、改めて「シニア」と言わなくても、それが日本人の平均像になる。
対象となる消費者、さまざまな媒体で論じる人、それを読む人、ビジネスの中心にいる人、…、みな同じようにシニアと呼ばれる年齢層の人ばかりになる。しかも、多くの調査研究からは、シニアと言われても自分のこととは思わない、年齢と全くかけ離れた意識をもつシニア像が浮かび上がっている。
ある意味、特別なことと考えずに自分達の感覚をそのまま生かせばよいような状況にあると言ってもよいのだろう。
すでに旅行業界ではsightseeingではなく、sight doingと言われて久しい。
A.H.マズローの欲求の階層では、人間はひとたび生理的欲求(食欲、睡眠、性欲など)、安全性欲求(住居、衣服、貯金など)など初期の欲求が満たされ、高レベルの欲求に移行すると、いくら低レベルの欲求を満たしても動機づけにはならないという。
モノが溢れる日本、その中でもブランドブーム、バブル、価格破壊など、さまざまな消費の形を経験してきた人達は、すでに生理的欲求、安全性欲求から社会的欲求(友情、協同、人間関係など)、自我欲求(他人からの尊敬、昇進など)、自己実現欲求(潜在能力の最大限の発揮)へ移行していると考えるべきだろう。
マーケットのニーズは、単なる「モノの充足」ではなく、「状況の充足・改善(参加、経験、スキルアップ、自己実現など)」という新たなソリューションテーマに移っている。
ティム・ガンのファッションチェックやAmerican Idol、X Factorのように、個々の潜在能力を開花させ、個人が進化するようなポジティブなビジネスが重要になる。
2012年10月1日、日経新聞に「三菱総合研究所が65歳以上を対象に1カ月の被服費として使ってもよい金額を聞いたところ、実際に使っている6千円~7千円程度の倍近い金額を答えた」という記事が掲載された。
筆者が提唱する「着やすい服」とどこか通じるものがあるが、基本的にデザインやサイズ(体型)が合わないというだけではなく、商業ビル、ショッピングセンターを見れば分かるようにシニアが買えるチャネル=店舗はない。
20年以上前に婦人物で実験したことがあるが、マインド35歳の商品構成でも十分70歳まで対応できる。当時30歳台半ばのバイヤーがマインド20歳のカジシャツを着ていたことを考えても、デザインやアイテムを年齢と無理矢理こじつけるのは無理があると言ってよいだろう。問題があるとすれば、ショップの形態=チャネルとサイズ(体型、型紙)である。
「 売りたいのに売れない」「買いたくても買えない」という供給側と買う側のミスマッチを誰も指摘せず、長年放置してきたというのが実情だろう。
「王様は裸だ!」と誰かが声高に叫び続けない限り、マーケットのニーズに応えるような構造転換は起こらない。長い間に染み付いた思考から抜け出すことができなければ新たなマーケットの創出も難しい。
筆者自身の経験として、日本の場合、標準体形から外れてしまえば、オシャレをしたくても実際には難しい。ファッション、オシャレなどという以前に、着られる服(身体が入る服)を確保することができなくなる。電車の中、街中だけでなく、テレビに出ているアナウンサーでさえ、サイズの合わない服を着ているケースは多い。
モノは溢れていても知識や着こなしといったソフト、ノウハウ面では後退し、そのことがさらにモノづくりや販売体制の後退にも影響していると思える。
実際に、さまざまな体型の人と一緒にショップを回り、気に入った服、実際に着られる服(体型的に身体が無理なく入り、フィットする)というキーワードで商品を探してみれば分かるが、標準体型を外れる人が着られる服も、それを売る店もほとんどないだろう。筆者が「着やすい服」というキーワードを提唱した時、周囲の人達(アパレル業界とは関係のない一般消費者)から数多くの賛同が得られたのも、そのような実情に対する消費者の不満、疑問と考えている。
「なぜ、こんなに店がたくさんあり、モノも溢れているのに、気に入った服で自分に合う服がないのだろう。」そう思っても、それを声高に叫ぶ一般消費者はいないし、マダムトモコのように「無ければ自分でつくればよい」と行動に移す人もいない。
その結果が三菱総合研究所の調査結果ということだろう。
多 くの人は諦め、ダイエットに励んでいるのかもしれない。事実、筆者は15kg減量して標準体型になってからは若い時と同じような服装に戻すことができている。
ブカブカで大きすぎる、窮屈で着てはいるが動けないというのでは、いつしか、オシャレすることを諦め、放棄する人が出ても不思議ではない。
新しいマーケットは、消費者の不満から生まれる。もともと立位で型紙を作っていれば動きに対する想定はないから満員電車で吊革につかまれば、スーツも、コートも窮屈である。消費者から不満の声が上がらないのは、長い間そういうものだと諦めているからであり、いろいろと話していく中からは通勤、通学、仕事など、さまざまな場面における不満や要望を知ることができる。
すでにファッションという分野も、ただモノとしての商品を大量生産、大量販売する時代から、一人一人のアイデンティティとしてのファッションをコーディネイトする時代(服装を組み合わせるのではなく、企画・場の提供などにより、ライフスタイルを創りあげる、あるいは具現化する)に入ったと言ってもよいだろう。
ファッションがTPO(time、place、occasion)というのであれば、新たに着て行く場所、用件を企画、創出すれば、新たなニーズ、新たなマーケットの創出につながる。
子供の入学式、友達の結婚式という非日常ではなく、アメリカで日曜日に着飾って協会に行くのと同様に、子育てを卒業した人達が、日常的にオシャレをして出かけられる場所、用件を企画、創出することが新たなマーケットの創出につながるはずである。
それを実現するには、現場を運営する人達の発想と具体的に対応できる事業構造の大幅な転換が必要になる。
いま必要なことは、「これまでの常識」の陰に隠れて見えなかった多くの「ミスマッチ」を一つずつ洗い出すことであり、いろいろな分野から「王様は裸だ!」という声が上がることだろう。
もし、近大、岡山理大とセブンイレブンがコラボして養殖ビジネスを始めたら…
テレビなどでも取り上げられることが多いのが、近畿大学におけるクロマグロの完全養殖である。最近、ウナギ味のナマズが注目されているが、幅広い研究がなされている。
一方、「魚の養殖は海」という常識を覆し、「好適環境水」という特許技術を用いて陸上で魚の養殖を実現したのが岡山理科大学である。淡水魚と海水魚の同一水槽での飼育を可能にし、陸上で多くの魚種の養殖も実現したことで、今度はクロマグロの養殖も手掛けるという。どちらも長年の研究から数多くの実績を持つ大学である。
この2校の持つ技術・ノウハウをコア技術として「海でとる漁業から陸で育てる漁業」を膨大な数の廃校施設を活用し、それに現在あるさまざまなシステム、ITなどを組み合わせることができれば、壮大なビジネスを生み出すことが可能になると考えている。
養殖だけでも十分地域産業として新たな雇用を生み出すことができるし、さらに水族館や釣り堀などレジャー・観光、輸出産業としての可能性もある。
問題は事業としての構成、運用方法である。従来のように単独組織を中心とした運用ではどうしても限界がある。ポテンシャルから考えても、全国をネットワークで結んだフランチャイズシステムのような経営形態を想定するべきだろう。
筆者は以前からコンビニエンスストア企業(セブン-イレブン・ジャパンしかない)を母体とした農業や漁業(養殖、加工など)のフランチャイズチェーン化を提唱しているが、マーケティング力、商品開発力、情報システム、数多くの店舗をマネジメントする業務システムなど、その技術・ノウハウ、システムは多くの可能性を秘めている。
ビジネスとして、より付加価値を高めるには、稚魚や成魚の販売という素材・原材料の販売だけではなく、料理の提供、水族館・釣堀など養殖の周辺にある観光・リゾートとしての可能性までを取り込み、6次産業的なトータルな事業に仕立てることが重要だろう。
必要なのは、事業企画、事業の推進母体、マーケティング、販売、資金、情報システム、IT、エネルギー、サプライチェーンなどを兼ね備えたインキュベーターのような組織である。
必ずしも大きな規模である必要はないが、技術、ノウハウ、経験などを持つプロフェッショナルな個人・組織が集まる必要がある。
現状であれば、まだ団塊の世代という多くの技術、経験を持つ人達を確保することも可能である。彼らを高齢化の象徴とするのではなく、高度成長期を支えたプロフェッショナルとしてもう一度活かすことができれば、実現性は大いに高まる。
すでに近畿大学、岡山理科大学の事業は、歴史、研究開発、事業化のレベルが高く、現状でも十分事業として成果を上げ、成長、発展もしている。ここで、あえて、この2校を廃校施設の有効活用と絡めて取り上げたのは、コア技術としてのポテンシャルが非常に高いからであり、現在、日本が持つさまざまな分野の技術やシステムを加えればさらに大きく社会貢献が可能と考えたからである。
◆前提条件として設定すべきポイント
①まず、コストという点に関して、陸上で魚を養殖する場所は、廃校施設を中心に地方にある遊休施設を活用する。もう一つ重要なことは水がよいこと、水温を一定に保つために太陽光発電など自家発電がしやすいこと、もしくは温泉、工場、ゴミ処理場などが近くにあり、熱利用が可能なこと、そして何といってもコストの多くを占める飼料問題を解決できる技術を持つ企業・組織・団体などが参加すること、最後に物流面を考えて消費地、高速インター、港など物流基地に近いこと、…などがあげられる。
②運用組織は、全体を戦略的な視点から統括する事業企画部門、コア技術を提供する研究開発部門(養殖、品種改良技術など)、周辺技術の研究開発部門(水質維持管理、省エネなど)、養殖を担当する生産部門、水・エネルギーなどを担当する環境部門、飼料を確保する前段階のサプライチェーン部門、ルート営業・販売(輸出を含む)を担当する後段階のサプライチェーン部門、小売・レストラン部門、水族館・釣堀・体験学習などを含めた観光部門、フランチャイズチェーンシステム(スーパーバイザーなど運用。マネジメント)部門、IT部門、業務・情報システム部門、….など、現在それぞれの業種業界で用いられている有効な技術、システムなどを集結させ、技術、ノウハウ、経験等の融合を図る。
◆具体的な事業イメージ
コア技術のポテンシャルを十分活かすために必要な要素が二つある。一つは事業資金を確保する収益力、もう一つが分散する拠点を統括してマネジメントするチェーンシステムの精度である。
①収益力; 輸出を含め、戦略的にどのような魚種にウエイトを置いて生産し、どのようなチャネルにどのくらいの量を流通させるのかをコントロールすることで収益力を高める。周辺の事業開発も必要である。
②チェーンシステム;事業規模が大きくなることで養魚施設は分散し、店舗も多店舗化すれば、従来の延長線上で一元管理することは難しくなる。チェーンストアがそうであるように、設計段階から多ヶ所を想定し、チェーンシステムとして運用、マネジメントする仕組を持つことが有効である。
具体的には、●本部を中心として技術、ノウハウを提供するフランチャイズシステム(スタート当初は直営中心)として、各地に魚種を振り分けて養殖させる ●本部は、研究開発、ルート営業・販売、小売・食事提供、観光などの企画開発・事業化を行い、地域ごとのフランチャイジー(事業会社)がその運営に当たる といったイメージである。
陸上での海水魚養殖というポテンシャルの高いコア技術、地方で増え続け、有効活用が難しい廃校….、現状ではなかなか結びつくことはない2つの要素であるが、上手く結びつけることができれば、大きな可能性を感じさせるビジネスとなり得るだろう。
このような組合せによるビッグチャンスはまだ他にも数多く眠っている。