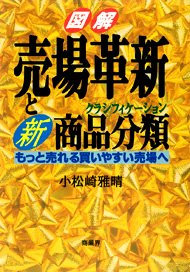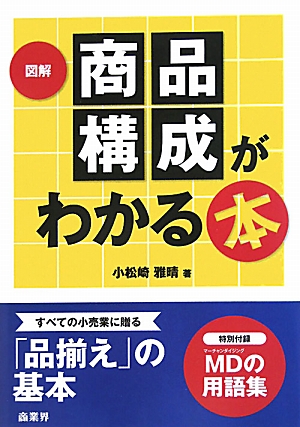11月17日、「インダストリー4.0時代 流通業の経営革命」(東洋経済新報社)のセミナーを受講することができた。 普段とは逆の立場で専門分野以外のセミナーを聞くことはいろいろと勉強になるし、自分の立ち位置を確認するのにもおおいに役に立つ。特に大学の情報工学科で教えていることを考えると、生の情報は非常に重要である。 チャンスがあれば、いろいろとネットワークを広げることは意味があるし、いまの時代を考えれば「専門分野」という概念も大きく変わっている。知っていてムダになることは一つもないと言ってもよいだろう。 できれば、学生の早いうちに、こういう空気に触れて刺激を受けることができれば、モチベーション、自覚、モノ・コトの見え方、視野の広さなど、多くのモノ・コトが変わるだろう。そうでもないと大学にいる4年間、数百万にものぼる教育コストを有効に生かすことができずに非常にもったいない(それ以前から考えれば千万単位であり、卒業後の奨学金返済の問題もあるから単純ではない)。 詳細は省くが、パネルディスカッションは特に面白かった。 冒頭の特別講演でも話されたベッコフオートメーション(株)代表取締役社長 川野俊充氏、オーマイグラス(株)代表取締役社長 清川忠康氏、Kii (株)共同創立者・代表取締役会長、CEO 荒井真成氏の3氏は、いずれもシリコンバレーに住んでいたことがあるということで、感覚的にも「あっち」側の人といった感じである。 何が「あっち」で何が「こっち」なのかを明確に説明しようとしてもなかなか難しいが、話を聞いているうちに頭に浮かんだ言葉が「あっち」側と「こっち」側であった。 おそらく、単純にベースに置いている前提が違うということだろうが、スピード感、距離感の違いは如何ともしがたいものがある。小売業を見に何回かアメリカに行ったことがあるのとは訳が違うから、その違いは大きい。 特に荒井真成氏の話、あるいは話の仕方は、いまの学生に最も聞かせたいと思った内容である。「話の仕方」と言ったのは、難しいことをあたかも何でもないことのように言ってしまうところであり、肌感覚でしかわからないことなのかもしれないが、若い人にとって非常によい刺激になるだろう。 自らの枠組みを限定せず、いたって普通にグローバルな世界にいられることは、モノ・コトの見方・認識・判断基準、リスクの取り方、思考と行動のメカニズムなどを違うものにしているように思う。 いま、学生がいる世界は、何もしなければ、ただ穴倉の中のような世界で終わる4年間かもしれないが、そこから一歩踏み出してみると、すぐ隣にはグローバルな世界が広がっているかもしれない、とても不思議な世界である。 その可能性を活かすか否かで状況は全く変わってしまうのだろう。 そういえば、アメリカ在住で日系3世の従妹からFacebookに「ひょっとして私の従妹ではないですか?」と問い合わせがあった。30年以上コンタクトをとっていなかったのに....と驚いたものだが、これが現在、我々がいる世界なのだと改めて実感させられた出来事であった。 学生たちにも穴倉から飛び出して、あっち側とこっち側を行き来してもらいたいものである。
Archive for wpmaster
「インダストリー4.0時代 流通業の経営革命」のセミナー受講
20世紀型産業と21世紀型産業の二層構造
20世紀型産業と21世紀型産業の二層構造が顕著になりつつある。 長い時間をかけ、物をベースにして出来上がった20世紀型産業は、いまでも産業の基礎を成しており、多くのインフラとしての物を所有し、企業活動を行っている。全ての基本が物であるから、何かをやるための物を設計し、つくり、販売・購入し、メンテナンス、管理することで事業が成り立つ。当然、そこに必要となる技術、人員もすべては物ベースであるから、あくまでも物が前提となる。 一方、デジタルとネットワークによって物凄いスピードで成長、進化している21世紀型産業は、全く異なるビジネスモデルで進化、発展しようとしている。 新しい時代を象徴する事例としてよく挙げられるのがUBER(https://www.uber.com/about)だろう。日本ではまだ六本木周辺だけということだが、既に世界67ケ国に普及しているという。 アプリを介し、ドライバーとして登録した人の中から時間に空きのある人が、お客のニーズに合わせ、タクシーとしてお客に対応する。支払いはクレジットカードだから直接金銭のやり取りは発生しない。 タイム24(駐車場)、ラクスル(チラシ印刷)などと同様、シェアビジネスの典型的な事例である。不特定多数の人に、不規則に、少しずつ発生し、しかも位置的にもアチコチに分散する能力の「空き」は、そのままでは何の意味もなく、「手待ち時間=アイドルタイム」として消えていく。生産性が上がらない重要な要因である。 しかし、一つずつは小く、発生箇所では解消できない「空き」も、ニーズある人・組織とマッチングさせると一つの大きなビジネスとなる。 「空き」が有効活用でき、小さなニーズをロットに関係なく解消し、そのシステムを提案・運用する側の3者が揃って初めて成り立つビジネスモデルであり、しかも3者ともWIN-WIN-WINという関係が出来上がる。 彼らは、自ら所有することをしないから、機器を購入することも、オペレーター、ドライバーを雇うことも、機器の管理やメンテナンスもすることなく、ビジネスを創り上げる。 実体は「物をベースにした20世紀型産業」だが、多くのモノ・コトを効率よく動かし、利益を上げるのは「デジタルとネットワークによる21世紀型産業」である。 だからこそ、物凄いスピードで成長し、売上・利益も拡大している 時価総額、収益力、成長性などを比べてみても、全ての面で圧倒するのは短機関で急拡大してきたIT系企業ばかりが目立つ。 すでに先進国は経済がサービス化していることから次なる成長はサービス産業にかかっていると言っても過言ではない。(昔から多くの人がそういっているが、実態はなかなかそうなっていないケースも多い) 安倍首相が「生産性運動60周年記念パーティー(主催;日本生産性本部)」の席上で「日本再興戦略の中で、経済成長の切り札としてサービス産業の生産性向上を位置づけた」とし、サービス生産性革命の必要性を訴えている。目指すべき方向性として①Google、Amazonに代表されるようなイノベーティブなサービス産業、②「おもてなし」に代表されるような質が高くリスペクトされるサービス産業(ふさわしい評価と対価が得られるためにサービス大賞の創設とサービスの質の見える化)、③言語、金融(クレジットカード、ATM)など様々な面で、シームレスでストレスのないグローバルなサービス産業の3つを提示している。 しかし、そんな先進国のベースを支えているのは、他でもない物をベースにした20世紀型産業だから、ややこしい。 問題があるとすれば、物ベースの時代に長い時間かけて出来上がってきた秩序や規制、所有することで作り上げてきたインフラと新しいビジネスモデルの仕組みが相互に矛盾する場合である。 多くの場合、規制などは非効率を生み出しているから、サービスの生産性向上には規制を廃止する必要がある。長年かけて出来上がった秩序や規制を取り払うことで、大きな生産性向上が実現できるが、そのためには大きな犠牲が必要になるから反発も多い。(例えば、1000円ヘアカットを政府が新しいビジネスモデルの事例としてとり上げたにもかかわらず、一方では、明らかにそれを規制するような条例が多くの県で制定されている) それでも前に進むのか、それとも躊躇して進化を止めるのか、選択の仕方一つで将来は大きく左右される。 重要なことは、ユニコーン企業も革新的な世界的規模のIT系企業も日本からは出ていないこと=ほとんどのプラットフォームは海外の企業によって占められているから、収益の多くは海外の企業に集中しているという事実、現状をどうとらえるかである。 先日、ある雑誌の原稿で「通販業界の明暗 好調アスクルと不調ニッセン」なるテーマがあった。 ポータル、あるいはプラットフォームとしての機能も備えるYahoo!とアスクルは何らかの化学反応を起こしたが、セブン-イレブン・ジャパンというリアルネットワークと通販名簿を持つニッセンの組合せでは化学反応は起きなかったということだろう。 いろいろと状況を観察して分かることは、物をベースにした20世紀型産業の時代には「売上、利益」は店舗が大きい、店舗数が多いなど物の量に左右されたが、デジタルとネットワークの時代にはプラットフォームをおさえた企業に「売上、利益」は集中する。 世の中、有料道路が圧倒的有利ということになれば、みな有料道路を通るしかないから、黙っていても有料道路を所有している企業に収益は集まってくる。 Microsoft、Google、Yahoo!、Facebook、...。 この理屈さえ分かれば、経営そのものは大きく変わるはずだが、未だに物としてのインフラをベースにしてしか発想しない20世紀型企業は、有料道路以外の活路を探し続けるしかないのだろう。 現在、そして将来をどう読むかの違いは大きく、企業の勢力図は短期間で大きく塗り替わる可能性が高い。
野球もサッカーもエキスパートエラー?
なぜ、ヒット1本しか打たれておらず、しかも85球しか投げていなかった大谷を替えたのか? なぜ、ホームのシンガポール戦では23本ものシュートを打ちながら、スコアレスドローに終わったのか? いろいろな解説や批判があったが、また、別の角度から見てみると「エキスパートエラー」なるものの存在が考えられる。 「エキスパートエラー」は、一言でいうと専門家ゆえの間違えである。正常性バイアスや多数派(集団)同調バイアスなどと同様、災害時に被害を大きくしてしまう一つの原因と考えられている。 詳細は省くが、9.11の際も専門家と電話で相談した結果、避難せずに貿易センタービル上階に留まった方がよいという判断があったというし、セウォール号でも船室に留まることを指示する船内放送があった。 咄嗟の判断ではあるが、過去の経験や知識を基にしたプロの判断が結果的に被害を大きくしてしまったことになる。 同様なことは、3.11東日本大震災の時も起こっている。 津波の規模を読み間違えて結果的に避難しなかった。あるいは、震災後、多くの地震学者が「想定外」という言葉を使っていたように、自身の研究範囲からその規模を除外して判断していた。原発で電源が確保できなかったことなども同様と考えてよいだろう。発想の原点を「安全」に置いたか「危険」に置いたかで、あとの発想、準備、意思決定はすべて変わる。 多くの専門家が、専門家ゆえに間違いを起こす。そのような判断に疑問を呈していた学者も少なからずいたことは、事が起こった後になって分かるから難しい。少数派、非主流派の意見はなかなか表に出てくることはないし、それを基に物事が動くことも少ない。 そこで野球の話に戻ると、なぜ、ヒット1本の完投ペースで投げていた大谷投手が降板したのかである。以前「勝利の方程式」なる言葉で表現されていたが、先発がある程度順調に投げてリードしていると、途中から決まった中継ぎ、ストッパーが出てきて試合を閉める勝ちパターンの投手リレーがあった。 そのような必要性があったかどうかは別にして、今回もそのような決まったパターンに当てはめようとしたのではないだろうか。(もちろん、年内最後の先発だから、その後に投球予定がない大谷投手が余裕を残して降板する必要はなかった訳だが...)キチンと決まれば、きれいな終わり方であるから、選択肢としては否定できない。 ちょっと視点は変わるが、サッカーも似たような感じがしている。 サッカーは知恵比べだから、スペインがワールドカップで優勝した次には、スペインのパスサッカーを破るフォーメーション、戦術を開発するチームが出てくる。フォーメーション、戦術は相手によって変わるから、「絶対」というものはなく、連覇は非常に難しい。 当然、引いて守るサッカーが良いか悪いかの議論は意味がなく、引いて守るサッカーを敗れなければ、それは知恵がないということにもなる。(そもそも何年か前には逆に日本が守りに守ってフランスを1-0で破っているから、逆の立場も十分すぎるくらいに知っているはずであるが...) ここでのエキスパートエラーは、サッカーのフォーメーション、それぞれのポジションの役割や戦術、なかなか点が入らなかった過去の試合の記憶、残り時間など試合中の心理状態...等々、いろいろと考えられるが、何よりも経験豊富な人たちがプロとして緻密なサッカーをやろうとし過ぎたからではないだろうか。 ホームのカンボジア戦では3点のうち、2点までがミドルシュートであった。人数をたくさん割いて相手のゴール前で必死に攻撃しても入らなかった点が、距離をおいて遠目から打ったら入っている(入ってしまった)。
「商品を売る」ための法則
商品がどのように売れるのか、小売業に限らず、卸売業、メーカーなど多くの人が興味のあることだろう。 いろいろ商品構成や売場づくりをいじっていくと、いくつかの法則(あるいは法則というまでではないが傾向)があることに気が付く。おそらく、売場で多くの経験がある人であれば、少なからず、このような法則を知っているだろうが、残念なことに個人の経験・ノウハウとしてあるだけで、人とともに売場から消え去ってしまうのが実情である。 昔から「売場にある知識・経験・技術・ノウハウ」を大切にしてこなかった小売業の体質が、長年培ってきた財産を消失させていると言ってよいだろう。 ◉食品スーパーのあるベテラン店長は、様々な実験を繰り返した結果、野菜をバラで売る時の値付けは78円が一番数量、金額とも伸び、利益も取れると教えてくれた。 ◉爆発点という考え方があり、商品の陳列規模(数量や露出の仕方)を拡大していくと、一定の規模を超えた時点で飛躍的に売上が伸びると言われていた。実際に中途半端にやるよりは、ダイナミックな展開をする方がはるかに多くの売上が得られる。爆発点の手前では多少在庫を増やしても販売量が飛躍的に増えることはない。ちょっとの差が結果に大きな差となって表れる。どうせやるなら爆発点を超えた方がはるかに効率がよいし、「売った~ッ」といった感覚、「売上を上げる楽しさ、面白さ」を味わうことができる。 ◉爆発点と似ているが、いろいろな実験を繰り返してみると、コモディティ商品については陳列量を増やし、フェイスを拡大すると売上は確実に伸びる。在庫数量が多いと発注精度も気にならないし、欠品を起こすリスクもなくなるから楽である。 ◉比較的高額な価格帯の商品を売りたい時には、さらにその上の価格帯に「売らなくてもよい商品(見せて比較する役割を果たす)」を置くと売りたい価格帯の商品が売りやすくなる。もちろん、見せるだけのつもりの商品が売れることもあるから、。その時にはさらに上の価格帯に商品を配置する。 ◉売場における商品分類は非常に重要である。ずいぶん昔の話になるが、あるホームセンターのカー用品売場でカーワックスの分類の仕方を変えたことがある。固形/半練り/液体という形態別分類を色別に直しただけだが、お客が商品を選ぶ際のやり方とマッチしたことでアイテムを全くいじらないのに売上が4割伸びた。お客が選ぶ順序に従って売場を直すことで商品が選びやすくなったことが理由だろう。それ以降、商品分類(クラシフィケーション;商品特性による分類)を修正することでいろいろな店、いろいろな商品の売上を伸ばしているから、売場づくりにとって非常に重要なキーワードということができるだろう。 ◉多箇所展開が盛んに行われている業態もあるが、商品をよく見ていくと、定番売場でフェイスを広げた方がよい商品、エンドに単品大量陳列をした方がよい商品、平台に山積みにした方がよい商品、多箇所展開した方がよい商品というように、商品によって向き不向きがあることが分かる。商品特性=お客の売場での買い方を考えた上で陳列場所・方法を選ぶ必要がある。在庫管理や商品補充など売場管理のしやすさもあるが、10個、20個、...と分散させて多箇所陳列する要も一箇所に100個まとめて陳列した方が認知されやすく、売場管理も楽になり、商品回転率も上がるというケースは多い。 ◉商品には、お客が価格の安さで買う商品(お客が値頃の価格を知っている)、機能・性能の良さで買う商品、イメージの良さで買う商品がある。価格で買う商品は「価格の安さ」が分かるように大量陳列、価格表示を明確にする、機能・性能の良さはPOP、動画、実演などで「良さ」が伝わるようにする、イメージの良さはカラーコントロールやディスプレーでイメージの良さが伝わるようにして売ることが大切である。しかし、多くの店でどんな商品も同じPOPを付け、同じ売場表現をしている。残念である。 基本的に、どの業態もお客の中心は女性である。女性が好む売場、表現方法と効率だけを追求した結果出来上がった売場、表現方法は根本的に違う。重要なことは効率=成果÷投入資源であるから、必ずしも全ての無駄をそぎ落として無機質な売場をつくる必要はない。 ◉営業中に売場の手直しをしていると、なぜかお客が寄ってくる。それまであまり目立たなかった商品が売れることもあるから不思議である。 その不思議を不思議で済ませずに生かすことで他社と差別化を図り、売上を伸ばしてきたのがジョイフル本田、ドン・キホーテ、ビレッジバンガードなどだろう。 あるホームセンターの役員が退職前に「効率を追求し、一生懸命ローコストに取り組んできたが、結局効率の向こうに効率はなかった」としみじみと言っていたのが印象的であった。 そう考えれば、効率追求の本質を理解して取り組んだのがセブン-イレブン・ジャパンということになるのかも知れない。いろいろ後講釈を言う人は多いが、結局は儲け方を知っていたという一言に尽きるだろう。 分かるか分からないかの差は大きい。
総合スーパー(GMS)再生の構造的障害、同じ構造的障害を抱えるショッピングセンター
総合スーパー(GMS)再生の障害はいくつか考えられる。
最も大きな問題は、いろいろな意味で広い衣料品売場に変わる商品が見つからないことである。
いくら衣料品の売上が減少し、食品売場がお客で溢れたとしても、マーケットサイズとシェア、粗利率、運用コストの違いを考えると安定的に売上が取れる食品をいくら広げても衣料品の穴を埋めることは難しい。
飲食やサービスにスペースを割くことも考えられないわけではないが、設備投資、坪売上/坪粗利を考えると食品よりもさらに難しい。
一店舗だけの問題でなく、総合スーパー(GMS)という業態の構造的な問題であるから、いつかは決断する必要があるのだろうが、衣料品と同じだけの粗利高(坪粗利、粗利総額)を稼ぎ出せるモノが見つからない限り、いつまで経っても、このジレンマから抜け出すことはできない。
立地の影響も大きい。人口動態や立地環境の変化(類似する商業施設の増加、鉄道の乗り入れなどによる都心部への時間的距離短縮など)など、いろいろな与件を考えると、足元商圏だけに頼るコモディティ型の大型総合スーパー(GMS)は、将来的なことを含めてより難しい状況にある。
いっそのこと、新しい方向へ踏み出すためにも、粗利高(坪粗利、粗利総額)を諦めてしまうというのも一つの方法だと思うが、お金に関わる問題だけにそう簡単にもいかないから悩ましい。
どこに基準を置くかという問題もあるが、少なくとも衣料品売場を広げた時代の数値をイメージしているのであれば身動きが取れない。
どこまで基準(収益)を下げることができるかによって選択肢も広がるのだが、それもなかなか難しいから八方塞がりである。
業績は悪化し、改善しない。しかし、代わりになるモノが見つからない。そんな状況がかれこれ20年も続いていれば(修正に取り組んでいるとそんなに時間が経っていたことにも気が付かず、いつの間にか常態化する)、閉店、撤退という結論になるのだろうが、契約、雇用を含めた周辺への影響、コスト、売上の大幅な減少などを考えれば、それもなかなか難しい。
現状で考えられる策は、衣料品を中心にして適正規模に圧縮し、損益を改善することしかないが、いつまでも結論を先延ばしにしてもしょうがない。
ずいぶん以前になるが、総合スーパー(GMS)がダメならば、食品はマックスバリュ、住関連はメガマート、衣料品は衣料マックスバリュ(衣料品のマックスバリュバージョン)で構成し直す方がよいのではと提案したことがある。
一般的な商品の総合によるワンストップショッピングが難しければ、専門性やディスカントなど、何らかの特徴ある品揃えと損益分岐点の低い運用システムの組合せにした方がまだ可能性は高い。
いずれにせよ、バブル期に創り上げた総合スーパー像、売上・利益のイメージが次のステップを踏み出す上で大きな障害となっていることだけは確かだろう。
同じジレンマに陥る可能性の高いショッピングセンターの方がテナントを入れ替えることができるという点では総合スーパー(GMS)よりまだ少しは選択肢が広いのかも知れないが、基本的な構造は全く同じである。
ビジネスモデルの修正は損益構造の修正でもあるから、損益構造から発想した方がいいのかも知れない。
単純に考えれば、「小売」にこだわり続けるのか、それとも経営として成り立つようなテナントミックス(小売にこだわらない)を考えるのか、ということになるだろう。
大家としては、家賃が確保できれば小売業の面積を圧縮することには何の問題もない。
ケアハウスや保育園がダメなのは、収益構造の問題であるから、新たなビジネスモデル(例えばインバウンドを意識した観光型ホテル+免税品販売+観光サービス)を開発して6次化するなど収益が確保できる方法を確立するしかない。
いずれにせよ、「小売」という範疇に限定せず、広く答えを探さない限り、答えを得ることは難しい。
分かるか、分からないか
ある企業で不振対策のためにバイヤーから話を聞いた。「現在、最も意識してやっていることは?」という問いにバイヤーから返ってきた答えは「店への十分な対応をするために本部にいて直ぐに電話に出られるようにすること」だという。 業績不振企業のバイヤーの最優先業務が「売れる商品の開発や粗利率アップ」でないのでは、いつまで経ってもこの状況から抜け出すことは難しい。 ある企業で52週の販売実績データを過去2年分+今年のデータの3年分をまとめてグラフ化してもらっていた。 グラフを見ていると、一昨年、昨年と今年のグラフがほぼ同じでいつまで経っても変化がない。 時系列データ(52週のグラフ)に期待することは、本来売上が取れるタイミングで仕掛けていない、売れるタイミングに欠品を起こして売りそこなっている、仕掛けのタイミングが速すぎる・遅すぎるなど、おかしな点を見つけて修正し、運用に活かすことである。同じグラフが3年も続くということは、毎年同じことしかしていないということになる。 「データは重要だ」と誰もが言うが、本当の意味を理解しないとそのデータを活かして結果を変えることができない。 データは記録すること(ストック)が目的ではなく、使うこと(フロー)が目的である。しかし、勘違いすると記録すること(データ蓄積のための機械的作業)ばかり一生懸命になって使うことをしなくなる。グループワークなどで賢い人が真っ先に書記を申し出るのと同じで、何も考えなくても、ディスカッションに参加しなくても、他人が言っていることを書いてさえいればよいから楽である。 去年のデータを見て、去年と同じことを繰り返せば、いつまで経ってもグラフの山谷の位置、形は変わらない。欠品を起こす所まで同じだともう笑うしかない。 ある優秀な店長と一緒に店舗の売上アップに取り組んだことがある。地道な努力のかいあって、売上、客数とも確実に伸び、店のモチベーションも非常に高まっていった。 当然、幹部社員、全店長の前で発表することになるが、どんなに聞いてもやったことの無い人にはなかなか本質が理解ができない。 熱心な店長の中には詳細な資料ファイルを欲しがる人もいるが、もらっただけで終わるケースがほとんどである。 改善活動の後に残った資料やデータは、いろいろな障害を一つ一つクリアしていく際に頭(思考)を整理するために使った道具である。仮説を立てて実験し、そこから見つかった問題をさらに解決するために様々な工夫する。まさにもがき苦しんだ記録である。 基本的な考え方や手順についてアドバイスした私が見ても、実際の活動記録を理解することは不可能だから、資料やデータをもらってもまず見ることはない。 データの意味、本質を理解していないと、たくさんの資料、データを欲しがることがある。しかし、それらは人からもらってたくさん持つことに意味があるのではない。 実際に改善活動に取り組んでいれば、問題意識を具体化し、様々な工夫をするたびに黙っていてもどんどん溜まっていくから、改善の進捗(状況がどんどん変わる)とともにほとんど意味を持たなくなる。 物事の「本質」、「意味」が分かるか分からないかの違いは大きい。それは個人であっても組織であっても同じことである。
「商品が売れる」というメカニズム
◆商品について知りたいこと
商品を売る側にとって「どんな商品が」「どのような理由で」「どのようにすれば」「どのくらい売れるのか」ということは非常に重要なテーマである。
「いつ」「どこで」「何が(商品・価格)」「どのように(売れ方=頻度、タイミング・お客の集中度合い)」「どのくらい」という情報が分かれば、商品・売場・人員を準備をするのに苦労はない。
ある意味、売れる商品と売れる時期、数量、売れ方(買う人・売れるタイミングなどの集中度合い)が分かれば、誰が買っているかはあまり関係ない。
誰が、どのような理由で買っているかは、売れる商品、時期、数量、売れ方などが分からないため、それを推測するために必要なだけであるから、要は何がいつ、いくつ売れるかさえ分かればよい。
◆商品がなぜ売れるのか、どのように売れるのか
商品が売れる、言い方を換えると「商品を買う」ということは物理的な問題と心理的な問題が関係する。
物理的理由か心理的理由かによって、明確に納得がいく「商品を買う理由」があるか、ないかが決まる。
マーケティングでは「ニーズ」「ウォンツ」などという言い方をするが、商品を必要だから、欲しいから買うというのは、ある意味正しい側面もあるが、それは過去の物がない時代の話であって、いまのように物が溢れ余っている時代には全くの錯覚ではないかと思えることも多い。
実際に我々の身の回りを見れば、必要のない物、なぜ買ってしまったのか分からない物で溢れている。
よくあるパターンが「とりあえず買っておこう」というものや、何でもいいから買うことで「欲求不満を満足させる、ストレス解消する」というものである。
買物依存症という言葉もあるが、このような場合には「買うこと」自体が目的になるから、買った物がその時点で必要だったか、欲しかったかということはあまり関係ない。
セミナーや授業で「買物実験(商品の干渉)」というものをよくやる。
実験の対象はスーツ、弁当、ポロシャツの3つである。いずれの場合も条件を変えながら、受講生・学生にどれを買うのか、あるいは買わないのかを聞いていく。
①スーツ
1万円から10万円まで1万円刻みでスーツが品揃えされている。いくらのスーツを買うかを聞いていく。多くは4~6万円を中心にし、その両側に行くにしたがって人数は減る。
次に購入希望がゼロ、あるいは極端に少なかった高額の方から商品をカットして1~7万円くらいの品揃えにする。そうすると中心価格は3~4万円に下がる。さらに売れなくなった上の価格をカットし、1~5万円くらいの品揃えにすると中心価格は2~3万円に下がる。
さらに購入しないという選択肢を与えると品揃えの幅が狭まるにしたがって購入しないと答える人数を増える。
売れない価格帯を上から削っていくにしたがって、確実に平均単価は下がり、選択の幅が狭まるにしたがって買わないという人数も増える。これまでPOSを使って死筋をカットするといういたって当り前のことをした結果である。
②弁当
コロッケ弁当、メンチカツ弁当、チキンカツ弁当、トンカツ弁当、ビーフカツ弁当の5つを用意する。白飯と煮物、おしんこがついている。
全てを500円としてどれを買うか聞く。ほとんどの人がトンカツ弁当とビーフカツ弁に集中する。
次にビーフカツ弁当を500円とし、トンカツ弁当480円、チキンカツ弁当460円、メンチカツ弁当440円、コロッケ弁当420円と20円ずつ差をつけてみる。この場合は500円均一の時とほぼ同じになるから、この価格差はあまり意味がない。
次に50円ずつ差をつけ、ビーフカツ弁当500円、トンカツ弁当450円、チキンカツ弁当398円、メンチカツ弁当350円、コロッケ弁当298円としてみる。この段階で選ぶ弁当が大きくばらけていく。それぞれの弁当の値頃、おかずと価格の関係が上手くバランスする価格差と考えられ、最も自然な形でみんなが選択する。ただし、選んだ理由を聞いてみると、好きだから、安いからなど、選択にはいろいろな理由があることが分かる。
さらに、50円の価格差を付けたまま、ビーフカツ弁当だけを日替わりと称してコロッケ弁当と同じ298円にしてみる。結果は、一気にビーフカツ弁当に集中する。好き・嫌いとは関係なく、損得勘定だけで選択する弁当は大きく変わる。
*ほとんどの人はビーフカツを見たことも食べたこともない。
③ポロシャツ
はじめは白と赤2色の品揃えに買わないという3択で聞いてみる。白が多いが買わない人も多い。次にピンク、クリーム、パープルを加えて5色+買わないの6択とする。前と大きく変わらない。
ここからモスグリーン、ネイビー、グレー、ブラックと1色ずつ加えていく。加えるたびに新たに加えた色に移行する人が増え(そのように色の順序を設定している)、買わないという人も減る。
最後に誰も買わないと言っていた色をカットする。多くの場合、ネイビー、グレー、ブラックしか残らない。この時点では誰も買わないという色だけをカットしているにもかかわらず、「買わない」を選択する人数が増える。
自分が買う色、買わない色という単純な条件だけで「買うか」「買わないか」は決まらないようである。
3つの実験から分かるのは、「商品さえ良ければ...」「売れる商品」「売れない商品」「高い」「安い」...など、いろいろなことを言ってみても、売場の状況、周囲にある商品などが商品購入に大きく影響していることが分かる。
在庫や周囲にある商品の影響(商品の干渉)が分からい状態では、POSデータは参考にはなるが、それ以上でも以下でもないことが分かる。
◉実験のおまけ
PB商品とNB商品の価格差を変えながら、それぞれがいくらの時、どちらを選ぶかを聞いてみる。
水・お茶などのペットボトルの場合、少しでも安ければPB商品を選ぶ人が増えるが、コーラでは売価が2倍違ってもNB商品を選ぶ人が多い。
PB商品の普及・定着度合が大きく影響している。何でもいいわけではない。
◆商品が売れるキーワード=クラシフィケーション
「商品がなぜ売れるのか」ということに関しては、その裏にある人の心理まで測定することは難しい。結局は売れた商品と売れ方(タイミングや集中度合い)など測定可能なデータを見ながら判断するしかない。
ただし、商品と価格だけを見ているのでは、よほど商品知識がないと解釈を間違える。
ずいぶん前になるが、子供のサッカーボール980円、1280円を売っている店と980円、1280円と2980円、4800円を扱っている店を比較して、こっちは高い、こっちは安いと分析していた例を見たことがある。
知らない人がただ価格だけを見れば高い、安いということになるが、安いのは子供のおもちゃ、高い方はサッカークラブで使う4号の練習球だから高いのではなく、商品そのものが全く別物である。おもちゃを売っている店はそれだけだが、クラブで使う練習球を扱う店はトレーニングシューズ、スパイク、ストッキング、スネあてなども扱っているはずである。
要するに商品を見る上で価格も重要だが、もう一つ価格やお客が選択するための商品が持つ特性(クラシフィケーション)を抑えておく必要がある。
例えば風邪薬を選ぶなら症状や剤形、容量(日数)だし、衣料品ならデザイン、素材、色・柄、サイズなどである。
商品にはいろいろな特性があるが、商品選択に全てが関与しているというわけではないから、お客が購入する際にキーワードとしている特性(クラシフィケーション)を特定することは重要である。
例えば、カジュアルシャツを選ぶ際、デザインなのか、色・柄なのか、素材なのか、ブランドなのか、...。
それを知るために、これらを表頭、表側に置くマトリックスをつくってみる。デザイン×色・柄、デザイン×素材、デザイン×サイズ、...などである。
ほとんどの場合、一定の比率で売れているから、それがその特性を支持する人の比率と考えられる(理由までは分からない)。
この売れる比率を基に商品構成を考えるが、ここで商品の購入実験(商品の干渉)で得られた法則が重要になる。
どの商品を選ぶかは、周囲にある商品や価格に影響を受けるから、それらを考慮して商品の売れ方を誘導、あるいはコントロールするような商品配置、売場陳列をする。
多くの企業でビーフカツ弁当を298円にしたような価格設定をするから、無意味に利益の無い商品に販売が集中し、多くのスペース、在庫金額を割いている定番商品が死んでしまう。定番商品と特売商品は別物ではなく、合わせてワンセットであるから、定番商品の設定の仕方と特売商品の設定の仕方は関連させて考える必要がある。
なぜ、売れるのかが分からなくても、何に影響されるか、どんな影響のされ方をするのかが分かれば、売れる商品や量をコントロールすることはある程度可能になる。
売場づくり、商品構成の醍醐味であるが、今ではそのようなプロフェッショナルな発想をする人も減っている。その代わりとしてビッグデータやAI(人工知能)が期待されているが、実用化はまだまだ先であるし、ゼロから有を生み出すことは機械には難しい。
問題意識があって、はじめて仮説が生まれ、実験ができる。その蓄積からでしかノウハウは生まれないから、商品構成を遊べる人が大切になる。
何でもたくさんの画面、帳票が出るシステムがよいシステムか⁉
随分前になるが、あるコンピュータ関連の企業にアドバイザリー契約で行っていた時のことである。 ちょうど私がいる時に、現在商談を進めている取引先が打ち合わせに来るという。よく聞けば、以前私が商品部を指導していた企業でバイヤーをやっていた人が情報システムの部署に移り、その人が来るという。 久しぶりの対面でいろいろと話したが、システムの話になると「とにかくたくさんの画面と帳票が欲しい」「何でもいいからたくさん出せて安いのを要望してこいと言われて来た」という。 小売業に限らないのかも知れないが、情報システムについての本当の理解がないと、画面も帳票もたくさんあることがよいという、まるで一山いくらで商品の価格交渉をしているような感覚で情報システムを考えているケースがある。 その裏返しがシステムをつくる側のSEということになるのだろう。Excelのピボットテーブルのように、自由にいろいろな組み合わせができるテーブルを提案する。とにかく、いろいろな手法を調べてきて、それらをメニューに加えようとする。 結局、「何でもできる」というシステムがまともに使えたことがないから、難しいシステムを高いコストをかけてつくり、しかも複雑だから後々メンテナンスも大変なシステムをつくり上げてしまう。 目的的に考えれば、このような価値観、考えのおかしさがよく分かる。 情報システムは、どんな形でアウトプットを出したとしても、要するに「業務で使う」ことが目的である。 「業務の精度を上げる」「業務の手間を省く」というのが主な目的であると考えれば、ベースにあるのは本部であろうが、店であろうが、そこで日常的に行われている「業務」に役に立たなければ意味がない。 本部や店で日常的に行われているルーチン業務、そこで行われる意思決定は、そんなに複雑ではない。 要するに計画に対してより多く売れたのか、それとも売れてないかのどちらかであるから、至って単純である。 売れ過ぎれば、予定よりも在庫が少なくなり売り逃しが発生する可能性があるから商品を追加する。追加するにはどの商品をどのくらい追加すればよいかということが分かればよい。 逆に予定よりも売れなかった場合には、予定よりも在庫が多く残るからどこかで仕入れを減らすなり、値下げをして販売数量を伸ばすことで在庫の調整をする。 いずれの場合も程度問題で、修正行動が必要な場合ととりあえずは様子を見るという場合に分かれる。 したがって、とりあえず必要なことは売上、在庫、仕入のバランスを見ることである。仕入のバランスが値入率を決めるし、仕入と売上のバランスが悪ければ在庫のバランスが崩れ、値下を含めて粗利が下がる。 業務の入口で必要となるのは売上、在庫、仕入、値入、粗利、客数、客単価、買上単価、買上点数であるから、これらが52週間という時系列でどのように進捗しているかが分かれば、とりあえずのことは事足りる。 全社/全部門、商品部としての全社/部門/ライン/クラス、店長/店部門/店ライン/店クラスなどは同じ帳票の単位違いだから、一つの帳票をドリルダウン、ドリルアップするだけで済む。 どの単位でも数値の異常を探すには下の単位を見ればよいから、異常値の原因は下の単位の構成比、あるいは前述の売上以下9つの数値のバランスを見れば済む。 あと必要になるのは商品構成を見るマトリックス(クラシフィケーション・マトリックス;商品特性×商品特性、商品特性×価格 Excelのピボットテーブルでできる)、商品部が見る取引先構成、取引先別値入率、発注/未納率、販売部が見る全社の店別散布図(売上/経常利益)などであるが、これらは定期的に確認する程度で高頻度で見る必要はない。 要するにたくさんいろいろな帳票が出たとしても、そんなものを見ているだけの時間をとれる部署は少ないし、仮に多くの画面があったとすれば、よほどインターフェイス、操作性をよくしない限り、画面操作に時間ばかり取られて業務効率は著しく低下する。 業務量分析をしてみれば分かるが、POS導入以降、実に多くのムダなオペレーション(価値を生まない作業時間)が生まれ、本来業務のクオリティを低下させている。 日常的な業務目的、開発コスト、メンテナンス/更新のコスト・容易性、...など、あらゆることを考えればシステムは単純で扱いやすく、分かりやすいのが一番である。 総合スーパー、食品スーパー、ホームセンター、コンビニエンスストア、ドラッグストア、....等々、様々な業態があるが、要するに商品を仕入れて売っているだけだし、全てのデータの基は仕入伝票に記載されているデータ(取引先名・コード、商品コード・JAN・商品名、売価、原価、数量)がベースだから、標準的なシステムを一つつくりさえすれば、あとはそれらのアレンジで済むはずである。違いがあるのは、生鮮食品の原価法と売価還元という粗利計算間違い、その他商品サイクルやアイテム数くらいである。 このような筆者の問いかけに対し、長年、大手企業のシステムを支えてきたあるシステムのプロはこのように応えてくれた。 要求事項さえ、キチンとできていれば標準的なシステムを一つつくれば済むが、各社各様にいろいろな注文を出してくるから、どうしてもそれに合せてカスタマイズをせざるを得ない。第一、標準的なシステム一つで済んでしまったら、これだけの規模の業界、これだけの人数がいるSE、プログラマーを養っていけない。 まさに、その通りではあるが、そのために様々なロスが生じていると思うと非常に複雑な思いである。 いっそのこと、標準的なシステムを一つつくり、それに合わせて業務の仕組みも変えてしまえば、非常にローコストで効率的な業務システムができると思うのだが....。
GMS(総合スーパー)からSMS(専門スーパー)へ
◆巨大なコンビニエンスと化したGMS
アメリカではGMSという業態はディスカウントストア、もしくは百貨店に業態転換して消滅しており、我国でもGMSという業態の存在に対する疑問の声が挙がっている。
商業施設の増加に伴い、様々な店舗・業態が生まれ、さらにインターネット通販が加わったことで商品供給チャネルは確実に多様化している。
また、一般消費者の中には就業人口の6割(現在は7割)を占める第3次産業就業者、学生・フリーター・主婦など第3次産業でのパート・アルバイトの経験を持ち、小売業の裏側を知る消費者が増え続けている。店舗の内情だけではなく、中には商品原価や問屋ルートなどまでを知り尽くしている人も少なからずいる。現に筆者が教える芝浦工大の授業では「品出し」「前出し」と言って通じる学生は少なくないし、中には商品やファストフードの原価をレポートに書いてくる学生もいて驚かされる。
多くの商品情報と経験・知識を持ち、消費することに習熟した消費者、流通・小売での就業経験を持つ消費者は、専門的な立場から商品・価格を評価することも、魅力ある店舗を見分けることもでき、そのための情報を入手する術も持ち合わせている。(いまでは、情報を発信し合っている)
商品を購入することに習熟し、なおかつ多くの選択肢を持つ消費者には、巨大なコンビニエンスストアと化したGMSで「一箇所でいろいろなものが揃うから」という理由だけでワンストップショッピングをする必要はない。1000坪~3000坪超の専門量販店が珍しくない時代にフルラインで3000坪~4000坪というGMSは既に大きな店舗ではない(Web上の品揃えを考えれば比べ物にならない)
多くのGMSで食品の売上構成比が40~50%前後になっている。実体は総合スーパーというよりもSSM(スーパースーパーマーケット)に近いと言ってよいだろう。 その結果、GMS を核とした3万㎡クラスのショッピングセンターの商圏が食品スーパー並みの半径2~3kmというケースも見受けられる。
すでにGMSは,取敢えずの商品が一通り揃う巨大なコンビニエンスストアとしての機能だけで成立していることになる。
◆GMSからSMSへ
10年(いまから20年)以上も前にGMS (General Merchandise Store)に代わる業態としてSMS(Specialty Merchandise Store)という概念を提唱したことがある。
総合化したために個々の部門の専門性が薄れ、競争力をなくしたGMSを立て直すには、個々の部門を専門店化してつくり直すしか方法はない。それぞれをショップとして確立し、ショップマスターを配置して仕入から利益管理までを任せるしか売場のレベルを上げることはできない。
GMSの総ての間違いは、カジュアルウエアなどインショップ化した商品部門を別事業部・別会社に分離し、残った商品だけで売場=平場を構成したことにある。
時代の流れにあった商品を売場の外に出せば、残る商品に大きく望むことは難しい。売場作り、販売形態、商品など特徴あるもの総てを外に出した後に残ったのがGMSでは、弱体化することはあっても強化することなどできるはずもない。
セルフサービスで売れる商品しか扱わなくなったことは、商品面の弱体化だけではなく、人員面での弱体化も同時に引き起こしている。
一つの方向として考えられるのがSMSである。カテゴリーマネジメントより、さらに専門化したインショップをユニットとして運用し、そこで確立した手法を総ての商品に広げていけば、独立した専門店の集合業態として再生できたはずである。
10年(20年)ほど前に筆者が提唱した「食品ブティック」と全く同様の概念を取り入れた店舗がアメリカのスーパーマーケットでも見られるようになったことがある。広い売場の中に特徴のある品揃えと販売方法の「ブティーク」を組み込み、アクセントとしている。「ブティーク」は他店との差別化を図るためのものであるが、その手法を見れば、あまりにも無機質化した売場づくりに対する反省、アンチテーゼであることは一目瞭然である。
完全に総ての商品ラインをコーナー化・インショップ化したわけではないが、スーパーマーケットでさえ、このような試みをせざるを得ない状況にあることは十分認識する必要がある。まして、フルラインでファッション商品までを扱うGMSであれば尚更だろう。
物事の流れを見れば、必ず行き着く先は見えてくる。
経験・知識とも豊富で消費に習熟した消費者、インターネットの普及による豊富な情報、...。
大型家電量販店、大型スポーツ量販店、収納・インテリア・寝具などを充実させる大型ホームセンター、価格とショートタイムショッピングで存在感を増すドラッグストア、クオリティを上げる食品スーパー、紳士服専門店、ジーンズショップ、ショッピングセンター中心に拡大するファストファッション、アウトレット、観光立地の行楽型ショッピングセンター...等々、多様化した店舗形態と商品供給チャネル。
選択肢は限りなく広がっており、ドル箱である肌着がユニクロのヒートテックに取って代わられたことはGMSの凋落を象徴する出来事である。
このような環境を考えれば、ただの大きな店が成り立つことは難しい。例え特徴ある専門店やシネマコンプレックスなどを配置してショッピングセンターという形態をとったとしても、核店舗のGMSが「ただの大きな店」では長続きすることは難しい。現にショッピングセンターの中には、1年間に10億円単位で売上が減少しているところも珍しくない。
「狭く深く」「広く深く」の店づくりはどうにかなるが、「広く浅く」では難しい。大きな店にたくさん商品が置いてあっても、品揃えが豊富な魅力的な店ということにはならない。
「ローコストを目指してずっとやってきたが、ローコストの向こうにローコストはなかった」とは、ある経営者の名言である。
売場から人員を減らし、そのためにセルフサービスでも売れる商品、パート・アルバイトでも扱える商品、パート・アルバイトでも維持できる売場を志向してきたが、結局売場の販売技術・ノウハウを失っただけだけではなく、消費者からの支持もなくし、働く者からも販売という魅力ある仕事とプライドを奪って、ただの作業だけにしてしまった。
このことの代償はあまりにも大きいと言わざるを得ないだろう。
◆これからどうするのか
実は、ここまでの原稿は2003年頃、いまから10年以上前に書いた原稿に多少手を加えたものである。数値など一部の記述は( )の中に注意書きを加えたが、いま読み返してもあまり違和感がない。失われた20年、いろいろな修正を加えてみても時代の変化に対して本質的な修正ができていなかったということだろう。
1990年代(20年前)に総合スーパー (General Merchandise Store)に代わる新しい業態としてSMS(Specialty Merchandise Store)を提唱した。
すでに市場には商品も店舗も溢れている。「巨大なコンビニエンスストア」と揶揄されるように、GMSはコンビニエンス性を維持したとしても、全ての商品を巨大な売場にまんべんなく扱う意味、必要性は失われつつある。まして高齢化時代にコモディティ商品の巨大店舗は時代に逆行する。
昨今、消費サイクルを自分独りで完結できない高齢者世帯・単独世帯が増えており、サービス型小売業のニーズが拡大している。マーケットのニーズは商品面での総合化、巨大な売場より、消費サイクルを完結させるための商品とサービスの融合、あるいは物よりもサービス(例えば高齢者の余命という時間の有効活用、若者のお金は物ではなく思い出に使いたいという物離れ)へと向いている。
筆者はかつて、無印良品の可能性について提言したことがあるが、個々の商品ラインを専門ショップ(サービスを含んだビジネスユニット)として確立すれば、単独でテナント出店することもできるし、専門ショップを組み合わせたユニットとして出店することもできる。さらにユニット同士の組合せ、総合化して大型店、他社をテナント、コンセッションとしてユニットに組み込む複合化など、フレキシビリティに富んだ構成を実現できる。
モジュール化したビジネスユニット(物販に限定せずサービスも含む)により、さまざまな状況に対応できるよう自由度を増せば、多様な立地条件、事業環境の変化に対する対応力も強化できる。
重要なことは、ただでさえ、高齢化・世帯人員減少、サービス付き高齢者住宅などへの住み替え、競合の激化などで、一部の観光立地の大型商業施設を除けば、足元商圏は確実に狭まり、かつ薄まっていることである。
さらに首都圏を中心に鉄道の乗り入れが進み、時間的距離が急速に短縮していることで都心に人が集まりやすく、その分地元の足元商圏では世帯数、人口規模はある程度あったとしても生活基盤(学校・仕事・買い物・娯楽など)は都市部へ移行していく傾向にある。
実際に埼玉県、千葉県、神奈川県の3県だけでも約290万人が毎日東京へ通勤・通学しており、筆者が試算した結果では少なく見積もっても年間約3兆円が東京都内で消費されている計算になる。
かつては最寄り品か、買回り品かという購買頻度や商品の価格・耐久年数などで単純に業態=立地や取扱い商品が決まり、棲み分けることができた。
現在は足元商圏か、通過客・来訪客が来る観光立地か、あるいは実店舗でのキャッシュ&キャリーか、インターネットで商品を探し、価格を比較にして購入するかというように従来とは全く異なる要因で購入する商品、購入するチャネルが変わっている。
かつて商圏を広げることができた商品が、大型専門店やインターネットへとシフトし、確実に売上が取れる食品のウエイトばかりが高まれば、自ずと商圏は狭まり、客単価、粗利率は下がっていく。食品のウエイトがやたらと高くならざるを得ない理由である。
このように売上、客数だけを意識した方向に舵を切れば、余計に購買頻度が高く、価格に敏感な商品のウエイトが高まるから、ますます本質的な解決とは異なる方向へと向かわざるを得なくなる。
「ハイブリッド化」という表現を使ったこともあるが、店舗を維持するためには、実店舗だけでなく、インターネット、宅配、移動販売など、複数チャネルを活用してシェアを高めていくしかない。
ただし、実店舗、キャッシュ&キャリーの現物販売をベースに出来上がってきた店舗にはクリアーしなければならないハードルが多い。インターネット通販、移動販売、宅配などの手法は商圏という枠組みを超えるから、隣接する自社店舗、フランチャイズ店舗などとの棲み分けを明確にしなければならない。
レンタルビデオなどがデジタル化した場合には企業としては物から解放されて大きく効率が上がるが、地域に存在する店舗、特にフランチャイズ店舗への影響をクリア―する必要がある。
いずれにせよ、環境は大きく変化し、従来の実店舗が前提としていた条件が大きく変わっている。
前提が大きく変わっていることを考えれば、修正ではなく、進化をするしか方法はない。
神奈川県が、今後12年間で142校の約2割、最大30の県立高校を廃止する
「神奈川県が、今後12年間で142校の約2割、最大で30の県立高校を廃止する」という記事が、様々なニュースで取り上げられている。 このテーマのもとにあるのは、「県立高校改革基本計画」(平成27年1月 神奈川県教育委員会)であり、そこにはもっと色々な改革案や経緯がまとめられている。 数値を見ると、公立中学校の卒業生が昭和63年(1988年)の12万2千人をピークに減り続け、平成41年(2029年)には6万2千人にまで減るということになる。ただし、その前に生徒数が急増することに対応するため「高校百校新設計画 昭和48~62(1973~1987年)年度の15年計画」に基づいて100校を新設し、165校としているという。 「点」だけで物事を見ていると分からないことも、「線」として流れの中で把握すると見え方が変わってくる。 表面的に物事を見ると「減らす」ことばかりが強調されがちだが、生徒数が増えるのに合わせて高校を増やし、生徒数が減るのに合せて高校を減らすことは、いたって常識的な対応である。 様々なシーンで「減らす」=ネガティブ、クオリティが落ちる、....等々、多くの批判が出ることがあるが、急激な人口減少・高齢化を考えれば、これまで許されてきたようなアルベキ論、理想論ではなく、財政面を考慮した現実的な対応が必要になる。 人口減少は、市区町村の議員定数にも影響してくる。地方自治法は、地方自治体の人口に比例する形で上限数を定めているから、人口が減少すれば、議員定数も当然減ることになる。 ただし、アメリカとの比較から日本の議員定数の多さは随分以前から指摘されているが、ドラスチックにメスが入ったことは未だ一度もない。 身の回りにある多くの物事に対して、人口が減ったらそれに合わせていけばよい、高齢化すれば、その時点でそれに合わせていけばよい、といったその場対応的な対処の仕方が多いが、既にそのような対応では間に合わない事柄も増えている。 2015年から2025年までの10年間、団塊の世代500万人が70歳台に入り、75歳の健康寿命を迎える。 2018年からは1年間の人口減少幅が50万人を超え、2024年からは毎年70万人超、2028年からは80万人超、2033年からは90万人超、そして2041年からは毎年100万人超の人口減少が30年以上に渡って続くという推計結果がある。 少なくとも総人口、年齢構成、経済状況、社会保障など、様々な物事が現状維持であれば、現在の状況を続けることも可能だろうが、推計値を見れば明らかに先細りであり、しかも毎年一つの県に相当する人口が減少するとなると、ただ事ではない。我々の想像をはるかに超えた事態が起こると考えて不思議はないだろう。 人口が増え続け、1億2千万人を超えて増えていく時と、1億人を割り込んで、8000万人、6000万人、....と人口が急激に減少していく時に同じシステムで対応できるとは到底思えない。 いつまでも「点」を追い続けていくのではなく、もっと広い視点から流れを見た上で、次の時代に対応可能なシステムへ移行しないと、後追いばかりで変化のスピードにはついていけない。 東急不動産ホールディングスの新中長期経営計画を見ると面白い。10年単位で先のことを考えながら攻めていることもよくわかるし、セグメント(事業)ごとにどこに力を入れていこうとしているのかを見ていくと、時代の流れをどのように読んでいるのかがよく分かる。 2013年に対し、2016年の営業利益を柱である都市事業は319億円から415億円と約3割アップ、事業創造その他事業は-13億円から一気に60億円としているのに対し、住宅事業は116億円から55億円と半分以下でしか見ていない。(新中長期経営計画 Value Frontier 2020) 人口が減り、「住宅」需要がなくなることを見越して、全く異なる分野へと舵を切っていることが分かる。東急電鉄(沿線人口のピークは2025年)のたまプラーザテラス、二子多摩川ライズ、渋谷ヒカリエ+渋谷駅周辺の大改修とともに見ている方向は明らかに違っている。 一般消費者の「住む」「暮らす」「日常」といったマーケットの中で伸びる可能性がある思えるのはウェルネス事業だけであり、他は人が集まる都市部における事業が中心になる。 何年か経った時に公立高校がどのような姿になっているの想像もつかないが、あれだけ郊外に出ていった大学が都心に戻り、高層ビルに近代的な設備を備えていることを見れば、ある程度方向は想像がつく。 私立高校が私立大学と同じような動きになれば、公立高校はさらに苦しくなるのかも知れない。 現状を前提にして発想しているだけでは分からないことは多い。分からない人ばかり集まって物事が決まっていくことは、それはそれで恐ろしいことだが、中にいればそれが見えないから、怖さも分からない。 高校に限らず、多くの分野で起こることである。