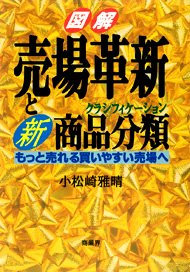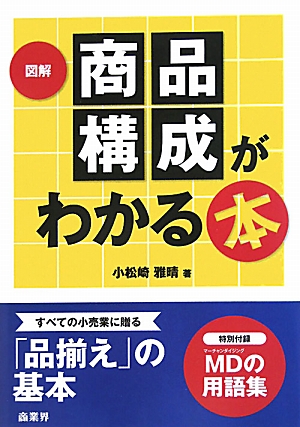だいぶ前になるが、「情報爆発」という言葉が言われていたことがある。その時代が情報爆発だったのであれば、いまは情報ビッグバンとでも言えばいいのだろうか。
Susieというサイトに掲載された「これから10年の間に大注目される!驚くほど近未来な11の職業」という記事の中に8:ニューロインプラント技師という職業がある。
脳研究のテクノロジーは大きく進歩し、頭のなかで考えていることをコンピューターにダウンロードできる時代になると脳のバックアップエンジニアやリアルタイムMRスキャナーの技師などが活躍するのではないかという近未来的な話である。
脳を研究してAIに応用し、そのうち脳とコンピュータが一体化するような話である。
この記事のように「頭の中で考えていることをダウンロードする」のも重要だろうが、ここまで情報量が増えてくると、「膨大な情報量を頭の中に入れて処理するインプットの方法とプロセス」を革命的に変更しないと頭の中に情報を入れるのに時間がかかり過ぎてどうにもならないない。
頭の中で考えていることをダウンロードするのもよいが、それよりも頭の中で情報を処理して考えるには外界にある膨大な情報を頭の中に入れ、認識させる(ダウンロード?)上手い方法を見つけ出す必要がある。
将棋電王戦の様子を詳細に追いかけたテレビ番組を見たが、すでにモニターを見ながらコンピュータとの戦い方をシミュレーションしていたのでは、経験できる=頭の中に入ってくる情報量が少なすぎて、いくら時間があっても人間の持つ24時間365日では対応できない。
残念なことに、現在我々が目や耳からインプットできる情報の形は文字、図表、音、画像、動画などでしかない。音も動画も情報量の割にはインプットするのに時間がかかり、現在のデジタルのレベルとはあまりにも掛け離れている。デジタルファイルをダウンロードするのとは単位時間当たりの情報量が桁違いである。
そうであれば、どこかの段階で文字、図表、音、画像、動画などを超える「膨大な情報量を瞬時に人間の頭の中に入れる新たな方式・仕組み」が必要になる。
一つは、文字、図表、音、画像、動画などに代わる情報の方式・形式(記号化)であり、もう一つは頭の中に認識させる(インプット)方法・仕組みである。
これができない限り、AIがどんどん進化しても、その先を開発する人間が何処かで限界を迎えてしまう。
以前、一生のうち、脳は100%有効に使われることがなく、多くの部分が未使用のままであるというような話を聞いたことがある。その未使用部分を目覚めさせて全く異なる進化をするのか(サバン症候群やアスペルガー症候群がヒント?)、PCのメモリーとCPUのようなものを脳に補助具としてつけるのかは分からないが、いずれにせよ、そのようなことが研究され、具体的になる必要があることだけは確かだろう。
教育の仕方も知識優先ではなく、頭の使い方=思考方法に切り替えていかないと、本来持っている能力を目覚めさせないまま封じ込めてしまう。
将棋電王戦を見てわかったことは、人間はコンピュータと違って「怖がる」「迷う」「自信を無くす」「後悔する」ことで本来の能力が発揮できなくなるという点である。このような感情は、実に「人間らしい」ことなのだが、人間にとっては、それらの要素を残しながらも能力を十分発揮できるような方法を見出す必要があるのだろう。