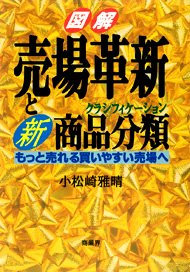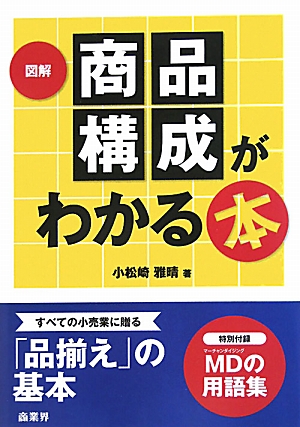「商品を増やせば売上は上がる」あるいは「アイテムを絞り込めば効率が上がる」、誰もがもっともと思える話だが、そこにある法則を理解しなければ意味のない不毛な議論と言わざるを得ない。
先日も、Webでそのような記事を見かけたが、もっともらしく聞こえてもあまり意味があるとは思えない。
そもそも、多い、少ない、売れる、売れないといっても、別項「カラスの話」に書いているように、それを判定する基準がなければ、主観的にそう思うと主張しているだけにすぎない。一見もっとらしく思えるかもしれないが、よく考えてみれば全く科学的ではないし、論理的でもない。
アイテム数を増やす、商品量を増やす、フェイス数、あるいは目に見える商品の陳列面を増やす、類似商品を集める、比較購買しやすい商品を集める、何ヶ所にも多ヶ所展開する、什器の見やすい・取りやすい位置に陳列する、レイアウト的に買いやすい位置に配置する、…等々、単にトータルとしての商品アイテム数や商品量、フェイス数などの問題だけでなく、商品構成を含めた様々な要素に関係する問題を整理しないとこのような結論は導けない。ある意味、表面的で全く意味のない不毛な議論ということになる。
同様にPOSデータを用いて売れ筋、死に筋などと安易に決めているケースは多いが、POSデータには、レイアウト、什器の陳列位置、フェイス数、在庫数量、類似商品・競合商品との位置関係、自店や競合店の販促などの要素は入っていない。救世主のように思われているID-POSも基本的には何も変わらない。
例えば、20フェイス、在庫数量200の商品の売上数量が20の場合と2フェイス、在庫数量20個で売上数量10個の商品があったとすると、どちらが「よく売れている」と判断するべきなのか、売上以外の要素を加えてみればみるほど=情報の精度が高まるほど判定することは難しくなる。もし、同じ条件で販売数量を比較したらどうなるかを考えれば、まずは販売効率のよい商品を広げ、逆に悪い商品を狭めて測定し、トータルとしてどうなるかを確認する必要がある。
また、同様にA、B 二つの商品があり、同じ品種の最も売れている商品Cが週販50に対し、両方とも週販1個だとして、AはCで代替えが利く類似品、Bは全く異なる規格・機能の商品でCでは代替えが利かない商品とすると、A、Bを週販1個だから両方とも死に筋と同じレベルで評価してカットの対象にするだろうか?
代替えが利く類似商品Aはなくても商品構成上問題はないが、代替えが利かないB商品がなくなれば商品構成としては明らかに選択肢が狭まる。売れるか否かという問題とは別に商品構成という店としてのポジションに影響する問題である。
商品構成は関係する要素が多く、奥が深い。単にグロスのアイテム数や商品量、売場面積、什器本数などだけでは評価できない。
そう考えると、本質を無視した議論をしてもあまり意味があるとは思えない。不毛な議論よりも精度の高い状況を如何に実現するかに時間とエネルギーを費やした方が有効である。