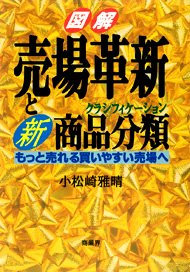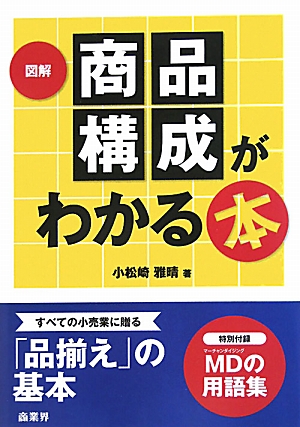いつのまにか恵方巻が世間を賑わせるようになったが、面白いのは一般には「恵方」の何たるかが全くと言ってよいほど知られていないことである。
「恵方」を調べると「陰陽道の….」とある。
陰陽道?と思うが、我々が知っているのは映画の陰陽師ぐらいで、どこから太巻きが出てきたのか?と不思議に思う。
クリスマスやバレンタインデーと一緒で、みんなで盛り上がることさえできれば、そんなことはどうでもよいのかも知れない。しかし、商売という観点から見れば、ポイントは普段あまり売れないケーキやトリのモモ、チョコレート、太巻きなどが「何らかの意味」を持つ(与える)とたくさん売れるようになるという事実である。
もちろん、その裏には企業・業界の仕掛け、マスコミが取り上げたくなる話題性、アルバイトへのノルマの押し付けなど、様々な事情もあるのだろうが、同じ商品が「ある時」「その意味を変える」と売れ方が大きく変わるという事実はおおいに注目する価値があるだろう。
◆商品が、時間と共に(時系列で)意味を変え、それに伴って売れ方が変わるというのは、小売業に限らず多くのビジネスにとって重要な意味を持つ。
売れ方が変われば、商品の原材料の手配から始まる生産体制、在庫の持ち方、仕入の仕方、販売体制、売場づくり、人員体制など、多くのモノ・コトが連動して変わる。当然、配送など物流面にも大きく影響するから、時系列変化を単に数値としてだけでなく、その変動要因となる社会行事・生活歳時などのほか天候や気温など様々な要素との関係において理解することが重要になる。
最も消費者に近い小売段階は最終的な販売と在庫調整=売上、利益、生産性などを決めるとても重要なポジションということになる。
筆者が最も基本に置いているのは52週の販売計画である。
これにはいろいろな意味があるが、主なものを整理すると次のようになる。
⓵日単位で見るのでは細かすぎるし、月でとらえてしまうと大きすぎる。月が替わるたびにリセットしたのでは、月をまたぐようなケースは捉えにくい。
⓶時間帯、日、週、旬、月、…など、いろいろな期間の取り方があるが、日常業務を見ていくと週という単位が大きすぎず、細か過ぎずちょうどよい。1か月4週という見方よりは13週(3か月)から26週(6か月)のスパンをローリング(1週過ぎたら先の1週を加え、常に13週なら13週、26週なら26週を見る)で見ていくのが、人員配置を含めた業務スケジュールなど、先のことを準備するのにちょうどよい。
また、売上、在庫、粗利など結果として現れる数値に対してし、その要因となる仕入、在庫、値入、売価変更など、結果が出るまでに時間的なズレがある数値についても時系列で見れば遡って因果関係を確認することができる。
あの時、仕入れすぎて在庫がオーバーしたから、その後値下が起きて粗利が下がった、あの時、A商品の仕入れが足りなかったから、後になって欠品を起こし、売上がショートした…等々である。
⓷時系列でモノ・コトを見る目的は、時間の経過とともに変化する状況(ある一定の法則)を見ながら将来を予測し、計画する、あるいは過去の不具合を修正し、活動の精度を高めることにある。
時系列で見ると、商品の意味の変化が売上の変化に影響し、売上の変化に伴う在庫の持ち方=仕入の仕方のタイミングや商品のバランス、売場表現、販促などが結果と連動していることがよく分かる。
例えば、在庫過多や値下が異常に増えた(粗利率が下がる)場合には、遡って仕入を見ればそこに原因があるし、逆に欠品による売上低迷が認められる時にもその原因はそこから遡った時点にあるから、どのような状況下で、どのようにして、どのようなことが起こったのか、原因の特定、異常が起こる際の因果関係=メカニズムを把握することができる。
⓸異常な事態だけではなく、上手くいった場合、大きく売上を伸ばした場合にも、その理由は遡って見ることができるから、単に結果として売上が上がる週だけではなく、その前後何週間かを見ていけば、良い場合、悪い場合とも、おおよその状況を把握することができる。
*言い方を換えれば、売上の高い週だけを見ていても、その理由を知ることはできないことになる。
また、事前告知をする大きな売り出しの場合には、必ず事前には買い控えがあり、また売り出しによる売上の先食いで後の売上低迷が起こるから、単に売り出し期間の売上を見ているだけで評価することは難しい。
以前、大手GMSなどが会員向けに大規模な割引セールを行っていたことがあるが、その週だけ見れば非常に大きな売上であるが、セールの前々週・前週、セール後の1~2週の売上まで含めて考えると、何もやらない場合と大して変わらないというケースも多々見受けられた(その結果を受けて取りやめている)。期間トータルとしての粗利率を考えれば、何もやらない方が結果として高かったということもあり、もう少し広い視点からモノ・コトを見ないと判断を間違える典型的な例ということになっている。
⓹粗利率や売上の相乗積計算は、単に商品の組合せだけではなく、商品A、B、C、…の代わりに第1週、第2週、第3週、…というように週単位の売上構成比を使っても同様にして見ることができる。このようにすれば、予算の進捗管理をしながら修正の仕方を考えて日常業務を進めることができる。
月単位での与実管理は管理会計的には重要であるが、現場での進捗管理=具体的に業務として現場の修正を行いながら業績を上げる=という観点から見れば、月ごとにリセットするよりは、累計値を継続して見る方が重要になる。
そのためにも週単位の時系列は有効な方法と言える。
⓺別項に相乗積と交叉比率をあげてあるが、⓹で説明したように商品や部門というとらえ方だけでなく、週単位の値を用いて同様のことを検討することができる。
全ての結果が出てからでは修正することができないから、少なくとも週単位に分けて数値の計画をし、それぞれの週の進捗を見ながら仕入=在庫の持ち方や粗利率の修正、売場づくり、販促などをこまめに修正していくことが重要になる。