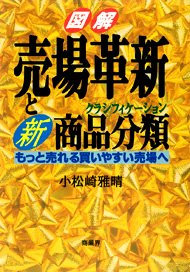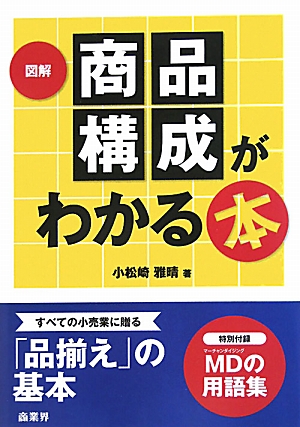マスコミで新しいライフスタイル業態、新業態と紹介された店舗をいくつか見たが、残念ながら多少内装が変わり、レイアウトが変わって、什器、陳列、品揃えが変わっただけであった。 本質的に物売りであることに何ら変わることはないから、いずれ珍しさがなくなれば、飽きられるか、現実的に日常生活で使われることが増えてくれば、数値を重視したやり方に収束していくことだろう。 表面的なつくりだけ変えて本質的に変われない理由は、売上と利益を上げる手法=ビジネスモデルが従来のまま何ら変わることがないからだろう。 客数を確保し、客単価を上げて売上を伸ばす手法が変わらない限り、どんなに内装を変え、多少商品を入替えてみても、やっていることは同じにならざるを得ない。 はじめて見た時に新鮮に思えた売場や商品も、毎日見ていれば、すぐに飽きてしまう。 日常的に使う店と、観光などで滅多にくることのないウィンドウショッピングをするような店では意味が違うから、もし、そのように性格の違う店に同じような手法を当てはめれば、いずれミスマッチが表面化してくる。 基本的に店舗はお客が慣れることで感動がなくなるということも含めて、オープン時から時間と共に陳腐化していく。時間の経過と共に進化・成長し、よりよくなっていくことはなかなか難しい。 日本の人口は2015年から2020年の5年間に約250万人、5年後の2025年までに約350万人、さらに5年ごとに400万人、450万人と減少する。 とりあえず、10年後の2025年までを見ると、600万人、約5%が減少する。その間、65歳以上人口が260万人増え、単独世帯も100万世帯増えるから、1人当たり支出、世帯支出が現在と同じとしても消費全体は現在よりも6%前後は減少すると考えてよいだろう。 年間商品販売額を140兆円、自動車と燃料を除いて約100兆円として見ると、6兆円(百貨店の売上と同じくらいの規模)くらいは減少すると考えられる。 高齢者だけが増えるというよりは、日本全体の年齢が上がる=年齢構成が変わるから、ライフステージの変化に伴うライフスタイル変化から、志向や必要なものが変わり、購入する商品、チャネルも変わると考えてよいだろう。 単純に現在ある店舗がそのままあったとすれば、全店平均して6%売上が下がるということになるが、そんなことはあり得ないので、売上を伸ばすところがある一方で売上を大きく落とす店が出てくるから、単純に考えても10~15%くらいの店舗が存続できなくなると考えてもおかしくはない。 新たに外資が参入してくることも十分考えられるし、異業種から小売に参入することも十分あり得るだろう。新たな業態が生まれて、特定のマーケットを抑えてしまうかもしれない。 その時、看板だけ架け替えて本質的に何も変われていない店舗は果たしてどうなっているだろうか。 10年は、まだまだ先の話なのか、それとも、もうすぐ目の前でアッという間に来てしまうのか、とらえ方は様々であるが、ある人がこんな話をしてくれた。 ●うちの周りには、80歳台、90歳台の人ばかりたくさんいるから、いつどこで葬儀があってもおかしくない。 ●空家が820万戸あると聞くと、何か凄いことが起きているように思うけど、気が付けば、うちの近所でも何軒かあった。 はじめはなかなか気が付くこともないが、そのうちだんだんと身の回りでもニュースでしか見なかったようなことが起こりだす。実際には起こっていても気が付かない程度だったものが、誰もが気がつくくらいの件数になるのだろう。 ただし、このような変化はボディブローのように小売店舗を疲弊させる。「茹でガエルの話」ではないが、じわりじわりで気が付いた時には遅かったということは企業には許されない。 残された時間を考えると、具体的な修正行動をとらなければならないタイミングにはなっているだろう。
Archive for wpmaster
物売りから抜け出せない小売業 10年後の2025年 どうする?
ファッションワールド東京2015 (株)良品計画 金井会長と(株)ジュン 佐々木社長のセミナーを聞いてきた
10月1日、ファッションワールド東京2015 で(株)良品計画 金井会長と(株)ジュン 佐々木社長のセミナーを聞くことができた。 金井会長は「『これでいい』を世界へ ~無印良品の思想と戦略~」というテーマで、まさに自然体でマーケットのニーズを一つ一つ掘り起こしていくという無印良品の思想をベースに現在までのビジネスを解説され、佐々木社長は「JUNが見据えるクリエイティブ産業の未来とソーシャルスタイルという概念~新たな時代に求められるリーダーシップと感性~」というテーマで、新しい世界を創造していく上でベースに置く考え方を話された。 自然体でマーケットを観察し、そこからビジネスを掘り起こしていく金井会長と「カッコよく儲けたい」と自らの力で新しい世界を創り上げ、切り開いていく佐々木社長では、一見すると東洋と西洋の違いのようなものを感じさせるが、お二人の話を連続して聞いてみると、非常によく似ているというか、共通点が多いことに思わずうれしくなった。 一つは、表面的なテクニカルな話よりも思想、哲学という考え方をベースに置いて話されていたこと、もう一つは物発想よりもお客のライフスタイル、生活をベースに発想し、その後で具体的な形を創り上げていることである。 ある意味、経営というレベルで物事を考えれば、物発想ではなく、あくまでも主体であるお客の生活をベースに発想することが重要であることは当然のような気もするが、様々な物事が業績に大きく左右される小売業(両社とも普通の小売業とは違うとも考えられるが...)ではなかなか簡単にはできないことである。通常の「物売り」とは違うから現在の状況があると言ってもよいだろう。 もう一つ、筆者が感じたのは、お二人とも「語る」ことである。 おそらく、スタッフや多くの人達に自らの思想を伝え、具体的にそれを理解してもらい、現実のものとするために、幾度となく表現を変え、言葉をを変え、言い方を変えて語ってきたのだろう。 心底からというか、身体の芯からというか、身にしみついていたもの、湧き出してくるものを「語る」姿がとても印象的であった。 とてもいいセミナーを聞けたと思っている。
チェーンストアの構造的問題 チェーンストア・グローイング・パラドックス CGP(Chain-store Growing Paradox)
チェーンストア企業が成長し、一定の規模を超えると低迷しはじめ、その後負のスパイラルに陥って最悪の場合破綻する。本来であれば有利であるはずの「規模の拡大」が、返って企業の自由度を奪い、低迷、破綻を引き起こす重要な要因となる。 筆者が様々な業態の企業約200社について、最長30年間に渡る単独売上と営業利益を分析した結果見出したチェーンストアの法則である。(詳細は「何故、チェーンストアは成長を止めるのか?」同友館) チェーンストアのアキレス腱、成長期には気づくことがなかったチェーンストアが内包する構造的矛盾と言ってもよいだろう。 チェーンストアがもつ「損益分岐点が高く、経費が固定費的に発生するという構造的特性」は良い時、悪い時、どちらの場合も極端に働く。成長期には利益を倍加させるテコの原理として働くが、ひとたび売上が低迷すれば、高い損益分岐点ゆえに固定費が重しのようにのしかかり、経営を圧迫する。 チェーンストアは、成長期にこそ、その強みをいかんなく発揮する経営形態であり、マグロが泳ぎ続けないと生きていけないように、どこまでも成長を追い求めていかないと逆のその構造に押しつぶされてしまう。 人口が減少し、マーケットが縮小する時代には「規模」は武器からリスクに変わる。 時代は規模の競争から損益分岐点と生産性の競争へと変わっている。 チェーンストアが拡大の前提を失った時にどのような状況を迎えるのか、特に高齢者が急増する2025年までの10年間、非常に難しい時代を迎えることになるだろう。 できるだけ早いうちに固定費を下げ、生産性を倍化させるような構造転換を図る必要がある。 少なくともこれまでの延長線上で生き残れる企業は限られるだろう。
◆CGPのメカニズム さまざまなデータを総合すると、CGPのメカニズムは、以下のように考えられる。 ①規模拡大に伴う新店効果(業績変化率)の低下 チェーンストアが小規模で店舗数が少ないうちは、新店効果による業績変化率が非常に大きい。売上増⇒利益増⇒再投資(出店)⇒売上増・利益増(新店効果)⇒再投資(出店)⇒...という成長の循環に入りやすく、効果が強調される。 店舗数が増え、企業規模が大きくなると、それと反比例するように出店比率が低下し、業績変化率は小さくなる。 小売業の構造的特性である損益分岐点が高く、固定費比率が高いという利益構造ゆえに、高い売上伸長が維持できなくなると、利益の伸びは急速に停止する。 チェーンストアが戦略目標とする規模の拡大は、同時に成長を鈍化させるマイナス面を併せ持つことになる。 ②商圏の高齢化に伴う消費構造の変化、既存店の競争力低下と業績低迷 既存店の増加に伴い高店齢の店舗が増える。同時に商圏も高齢化して、ライフステージ(年齢、職業、家族構成など)、消費構造なども大きく変わる。 高齢化によって世帯人員、世帯収入は減少する。商圏は縮小(行動半径の縮小)し、客数も減少(外出頻度=来店頻度の低下)して消費量・消費金額は減少する。 消費構造の変化は立地(特に交通手段)や業態(部門構成、商品構成など)の優位性に影響し、出店時のまま店舗を維持することが難しくなる。高店齢の店舗は後から出店した商業施設に対して競争力が弱く、商圏は縮小してシェアも低下する。 ③新規出店の前提となる既存店の業績低迷と出店の減少・停止=成長循環の停止 既存店の競争力は相対的に弱まり、多くの既店舗を抱えた企業は構造的な業績低迷に陥りやすくなる。特に企業規模が大きく、店舗数、人員数が多い場合、立地、業態、店舗規模などが多岐に渡る場合が多く、閉店、改装、業態転換、人員の再教育など、短期間での修正が困難になる。大規模企業の低迷が長引く大きな理由である。 拡大再生産の前提、企業成長の源でもある既存店の業績低迷が始まると、やがて出店は滞り、成長の循環を維持することが難しくなる。 ④ 逆に働くテコの原理、チェーンストアが破綻する負のスパイラル 既存店の業績が低迷し、出店が止まると、弱体化した既存店だけで企業を支えなければならない。このような状況に陥ると「高い損益分岐点、高い固定費比率」という成長期には利益を倍加させ、企業の成長を加速させたテコの原理が逆に働く。固定費の塊である「低迷する既存店」は選択肢を限定し、経営を圧迫する。 赤字店の閉鎖など既存店の整理がはじまると、売上は急激に減少し、負のスパイラルに陥る。 人口ボーナス(人口=働く人が増えて豊かになる)後に必ず訪れる人口オーナス(高齢化して社会が養わなければならない人が増え、重荷になる)同様に、成長期には多くのスケールメリットをもたらした「規模」もやがて強みから弱みへと変わる。 これまであまり注目されることがなかったチェーンストアの負の側面である。 これが、チェーンストアが破綻するCGPのメカニズムであり、多くの企業が規模拡大後に必ずと言ってよいほど経験する負のスパイラルである。 チェーンストアは成長する時も衰退する時も一方通行であり、生き延びるには、どこまでも規模を拡大し続けるしか術を持たない。 半世紀に渡る小売業の歴史を見る限りでは、CGPに陥ることなく拡大し続けることができた企業はほとんど見当たらない。そうであれば、成長するマーケットを求めて海外へシフトすることは、理にかなった選択と言うことができる。 ただし、人口減少、地方の過疎化、急速な高齢化、生産年齢人口の減少、買い物難民、…等々、数多くの難題を抱えながら縮小すると考えられる国内マーケットで、今後どのように企業が存続していけばよいのかという答えは未だ得られていない。 多くの難題に直面する日本には、産業革命以来続く拡大再生産の論理に変わる論理、手法の構築が急務である。 ◆CGPを加速させる環境変化 構造的問題 CGPを加速させる環境変化、構造的問題は複雑かつ多岐にわたる。 ①人口減少、急激な高齢化、中~大規模都市の減少(人口データはいずれも国立社会保障人口問題研究所の資料より、年間商品販売額は商業統計より) 日本の人口は、毎年、地方主要都市に相当する20~30万人ずつ減少している。減少数は、やがて50万人(2018年~)、70万人(2024年~)と増え続け、2041年からの30年間は毎年一つの県に相当する100万人ずつ減少すると推計される。 2010年12800万人の人口は2030年までの20年間に約9%、1140万人減少し、11660万人になる。50歳以上が人口の過半数を占め、平均年齢は51歳を超える。 消費支出をGDP(2010年約480兆円)の約6割として計算すると、人口減少分9%に相当する消費支出の減少額は約26兆円、うち小売業の年間商品販売額(2010年134.7兆円)=物消費の減少分は約12.1兆円になる。この金額は平成25年日本チェーンストア協会の加盟全58社、8,231店舗分の売上12.7兆円にほぼ匹敵する。 人口減少以外にも高齢化(世帯主の年齢が50歳台➡60歳台➡70歳台と上がると消費支出は5万円/月ずつ減る)、単独世帯(2人以上世帯が単独世帯になると消費支出は13万円/月減る)の増加による消費支出の減少分もあるから、その影響は計り知れない。 また、人口減少に伴う市区町村の規模別分布を見ると、2010年から2040年までの30年間に3~100万人規模の市区町村が約140減少し、5千人未満規模の市区町村だけが増える。首都圏、地方を問わず、商業、工業、農業などの中心を成す中~大規模都市の減少によって日本全体の活力は低下する。 すでに都道府県、市区町村という日本を構成する基本単位を維持することは難しくなるだろう。(そのような意味で大阪の都構想は重要な社会実験と考えられたのだが...) ②商業施設の大規模化、オーバーストアに伴う設備生産性の低下 小売業の年間商品販売額は平成9年に147.7兆円でピークを打ち、その後低迷している。しかし、売場面積は増加し続けており、単位面積二人商品販売額=設備生産性は著しく低下している。競争力と生産性を高めることを目的とした商業施設の大型化が、いまでは設備生産性の低下を招き、膨大な固定費が経営を圧迫するように変わっている。 すでに総合スーパーの大量閉店という発表が話題となっているが、今後3~100万人規模の都市が大きく減少すれば大型商業施設の立地は失われ、地域一番店が固定費負担に耐えられずに撤退を余儀なくされるという事態も十分考えられる。 ③インターネットの普及 消費者にとっての買物の意味・仕方の変化 インターネットの普及は、タイムフリー/ロケーションフリー/カテゴリーフリー/コストフリーなど、これまでとは全く異なる状況をつくりだし、小売は特定事業者が行う「業」から誰でも行うことができる「機能」へと変わった。 ショールーミングが議論されるように、買物の利便性、情報量、時間的・場所的制約など多くの点でインターネット通販が大型商業施設の機能を凌いでいる。ウインドウショッピングを含めたさまざまな要素で勝るインターネットショッピングによって実店舗で買物するオケージョンは著しく減少している。 さらにロングテール(Chris Anderson「the Long Tail」2004年10月)で指摘されたように、特殊商品がインターネットに集中すれば、店数分在庫を持たなければならない実店舗は自ずとコモディティ商品を中心とした品揃えと価格競争へ向かうことになる。 グローバル化に伴う価格低下、大量普及は、かつてのスペシャルティ商品をコモディティ化し、マーチャンダイジングの重要な要素は、価格とロジスティックス(必要な時に、必要な商品が、適正価格で、必要な量、お客に提供できる)へと変わっている。 さまざまな面でシステム構築が進む大規模なグローバル企業、店舗を持たないロジスティクス型メガ小売業が、消費者とのインターフェイス、利便性の提供などで有利さを増し、そのことが消費者の購買行動を大きく変える。 ④サービス・ニーズの増加 高齢者世帯、単独世帯の増加に伴い、電球が買えても、一人では換えられない=消費が完結できない世帯が増えている。同様に身体的・物理的・経済的理由から生鮮食品を買えても一人で夕食をつくらない・つくれない世帯、日用品を買えても一人では家事をしない・できない世帯が増加する。 マーケットのニーズは、物の充足によるソリューションから状況改善・状況充足によるソリューションへと大きくシフトしている。 マーケットの成長が見込めない以上、多くの費目をカバーできる「消費を完結させるためのサービス機能」を併せ持つサービス型小売業へと転換する必要がある。 いち早く少量パックの総菜や宅配に乗り出したコンビニエンスストアがある一方で、生鮮食品と低価格にこだわる食品スーパーがある。 サービス付き高齢者住宅の普及、調理をする家庭の減少などを考えれば、物販中心に拡大してきた小売業はビジネスモデル、インフラなどのミスマッチから、急激に衰退する可能性が高い。 団塊の世代が70歳台に入り、年齢構成が最も大きく変わるのが2015~2025年までの10年間である。 地方創生によって地方経済が活性化したとしても、人口減少、高齢化の流れは変わらない。人口減少の仕方、高齢化の仕方、生産年齢人口減少の仕方など様々な推計値から読み取れるのは、中~大規模の地方主要都市を中心にして難しい局面を迎える可能性が高いということである。
GMS 総合スーパーはどこへ行くのか?
ユニーグループ・ホールディングスに続いてイトーヨーカ堂も大幅な店舗の整理を打ち出したが、イオン(ダイエー、マイカル)、西友までを含めれば、すでに相当数の店舗が閉鎖、もしくは撤退し、別業態へと転換している。 問題は、総合スーパーという業態なのか、それとも商圏変化なのか、あるいは業態と商圏のミスマッチなのか、....といった本質的な議論はあまり表面には出てきていないことだろう。 単純に総合スーパーの業績が回復しないから、もうダメだという論調が多いが、なぜ総合スーパーではダメなのという議論はあまりない。 面白いのは、これらの企業が総合スーパーを縮小し、食品スーパーやコンビニエンスストアへ比重を移す一方で、ライフコーポレーションのように食品スーパーから商品ラインを増やし、衣食住のフルライン化を図る企業が業績を伸ばしていることである。ホームセンターも食品を導入し、今では肌着や軽衣料など衣料品を取り込む動きが活発である。 商圏が限られ、競争が激しくなれば、多くの費目を取り入れるために総合化する。またワンストップショッピングを可能にすることで消費者に利便性を提供するという意味でも、商品ラインを増やし、総合化を図ることはいたって自然な流れである。成り立ちから言っても、何十年か昔のGMS総合スーパーに回帰するような動きが全く別のところで起こっていることになる。 何年か前に総合スーパー再生について調べたことがあるが、大きくなりすぎた総合スーパーは、その固定費を賄うためにも多くの売上をとらなければならず、そのため商圏を広くとり、高額品も売らないといけないなど、様々な点で状況を難しくさせている。 それに対し、はるか昔の1000~2000坪クラスのGMS 総合スーパーのような形態をとるコモディティ型店舗(食品スーパーから進化)は、消費者に利便性を提供するためにワンストップショッピング化を図っていき、結果的に衣食住のフルラインに行きついたという形だから、商圏における店舗の意味が全く違っている。バブル期の進化ではなく、現状のニーズに対応した進化である。 高齢化が進み、移動手段を持たない高齢者が増えれば商圏は縮小し、利便性の高い万屋的店舗のニーズが高まる。拡大し、大型化、高級化、プチ百貨店化した時代は消費の中心にいた人たちも若く、バブリーで、マーケットの成長とともに店舗に対する要求も、より細分化・専門化・高級化したものであったが、それが高齢化に伴って実生活に必要な分野に収束してきたと考えれば分かりやすいだろう。 ポイントは時代の志向に適した立地・規模・店舗性格なのだろう。拡大し、高級化していった時は、都心から郊外までみな同じ流れの中にあったから、地方都市の総合スーパーでも高級化路線でよかったが、いまは年齢による行動範囲の違いから都心と郊外・地方都市とでは消費者の求めるもの、店舗の使い方が異なっている。鉄道の乗り入れなど時間敵距離の短縮から中途半端に郊外・地方都市で買わなくてもすぐに本物がある都心に行くことができる。 歴史的、構造的な変遷を見直してみると、総合スーパーが整理される理由も何となく分かってくるが、それと同時に総合スーパーに対する戦略的な間違いも分かってくる。 問題は、それだけの店がなくなった後、その地域がどうなるかだろう。地方の地価は上がるところと下がり続けるところで二極化しているというから、雇用を含め、難しい局面を迎える地域が増えることになる。 単純に単店の採算だけで判断するのではなく、ある程度広域を見た上で、ターミナルとして地域の中核になるエリア、日常的に比較的高頻度な買い物をするエリアなど、その地域の特性に応じてタイプの異なる店舗を再配置するという発想で見直す必要があるだろう。(個々の企業だけでなく、都市計画的な発想が必要だろう)
チェーンストア、小売関連企業は2025年までの10年間に何をどう対処すればよいのか⁉
2020年東京オリンピックが終わり、宴の後とも言える2025年までの10年の間に起こる出来事を整理すると次のようになる。 ①2025年には団塊の世代約500万人全てが75歳(健康寿命)を超える。 ②日本の人口は2015年より約600万人減って12060万人になる。 ③生産年齢人口も2015年より約600万人減って7080万人になる。 ④日本人の平均年齢は49.5歳、65歳以上人口は3660万人、30.3%となる。 ⑤世帯主が65歳以上の世帯は2015年より約130万世帯増えて2015万世帯、そのうち独世帯は約100万世帯増えて700万世帯となる。 ⑥世帯主が75歳以上の世帯(再掲)は2015年よりも約300万世帯増えて1190万世帯、そのうち単独世帯は約120万世帯増えて450万世帯となる。 ⑦2025年、女性の単独世帯に占める65歳以上の割合は50.9%となり、単独世帯は高齢者女性の代名詞となる。(男性は24.4%で女性の半分) ⑧市区町村を規模別にみると、2010年に対し2025年には1~100万人規模の市区町村が73減少し、5千~1万人が5、5千人未満が68増える。大きく減るのは5~10万人35、10~30万人14、3~5万人12であり、地方で産業を支える中~大規模の主要都市が大きく減少する。小売業の主要な立地も10年間に大きく減少する。 何をどう準備すればよいのか? 別項でCGP(チェーンストア・グローイング・パラドックス)というチェーンストアの法則について触れているが(*詳細は「何故、チェーンストアは成長を止めるのか?」同友館)、チェーンストアは成長期に向いた経営システムであり、売上低迷に対しては、これといった方策を持ち合わせていない。しかも、失われた20年の間にギリギリまで無理をしてコストを下げてきたので、これ以上、現在のビジネスモデルのままでコストを下げることは難しい。 インバウンド消費で一息入れている企業も多いが、インバウンド景気に浮かれて「のど元過ぎれば...」という悪しき体質が顔をのぞかせては、抜本的な対策を後回しにするだけという結果になりかねない。 ユトリのあるうちに、固定費を減らし、損益分岐点が低く生産性の高い(多くの付加価値を生み出す)ビジネスモデルに切り替える必要がある。 そのためには ①単に物を売って差益をとるだけの商売をやめ、6次産業化を図る、物販周辺のサービスを取り込むなど、収益を上げる間口を大きく広げる。 ②店舗のように物理的に商圏=マーケットサイズが限定されるビジネスから幅を広げ、ネット通販、ルートセールス、卸売り、ファブレス(工場を持たない製造業)など、一取引の額が大きく、商圏の制約を受けないようなビジネスモデルへ転換を図る(あるいは従来の小売とミックスする)。 ③マーケットが縮小し、労働力の確保が難しくなれば、物理的に商品を扱うにはICTや自動化・ロボット化は絶対条件になる。セブン&アイHLDGS.のネットスーパー専用店舗のような自動物流倉庫型店舗や、かつて西友がつくったメカトロ店舗、IBM/メトロのフューチャーストア、あるいはコンビニエンスストアをさらにハイテク武装したAmazon Goのような店舗やサテライト店舗(宅配用デポ兼用)など、従来とは全く思想が異なる物流、デジタル技術などをベースに発想した業態開発が重要になる。 これまで小売業が鮮度や接客を中心としたサービスのために、なかなか実現することができなかった労働装備率のアップが、生き残るために一気に進むことになれば、従来の常識、我々の想像をはるかに超えた、全く新しい商品流通の時代が始まることになるだろう。
GMS衣料品の構造的問題点 同じ構造のショッピングセンター
GMS衣料品の苦戦が続いている。数値を示し、ユニクロやしまむらの成長と入れ替わるようにして停滞が始まったという指摘もあるが、それほど単純とも思えない。 歴史的に見ると、GMSでは紳士、婦人を問わず、ヤングカジュアル系の商品が伸び始めた際、それらの商品を平場から抜いてインショップ化し、後に事業部、別会社へと切り替えていった。 その結果、衣料品売場にはシニア商品、ミセス商品などファッション、流行とは縁遠い実用衣料だけが残された。この点では百貨店の平場に単品商品が残ったのと経緯が似ている。 バブル時代になるとGMSは大型化、高級化、プチ百貨店化したのに伴って衣料品売場を大きく広げている。売場が百貨店や専門店に見られるようなショップ形式に変わると、品揃えの思想とオペレーションは、かつての単品量販型から多品種少量型に変わる。デザイン商品、スポット的な扱いの商品の比率が高まり、ベーシック商品を中心とした定番商品の取り扱いは減る。 「ファッション」という言葉の意味するものが、ブランド商品や高額品、あるいはデザイン性の高い商品、デコラティブ(装飾性の高い)な商品というとらえ方が定着したのが、この時期と考えてよいだろう。売場に映えないシンプルでベーシックな商品は低価格帯、特売などに位置づけられ、軽視される。 ただし、多くの消費者に訊いて分かることは、数多く持っている衣料は圧倒的にシンプルでベーシックなアイテムが中心であるから、GMSが消費者の志向と違う方向に進みだしたのは、この時期からと考えてよいだろう。 ◆品種売場とアイテム売場 専門店、ブティックなどに多く見られるコーディネイトを指向した商業型の売場を「アイテム売場」と呼ぶことにする。 商品構成は全体のバランス、商品回転率、在庫リスクなどを考慮したアソート(色・サイズをチョイスした品揃え)であり、在庫をフルカラー、フルサイズで持つことはない。商品の豊富感は色・サイズではなく、アイテム(デザイン)数によって表現されるからアイテム数の割にSKU数は少ない。 いろいろな商品があるように見えても、このデザインのこの色、このサイズという要望に応えることはできない。品揃えされていない在庫を接客でカバーしながら販売できる専門店に向いており、広いセルフ販売の売場には向かない。GMSのフロア構成の中でアクセントとなるようなインショップ向きである。 一方、「品種売場」は品種を構成するアイテム(デザイン)数は多くないが、1アイテム当りの色数×サイズ数、品種を構成する総SKU数の多さで豊富感を演出する。1アイテム当りのSKU数、1SKU当りの売場在庫数が多く、典型的な単品量販型の売場づくり(ユニクロに象徴される売場)に向く。 量感を演出するには、高い陳列線と色の面によって構成される売場が有効である。細々として複雑に入り組んだ色・形の陳列がインショップのアイテム売場向きであるのに対し、売場規模、陳列規模とも大きく、遠くからも視認しやすい。VMD、カラーコントロールと呼ぶのに相応しい演出が可能になる。 基本的にセルフ販売で単品量販をするための工業型の売場であり、欠品を避けるためにフェイス管理を強化し、在庫数もSKUごとに算出して持つようにする。 アイテム数が少ないために基本的なデザインを重視し、シンプルでベーシックな商品が中心になる。それだけに色数×サイズ数の持つ意味が重要になる。売場づくり、売場管理ばかりでなく、商品の原材料調達、製造工程、生産計画にとっても重要な意味を持つ。SPA企業にとっては、生命線とも言える最も基本的部分の設計である。 原型は昭和50年代に新宿伊勢丹が入口につくった36色のニットコーナーとも考えられるが、売場面積、客数、販売点数、販売金額とも、かつての専門店とは比べ物にならないほど大きくなった現在に適した形態と考えられる。合理的に理詰めで考えた結果、行き着いた形とも考えられる。 ◆GMSの品揃え、売場づくりと経営スタイル、オペレーションの矛盾 GMSは経営スタイル、オペレーションが向かう方向とは全く逆の品揃え、売場づくりをしたことで自ら難しい状況に陥っていると言ってもよいだろう。売場から人を排除し、ローコストでオペレーションをするのであれば、セルフに向いた工業型の単品量販型売場=ユニクロのような品種売場が向く。 一方、専門店やブティックのように、多くの商品を持たず、適度にSKUを配置して接客販売しようとするのであればアイテム売場の方がよい。このような売場特性から考えると、アイテム売場で規模を拡大するにはアイテム数を増やす必要があり、管理はかなり複雑になる。人を減らし、セルフでするには明らかに向かない形態である。 以上のような理解をした上で、両方の良いところを上手くミックスし、ビジネスモデルとして創り上げたのがH&Mなどに代表されるファストファッションということなのかもしれない。 GMSはバブル時代の名残で、住関連売場や食品売場では代わりに埋めることができないほどの非常に広い衣料品売場とその実績数値が残ってしまった。ベーシックアイテムの単品量販型売場ですべてを埋めることができないために、専門店やブティックがやるような商業型のアイテム売場を多用してスペースを埋めているところに無理がある。 多くのスペースを埋めるには、多くのアイテムが必要になるからバイイングや維持管理の手間がかかり、商品回転率や粗利(特に値下)のコントロールも難しくなる。一方、運営はローコストの工業型、セルフ販売型で対応するから品揃え、売場づくりとオペレーション、管理形態の間にミスマッチが生じる。 歯抜け状態の売場(アソートだから品揃えしたはじめの時点ですでに欠品状態)で接客人員がいなければ、チャンスロスは増え、欲しくても買えなければお客のストレスも増す。 アソートでの商品販売には発注と在庫処理の技術が必要になる。少ない人員ではチャンスロスと値下ロスが増え、効率はなかなか上がらない。それでも坪売上、坪粗利を上げようとすればアイテム数を多く投入せざるを得ないから、さらに難しい状況に陥ることになる。 ネライが効率なのか、売上なのか、利益なのか、残ってしまった広い売場への対処なのか、..。どこかで決断する必要がある。 ◆GMS衣料品の構造的問題と同じ構造にあるショッピングセンター GMSの問題構造は、衣料品偏重の広げ過ぎた売場に対処できないことがすべてと言ってもよいだろう。売場を一気に縮めることも、品揃えをベーシックアイテムに絞り込むこともできないために20年以上もこの状況から抜け出すことができずにいる。 日本チェーンストア協会の長期統計を見ても、衣料品は1994年3,646,088百万円、2004年1,878,282百万円、2014年1,221,409百万円とほぼ3分の一まで減少しているが、店舗面積は拡大しているから、スペース効率は確実に低下している。 GMSの中には、フロアごとテナントに入れ替えるような大手術をしている店も見られるが、まだほんの一部である。いろいろな修正案も試されているが、商圏が限られるコモディティ型立地では、人口減少・高齢化の影響もあり、限界がある。 このGMSと同じ問題構造にあるのが、アパレル専門店中心に構成されるショッピングセンターである。 広げ過ぎた売場、類似するテナント構成、人口減少・高齢化による衣料品支出の減少、テナントを入れ替えるにもその広い面積を埋めるだけの代わりが見つからないという状況は、バブル崩壊後のGMSが歩んできた道とどこか似ている。 ホームセンター、家電量販店、インバウンドを意識した大型免税店、アミューズメント、テーマパーク、各種サービスなど、いずれも立地との兼ね合いから現在の集客力、販売効率を実現することは難しい。 このままいけば、GMSと同じ結果がショッピングセンターを待ち受けていると考えてよいだろう。 大型ショッピングセンターが数多く展開する横浜市都筑区の港北ニュータウンと周辺5区(横浜市港北区・青葉区・緑区、川崎市中原区・高津区)の推計人口を分析してみると、人口が減らないが、高齢化は全国でもトップクラスの増え方で急速に進む。ターミナルは少子高齢化によって定期乗車券による通勤・通学客減少の影響を受けるようになるだろう。 いずれにせよ、広い売場面積とそれを維持するために必要となる固定費がいずれネックになる時が必ず来ると考えるべきである。 リアル店舗がすぐになくなるとは思わないが、従来の発想、方法論の延長線上に答えがあるとも思えない。 いま、本当に必要なのは、クリエイター、プロデューサー、ディレクター、エンジニアなど従来の小売、物販の発想を超えられる人達である。バブル期のアクロスのような文化論、消費者論が、今風に進化して蘇ることが望まれる。 IoT、ICT、AI、ロボットなど、さまざまなデジタル技術と実店舗を結び付けることができるクリエイティブなエンジニア、全体をデザインすることができるクリエイター、現実のものとして組み上げるプロデューサーやディレクター達が旧態依然とした物売り型小売業を根底から否定して全く新しい思想、ライフスタイル、カルチャーを創造するしか再生の道はないのかも知れない。
商圏縮小、商圏密度低下、従業員不足 その時どうする?
急激な高齢化と人口減少によって、消費がタイトになることは誰が考えてもすぐ分かる。しかし、そのことばかりに目が行き過ぎると、人口減少、少子化に伴って生産年齢人口=働き手も毎年100万人ずつ減少していくという事実を見落としてしまう。 日本の地域別将来推計人口 平成25年3月推計(国立社会保障・人口問題研究所)のデータを基にして、いろいろな角度から調べてみた結果、次のようなことが分かった。 ①人口の減り方は、現在の人口規模とは関係なく起こる。大都市も小都市も、現在の人口規模に関係なく、人口が増える都市も減る都市もある。中小都市を中心に「消滅可能性都市」と考えると間違える。減少率が一定であれば、人口規模の大きい都市の方が減少する人数は多く、様々な点で影響は大きくなる。 ②人口減少に大きく影響するのは「2015年時点の総人口に占める65歳以上人口の割合」である。この値が20%代前半まで(20%以下では人口が増加する都市が多い)とそれ以降、30%以上では、その後の人口減少の仕方は大きく変わる。 ③2015年から2025年までの10年間が最も高齢者が増加する速度が速い。 ④2015年の生産年齢人口指数(2010年=100)が小さい都市(生産年齢人口の減少速度が速い)は都市の人口規模と関係なく、2025年時点の同指数も大きく減少する。*たとえ人口1万人の都市でも増える都市はあるが、50万人以上の都市でも減る都市は減る。 ⑤2025年時点の生産年齢人口指数(2010年=100)に大きく影響を与えるのは、「2015年時点の総人口に占める65歳以上人口の割合≒人口減少の大小」である。 すでに一部では人の確保ができずに企業存続すら危ぶまれるような状況も生まれているが、前述のことから今後5年~10年後の状況を考えると、業種・業態・職種などによっては極端に人件費が高騰し、それでも人手が確保できないという状況が考えられる。 仮に労働力が80%になった場合、現在の生産性を維持するには、生産性を125%以上にする必要があり、さらに人件費が10%上がると、125%×1.1=137.5%以上にまで引き上げる必要がある。現在のビジネスモデルのままで実現するには現実離れした数値というしかない。 セブン&アイ ネットスーパー西日暮里店は約600mのベルトコンベアを持つというが、すでに店舗というよりは自動物流倉庫といった方がよいつくりだろう。かつて西友が能見台につくったメカトロ店舗、あるいはメトロのフューチャーストアといった形態が、いよいよ現実のものとなる時代になったと考えてよいだろう。 商品を一つ一つ人手でハンドリングしている限り生産性は上がらないから、庫内物流(店舗内での物の動かし方)を含めた物流を如何に自動化するかが重要になる。 課題は倉庫のような無機質な空間を感じさせず、如何に消費者に小売するかであり、今後人型ロボットの活用など様々な工夫がなされるだろう。 課題は資本力だろう。莫大な設備投資をして自動化できる企業とできない企業が出てくることは確実である。 ただし、その違いだけで存続できる企業が決まってしまうのもつまらない。 資本力がない企業は「知恵」を出し、ブランドの確立、新規ビジネスモデルの開発などによって投資を呼び込むしかない。 人口動態から見ると、状況が大きく変化するのは2015年~2025年までの10年間、様々な影響が出てくるのは、そこから少し遅れて2035年くらいまでと考えている。 その間、人口減少が極端な都市は消滅、あるいは吸収され、人口が大きく減らない都市は急激に高齢化が進んだ後人口が大きく減少する。 おそらく2040年以降には年齢構成も落ち着いてくると考えられるが、人口推計では2018年頃には年間の人口減少が50万人を超え、2024年に70万人、そして2041年から30年以上に渡り毎年100万人以上が減少するとされている。 各企業が、どんな準備をするのか・できるのか定かではないが、少なくとも今年の新入社員が無事定年を迎えられるよう、その時点から逆算して準備をする必要があるだろう。
成長曲線(ロジスティック曲線やゴンペルッ曲線など)をはじめとした売れ方の法則など小売業の法則を見つけよう。
これまで小売業を経験してきて、最もすごいと思ったことは、理屈から言えば明らかに間違っていると思えることでも、徹底してやり通してしまうと現状よりもよい結果が得られることが多いということである。 勝てば官軍という言葉があるように、全ては結果次第であるから、さまざまな考え方、さまざまな方法が成立していてもおかしくはない。例え、それが「たまたまの結果」だとしても、結果さえ伴えば、それが正しいことと理解することは否定できない。 例えば、多くの小売業が、商品が売れないとすぐに商品の価格を下げて販売しようとする。中には、仕入原価を割り込んで赤字になるような価格をつけて販売することも当たり前のように行われる。 しかし、筆者が学生の時にアルバイトで経験したことは全く逆である。輸入品のインテリア雑貨を扱う卸売業であるが、催事用の商品が足りなくなると百貨店に置いてある商品を引き下げてきて催事に回す。19,800円で売れ残っていた象嵌のワゴンに39,800円の値札をつけて催事場に並べると、その場で商品が飛ぶようにして売れてしまう。1本100円でも売れない七宝焼きのスプーンを、ビロード張りのハードケースに入れて見栄えをよくした途端、5本セット5,000円でも売れていってしまう。バブル時代には、別に珍しいことではなかったはずである。 輸入品の原価と売価の関係を知る人が見れば、常識的な値付けかも知れないが、知らない人が聞いたらビックリするような価格設定である。そのような価格設定の商品を喜んで買うお客がいるし、そのような商売もあるから、何でも同じ理屈で説明しようとすると無理がある。
問題は、その結果に至ったシチュエーション、商品の特性、お客の購買心理、…等々、その結果に到達したさまざまな条件を無視して「商品は安くすれば売れる」「商品は高くした方が売れる」といった結論だけが独り歩きすることである。しかも、さまざまな条件の組合せによって、たまたま起こった一つの結果が、あたかも全ての事柄に当てはまる唯一絶対の真理のように理解するからアチコチでおかしなことが起こってしまう。 たまたま起こったある一つの結果に対して、前提となる全ての条件を無視して、結果だけをあらゆる事柄に当てはめようとすることは無謀である。 いまから10年以上前になるが、ユニクロのフリースが異常に売れたことがある。当時、まだ小学生だった子供のクラスでは4人に一人がユニクロのフリースを着ているという話を聞いた覚えがある。 その時、ユニクロのフリースが売れた理由は「みんながユニクロのフリースを着ているから」であったが、その後しばらくしてフリースが売れなくなった際の理由も「みんながユニクロのフリースを着ているから」であった。 全く同じ理由で真逆の結果が出ることは、小売業を長年経験していれば、よくあることである。所詮、お客は気まぐれだし、過熱すれば飽きもくるから、人間の心理はなかなかとらえきれない。これが長年さまざまな法則を研究することなく、放置してきた理由だろう。このようなことは日常的に起こるし、商品もスタッフも年中入れ替わるから、いちいち細かなことまで気にしてはいられない、というのが小売業の体質なのかも知れない。 しかし、見方によっては、このような状況も「全く違ったもの」としてとらえることができたかも知れない。 例えば、生体の個体数の増加や新製品の販売数、普及状況などを見る成長曲線というものがある。はじめは緩やかに成長し、一定の値を超えると急激に上昇し、飽和点に近付くと、また増加が緩やかになってS字のようなカーブを描く。 新しく市場に普及し始めた家電製品などの普及状況を説明する際によく使われる。一定の普及率(例えば25%)までは緩やかに成長し、それを超えると急速に普及率が上がる。そしてまた90%を超えてくるとその先はなかなか普及率が上がらなくなって横這いに近くなるのでS字のようなカーブになる。 ユニクロのフリースもそのような法則に従って成長曲線を描いたと考えれば、客観的に理解することができたかも知れない。そうしないと、同じ状況、同じ理由で180度異なる結果が出るのが小売というもので、お客は気紛れだからしょうがない、という一言で物事全てが済んでしまう。いつまで経っても科学的な視点に立って物事を論じることができなくなる。 いろいろな企業で、いろいろな売場を見る機会がある。売場で問題意識を持ち、少しでも自分の周りを良くしようとしている人達は、いろいろなところで、実にさまざまな工夫をしている。 周りの状況を細かく観察し、いろいろな仮説を立てては実験を繰り返し、自分なりに法則を見出そうとしている。漠然と問題意識をもっているが、どうしてよいかわからずに悶々としている人達は、考え方や方法など、ちょっとしたヒントを与えただけで見違えるように大変身する。 以前、取材で山形に行った際、出会った食品スーパーの店長は、バイヤー経験もあり、商品についていろいろなことを教えてくれた。昔の食品スーパーではよく見られた、職人肌の、まさにスーパー店長である。 競合他社の総菜を買ってきては、それを細かくバラして素材別に重量を量り、自社の惣菜と比較して改善するという、まさに職人技ともいえる競合対策のやり方には、ただただ感心させられた。青果ではいろいろな価格で売ってみた結果、1点78円という価格が数量、売上金額とも一番とれる価格だとも教えてくれた。そこに行き着くまでに、10円刻みで何回も特売を打って試したからこそ言える内容である。 筆者も青果商品の時間帯別売上から売れ方のパターンを調べたことがある。午前中の販売数量と昼から閉店までの販売数量の関係を見ると、午前中に全く売れなかった商品はその後もほとんど売れなかった。午前中によく売れた商品の中にも、午後の売れ方が、午前中の2倍の商品、3倍の商品というようにいくつかのパターンがあることも分かった。 午前中の販売実績を基準にして一日の販売数量を予測することができれば、ムダな加工をする必要もないし、つくり過ぎてロスを出すこともなくなる。 このように見ていくと、小売業には、チェーンストアの経営に影響を与えるような大きな観点での法則から、品出しが早く済むコツというような日常的な作業レベルまで、さまざまなレベルで原理原則、法則があることが分かる。 これらの原理原則、法則を多くの人達の財産として小売業が蓄積し、定着させていけば、ムダな試行錯誤が省け、生産性もはるかに高まることだろう。 いろいろと難しい状況に直面しているからこそ、このような原理原則、法則を改めて確認し、より確率の高い方法を取り入れていくことが重要である。
住居・余暇関連 新たなマーケット開発
人口減少・高齢化は、消費構造を大きく変える。 高齢者夫婦のみ世帯・高齢者単身世帯の増加は、電球は買えても独りでは換えられない世帯、食材は買えても調理しない世帯、洗剤は買えても家事をしない世帯など、消費サイクルを独りで完結できない世帯の増加を意味する。このようなマーケットニーズの変化は、単なる物売り業を排除し、サービス型小売業、あるいは小売機能付きサービス業の需要を高める。 かつてホームセンターのカー用品売場からピット併設型のカー用品専門店へマーケットが大きくシフトしたことがある。必要な商品を買い集め、自分で洗車やワイパー交換、オイル交換までやっていた人達は減少し、クルマのケアはディーラー、ガソリンスタンド、ピット併設のカー用品専門店に全て任せるというように消費の仕方が変化した。 いま、それと同じ変化が生活の様々な場面で起きようとしている。 例えば、高齢化に伴いサービス付き高齢者住宅に移り住む人が増えると、そこで食事や身の回りのサービスを受けるように変わる。個々の消費者が様々な商品を直接小売店から買う必要がなくなると、それまで買っていた多くの消費財はサービス付き高齢者住宅を運営する企業が生産財として別のチャネルから仕入れるように変わる。 商圏人口が変わらなくても小売マーケットが縮小する構造的変化である。 カー用品がホームセンターからカーピットへ移ったことを考えれば、住関連の新たなマーケットは、家事周辺分野をサービスとして提供するビジネスへシフトすると考えるのが普通だろう。 実用的な生活関連商品が一部でもサービスマーケット―シフトすれば、影響を受ける業態、店舗は多い。 その時には、QOL(Quality of Life)を高めるような住環境、生活環境を高めるような新たなマーケットを開拓するしかない。健康や余暇関連分野は、その一環として位置づけられ、マーケットの深耕が盛んに行われるだろう。 立地によっては、インバウンド関連の商品・サービスも考えられるが、すでにリピーターは典型的な観光地での観光(大量・爆買い)から、地方の日常的な生活に触れることができる体験型(地方固有)へとシフトしている。 新たにKitchHike(https://ja.kitchhike.com/)のようなビジネスモデルが出てきたことを考えても、マスコミベースの観光からミニコミ、あるいはSNSベースの「私だけの...」「ここだけの...」といった情報がつくり出すマッチング、固有の体験が新しいビジネスのキーワードになっていくだろう。 ある意味、趣味の商品分野が消費者の習熟によって変遷していくのと同じような変化をすると考えられる。 アクアリウム、ガーデニングなど「限られた人のマニアックな趣味=狭く深く」➡「一般に広がりマス化=広く浅く」➡「習熟し、細分化・専門化して個々の分野は小さく分化(広く浅く➡狭く深く)」という変化の仕方である。 マーケットを読み違えると、後々修正することは難しくなる。 確かなことは、従来のように「大量販売=大型店、大量在庫、大量販売...」で成り立つケースは確実に減ってくるということだろう。損益分岐点を下げ、小さな収益を確実に積み上げるか、原価率の極端に低いビジネスを確実に積み上げるようにするしかない。
食品 新たなマーケット開発
今後、食のマーケットがどう変化するのかは、重要なテーマである。 考えられるポイントは、大きく分けて3つである。 ①農業を中心とした第一次産業の6次産業化推進によって、食品スーパーから直売所、道の駅などへ生鮮食品の販売チャネルのシェアシフトが起こる。 ②高齢者夫婦・高齢者単身世帯、非婚者の単身世帯の増加、あるいはサービス付き高齢者住宅への住み替えなどによって、食材を買って自宅で調理をする世帯は減少する。 生鮮食品からレトルト食品・惣菜などへの移行、弁当の宅配、サービスとして食事の提供を受ける世帯の増加が起こることで、食品販売チャネルや消費財から生産財へのシフトなどが起こる。 ③Kitchike(https://ja.kitchhike.com/)のような外国人観光客、あるいは国内在住の外国人家庭と日本人家庭の日常的な食事のマッチングサイトが生まれたことを考えると、食の世界がグローバル化し、新たな出会い・交流の「場」として新しく意味を持ち始めている。食材、調理法、レシピといった「物」だけで完結し、成り立っていた食の世界が、人が時間・経験を共有する「交流の場」に変わる意味は大きい。 レストランの食事ではなく、従来とは全く視点を変えて、世界の家庭料理が見直される可能性もある。その時には、食材、調味料、調理器具などの他、文化としての食にまつわる様々なマーケットが新たに生まれる可能性が高い。 このような変化を考えると、従来の食品スーパーは、人口減少・高齢化による商圏の縮小・商圏密度の低下、食に関する意味・チャネルの多様化によるシェア低下など難しい局面を迎える可能性が高い。特に食品スーパーのアイデンティティとも言える生鮮食品は、初期投資、運用コストともに高いので、調理をしない世帯の増加、専門性の高い海外の食材・調味料など従来とは全く異なるニーズが高まった場合にはアキレス腱となる可能性が高い。 高齢者世帯、単身世帯が増えることを考えると、単に腹を満たす、栄養を摂取するという物理的な意味の食事とは別に、「食」を通して参加・体験・交流など、よい時間を創りだし共有するといった「メンタルを満たす」マーケットの重要性が増すだろう。