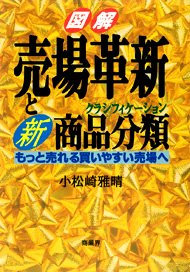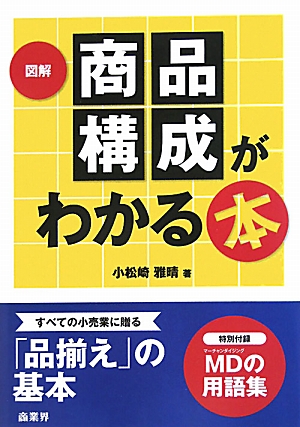もう、40年以上も前の話である。大学2年の時に行った工場見学で生産管理部長である真鍋さんが次のような話をしてくれた。
「カラスが泣いて西の空へ飛んでいく」この文章を読んで君たちはどう思うかね?
皆は何を言われているのかよくわからずに黙って聞いていた。真鍋さんは続けて、もし、これが文学部の学生だったら、子が待つ巣に帰るのだろうとか、夕焼けの中をカラスが飛んでいく情景を様々な思いを巡らせながら延々と綴っていくだろう。しかし、君たちは工学部の学生だから、事実を「定性と定量」で整理して話さないといけない。
カラスは嘴太ガラス1羽、飛んでいる高さは地上から20m、飛んでいる方角は西南西 西22°30‘南、羽ばたきは30回/分、…、という具合である。
ある意味、この話が筆者の重要な原点となっている。「定性と定量」…定量は物理、あるいは化学など何らかの単位が付いた数値、定性はそれらの数値が何を意味しているかを説明したものである。よく「数値で物事をとらえなさい」というのがこのことである。
面白いのは、数値で物事をとらえても、本質を理解していないとかえって間違いが大きくなることである。例えば、カラスが飛んでいる高さ20mが高いか低いかと学生に質問すると、それぞれが判断して高いとか低いとか言い始める。しかし、カラスが飛ぶ高さに関する客観的な判断基準を持たずに、それぞれが勝手に判断するのでは、例え20mという高さが事実であり、正確に測定した正しい数値だとしても、そこから先は間違いということになる。客観的な判断基準=根拠なくして、数値を盾に自分の感覚だけで物事を判断、主張するのは本来の姿とは大きくかけ離れている。
「事実なのか、それとも自分で勝手に判断したことなのか、どちらなのか…」芝浦工大の恩師である津村豊治氏から学生の時に繰り返し何度も教わった重要な視点である。
たしか「統計でウソをつく法」という本があったが、数字を盾にした主張は意図してやればウソで他人を騙すことになるし、知らずにやれば、信じきっているだけに多くの人を間違った方向に導き、大きな混乱を生じさせることにもなりかねない。
定性と定量で事実をつかむことは重要であるが、あくまでも事実を把握するまでであって、その先にある判断とはまた別物である。
このようにして把握した数値もバラバラで見ていると分かりにくいから、それらを関連付け、全体の関係を整理するには「図表化」という手順が有効である。絵を描いて整理すること物事の状況を把握する上で重要な技術である。
また、「科学」という言葉を広辞苑で引くと、「科学とは、現実の全体、或はその特殊な領域、または諸側面に関する系統的認識」とある。これを「現実=事実を正しく知る」「系統的認識=事実の相互関係から仕組みや法則性を見出す」と言い換えると、事実を正しく知るには定性と定量が必要であり、事実の相互関係から仕組みや法則性を見出すには、図表化したり、グルーピングとモデル化という手順によって類似する特性の要素をまとめることが必要になる。
類似する特性の要素をまとめるには、分類=クラシフィケーション(Classification)概念が重要になるから、これらの一連の要素が科学的な方法の基本ということになる。
このようにカラスの話から学べることは多い。
真理は単純で分かりやすく、しかも普遍的であるが、どうも世の中難しいことが高度であり、単純なことはレベルが低いという勘違いがある。多くの人材を育て、進化をするためにもどうにかしたいものである。
Archive for wpmaster
カラスの話
manage うまくやる どうにかする
日本人は「管理」が好きである。何にでも管理をつけようとする。売上管理、在庫管理、生産管理、販売管理、労務管理、…。ただし、やっている人達によくよく聞いてみると、ただ細かな数値をたくさん並べて眺めてるだけというケースも少なくない。必要なくてもコンピュータから数値がたくさん出てくる時代だから仕方ないのかもしれない。
管理と類似する言葉にマネジメント(management)という言葉がある。なぜか日本語では古くから経営管理と訳されている。本来、経営と管理は異なる概念だと思うのだが、なぜか昔からそういうことになっている。
managementの動詞形 manageの語源には「手で扱う,馬をならす」という意味があり、そこから転じて〔…なしで〕うまくやる,どうにかする、なんとか間に合わせる、という意味になっている。
いまでは、管理のサイクル Plan-Do-Check-Action、マネジメント・サイクル Plan-Do-Seeなどが当り前になっているが、手続き論ばかりが幅を利かせると、計画だけでも何十枚、何百枚もの書類が必要になる。それはそれで重要なことであるから否定はしないが、たまには「どうにかする」「うまくやる」といった単純なmanagementがあってもいいだろう。何事も程度問題。適度にやるのが一番である。
ホメオスタシス Homeostasis 恒常性の維持に学ぶ
寒いと身体を震わせて体温を上げようとする、暑ければ汗をかいて体温を下げとようとする、病原菌が入れば発熱によって体温を上げ、病原菌(熱に弱い)に対して抵抗する、ケガをして出血すれば瘡蓋をつくり傷口が治るまで保護しながら修復する。
生体には身体を一定状態=安定した恒常的状態に保とうとする仕組みが備わっており、一定状態から逸脱しそうになれば元の状態に戻そうとする仕組みが自動的に働く。恒常性の維持=ホメオスタシス(Homeostasis)である。
面白いことに、小さな動物、生まれたばかりの小さな子供でもこのような機能を備え持つのに、その人達が集合し、高度な知識・技術・経験を駆使しても組織の中にこのような機能を確立することはほぼ不可能に近い。
一つの理想形、完成されたプロトタイプが目の前にあるにもかかわらず、残念なことにそれを研究しているのは生物学の世界であって、社会科学の世界はまた違ったアプローチをとっている。実践の場である社会・組織では全くそのような発想すら持ちえていない。
さまざまなモノ・コトの境界線が消失し、総合・複合・融合することで新しいモノを創り出すことが可能になった時代、あるいは創り出すことが必要になった時代である。
進化するためには、思想、価値観、論理など行動の原点にある基準の抜本的な改革、転換が必要になる。見える人には見えても、見ようとしない、あるいは意識するか否かは別にして全く見ることができない人には、全く気の付くことのない見えない世界がある。
特に大きく変化する時代には、相互に異星人と思えるくらい見えるモノが違ってしまういくつかのグループに分かれるのだろう。徐々にある方向に収束するのだろうが、それでも変われない、変わらない人達がいる。問題はどのような人達が大きく影響を与えるかである。大阪都構想、イギリスEU離脱,いまを見るか、将来を見るかで結果は大きく変わる。
ホメオスタシス恒常性の維持は、単なる現状維持ではなく、環境の変化に対応しながら、状態を一定に維持する機能である。そう考えると社会的にもどのような機能が必要になるか、ある程度見えてくるだろう。
正常性バイアス(normalcy bias) ⋆bias 偏見、先入観、思い込み
災害時に被害を大きくする要因として正常性バイアスが注目されている。些細なことに一々反応しないようにする心の安全装置の一つとも説明されるが、「まだ大丈夫」「まさかそんなことは起こらないだろう」という気持ちが被害を大きくする。
また、多数派(集団)同調バイアス(majority synching bias=迷った時に周囲と同じ行動をとる)も正常性バイアスと同時に起こると一層被害を大きくすると指摘されている。
確かに、韓国の地下鉄火災では煙の中でも多くの人が座席に座り、スマホをいじっている人の表情はどこか笑ってさえいるように見えた。セウォール号でも沈没直前、逃げるのではなく、船内での動画がたくさん残されていた。
商業施設内で非常ベルが鳴り響いても誰も騒ぎ立てたり、駆け出したりしない。多くの人が「万が一」を考えるのではなく、「またか」「どうせ…」と思うから、全員がそのように対応する。
東日本大震災の時、女子中学生が「高台に逃げろ」と大声で叫んだことで多くの人が助かったという話がある。正常性バイアスを破り、皆を逆方向に同調させたことで多くの命が救われたことになる。多数派(集団)同調バイアスがよい方に向かったケースである。
また、エキスパート・エラーなるものもある。既存の経験・知識の範囲内で発想するからプロであればあるほど間違えるし、プロを信頼して言うことを聞けば被害も大きくなる。セウォール号における「船室で待機せよ」という船内放送もその一つと言われている。
以前から人口減少・高齢化については多くの原稿を書き、セミナーでも話してきたが、まだ多くの企業は動こうとしない。正常性バイアスが強く働いてるらしい。
「日本の人口は地方で減少しているが、東京など大都市には人口が集中している」というのが、一般的な認識である。しかし、政府が16日に閣議決定した2015年版首都圏白書では、「首都圏の人口は2015年をピークに減少に転じ、高齢者人口は他地域に比べて急激なペースで増える」というものであった。首都圏の人口減少・高齢化でも、いまは介護問題だけがクローズアップされているが、今後様々な分野で影響が顕在化してくるだろう。
インフラや箱モノなど形あるモノの維持管理・更新問題が大きいが、人口が減少し、高齢化して収入が減ればコスト負担が難しくなるのは明らかである。特に2020年東京オリンピック以降、宴の後をどうするのか、今から準備する必要があるだろう。
もったいない
大学で非常勤として教え始めて20年以上経つが、「勉強=工夫の仕方」「思考・論理の組み立て方」「基礎知識・基礎学力」「人との接し方・組織の中でのポジションの取り方」など、最も基本的なことを身につけずに小中高12年間を過ごしてきたケースが少なくない。
面白いことに、多くの学生が親や教師から「勉強しなさい」と言われたことがあっても「勉強とは何か」について説明されたことはないという。
学生には「勉強=工夫すること」と定義し、工夫する際に有効と思われる手法、思考方法、論理の組み立て方などが身につくような実技中心の授業をしている。
もともとコンサルティングが本業ということもあるが、問題の定義の仕方、問題解決の方法は、あらゆる場面で役に立つ。
ちょっとした知識、思考法、手法を知るだけで能力が飛躍的に伸びる=本来持てる能力を発揮することは珍しくない。「化ける」と言うこともあるが、本来の姿を取り戻しただけである。
これからの時代を考えると、人口減少・高齢化という我々が過ごしたよりはるかに難しい時代を生きていく必要がある。そう考えれば、少なくとも、社会に出る前にその準備ができるようにするのが我々の責務だろう。
企業についても全く同様である。持てる能力を十分引き出すことができるか否かですべては大きく変わる。いろいろな企業を見てわかることは、企業には潜在的な能力とそれを十分生かすために明らかに不足している機能・能力(経営者の器もその一つ)があり、そのマッチングが上手くいっている企業はほとんどない。
情報量は増え、進化の速度も早まっている。地球の裏側で起きたリーマンショックで、日本の公園に多くの失業者が溢れることを考えれば、人も企業も持てる能力を十分生かせる知恵と工夫、それが実現できる仕組みが必要である。
「バカの壁」「無知の知」….等々、難しい話にしなくても、もっと単純に本来の能力が生かせないのは「もったいない」と考えればやるべきことはたくさんある。
マーチャンダイジング変革②
地域別の品揃えがブームになりそうだが、一歩間違えると大きな混乱を招くことになるだろう。本来、地域特性に合わせて品揃えを変えること(個々の状況に合わせて対応すること)と「標準化」「システム化」とは相反する概念ではないが、どうも対立する概念といった理解が主流であるような気がする。
小売業では「標準化=画一化」という間違った理解、解釈が長年支配的であり、「モジュール化」という標準化の応用形を知らないまま現在に至っているケースが多い。
レゴなどのブロック玩具をみれば、ベースにあるパーツは複数の標準化された形をしているが、それらを組合せることで家でもクルマでもロボットでも、好きなものをつくることができる。出来上がりの姿を標準化するのではなく、要素となるユニットを標準化し、出来上がりの姿には自由度を持たせている。
自動車メーカーが同じ製造ラインで赤いクルマと白いクルマを一緒に流しているのと同じ理屈であるから、すでに何十年も前から当り前にあった概念である。事実30年以上前、筆者がバイヤーをやっていた時には、このような考え方に基づいて店ごとに品揃えを変えていた。。
レゴの仕組みに従えば、例えば什器3本パターンをつくる場合、3本をまとめてセットにし、Aパターン、Bパターン、Cパターンとするのではなく、1本目の什器用にa1、a2、a3、2本目用にb1、b2、b3、3本目用にc1、c2、c3というように細かく分けてパターンを持つ。それぞれの什器に3つずつ合計9パターンを持っていれば、組合せの数は3×3×3=27通りになる。実際の運用では、3本パターンであればa~eの5本分というように余分に持つ(3×3×3×3×3=243通り)、あるいは什器単位ではなく、棚板単位で更に細かく分けるというようにすれば、どんなに店数が多く、地域差があったとしてもほぼ上手くいく。
標準化したままでも十分個々の店の特徴に合わせた品揃えが実現できることになる。
問題は、情報関連部署も、実際にバイイングをする人達も長い間このような発想、手法を持っていなかったために、システムがモジュール化に対応できるようになっていないことだろう。
マーチャンダイジングを変革するには、設計思想から変えていく必要がある。
やろうとしていることは決して難しいことではないが、情報システムの設計思想が違っているから実現には時間がかかる。(Excelを使えばパソコンで簡単にできるのだが…)
製造やIT分野の進化に対し、小売の現場はまるで浦島太郎状態といってよいほど遅れている。人材交流を含めハイブリッド化しないと、すぐ目の前にある新たな時代に対応できない。
マーチャンダイジング変革①
平成23年国民健康・栄養調査によると、加齢に伴い腹囲 男性85cm以上、女性75cm以上(メタボリック症候群の基準は90cm以上)が、男性では30歳代で40%、40歳代で50%を超え、60歳代では60%を占める。女性は20歳代30%、30歳代には50%を超え、その後80%超まで増え続ける。
男性は、肥満・標準体重に関わらず、加齢に伴って腹囲増加が目立つのに対し、女性は体重増加を伴う腹囲増加が起こる。ある調査データを基に男性の身長とチェストを固定し、ウエスト、ヒップ、腕付根囲、太腿囲の年齢変化を見ると、20歳代と70歳代の比較では、ウエストサイズが8~10cm、ヒップは1~3cm増え、腕付根囲はほぼ同じ、太腿囲は逆に3~4cm細くなる。
服を選ぶ際、最も大きな部位でサイズを合わせるため、ウエストに合わせてスラックスを選んだ場合、高齢化するに従ってヒップも太腿も大きすぎることになる。
一般に行われるグレーディングと加齢に伴う実際の体型変化の間にミスマッチが生じているため、高齢化するとフィットする服の入手が困難になる。体型に合う服、着られる服、着やすい服がない、という消費者の不満が生まれる構図である。
女性の場合、男性ほど単純ではないが、男性と似たような傾向は確認できる。かなり古いデータではあるが、ある調査データを基に加齢に伴う各部位の身長比を指数化(各部位÷身長×100)してみた。20-24歳と60-65歳の比較ではウエストの指数増加が圧倒的に多く、バスト、ヒップはウエストの指数の約4割、太腿囲は微増にとどまっており、前述の男性の場合とよく似た結果となっている。
「マーチャンダイジング」とかっこよく言ってみても、科学的でなければ消費者は満足しない。高齢化すれば衣料品への支出は確実に減る。マーチャンダイジングそのものの思想、手法を変えないと、生き残ることが難しくなる。
相乗積と交叉比率
「相乗積は?」と訊くと「荒利率×売上構成比」という答えが返ってくる。「意味は?」と訊くと「???」とほとんどの人が理解していない。算数と同じで公式だけを丸暗記する教育の弊害である。クエスチョニング思考であれば、まず「荒利率×売上構成比」という式を絵に描いてみる、あるいは式を展開する。
例えばA商品、B商品、C商品という3つの商品があるとする。A商品の相乗積は(A荒利率=A荒利高÷A売上高)×(A売上構成比=A売上高÷売上高合計)であるから、分母と分子にあるA売上高が消えて、残るのはA粗利高÷売上高合計、つまりA商品が稼ぎ出す粗利高が売上合計に占める割合=全体に対する利益の貢献度合いということになる。
公式を覚えただけでは忘れてしまえばそれで終わるが、図表「相乗積の意味」に示すように絵を描いてみれば、やっていることがA商品、B商品、C商品のそれぞれについて荒利高を計算して足しているだけということが理解できる。意味が解れば例え公式を忘れても導くことができる。
交叉比率も全く同じようにして「荒利率×商品回転率」という式を展開すれば(荒利高÷売上高)×(売上高÷在庫高)となって、分子と分母にある売上高が消えるから、荒利高÷在庫高(投資と見る)となり、投資した在庫の何倍の荒利高を稼ぎ出しているかを求めていることが分かる。ちなみに商品回転率は在庫高(投資と見る)の何倍の売上高を上げているかである。
単に式を覚えただけでは、テスト問題は解けるかもしれないが、忘れてしまえばそれまでである。まして意味が理解できていなければ、使いこなすことなどできはしない。
どうせ同じ時間をかけるのであれば、実のあることをする方がよいに決まっている。
「クエスチョニングのすすめである」
★参考 相乗積と交叉比率を使いこなす
何でもマトリックス
学校でも習うメンデレェフ(Mendeleev,Dmitri Ivanovich ロシア1834年~1907年)の周期律表は、思考を整理する上でとても重要なヒントを与えてくれる。
当時はスペクトル分析や電気分解を通して約60種類の元素が分かっていた。メンデレェフは原子量の順に並べるとよく似た性質の元素が一定周期で現れることを発見し、1869年周期律表にまとめた。周期表に基づいて未知の元素ガリウム、スカンジウム、ゲルマニウムなど27個の新元素の存在を予言し、その後予言通りそれらの元素は発見されている。
表頭(横軸)、表側(縦軸)に規則性、法則性を持たせてマトリックスを作成すると、マトリックスの中にすべての関連する要素を規則、法則に従ってモレなく整理することができる。
例えば、経営の3要素である人、物、金、マネジメントサイクルplan、do、see、あるいは5W3H(what、why、when、where、who、how to、how much・many・long、how well)のマトリックスを作成すると、さまざまな物事をモレなく抽出することができる。
表頭と表側に目的と手段、あるいは原因と結果とするマトリックスを作成すれば、我々の身近にあるあらゆる物事に対処する基本的な形を手に入れることができる。さらに5W3Hを加えれば、より具体的にモレをなくすことができるから、思考を整理したり、詳細な計画を作成したりする時にはとても便利である。
何にでもマトリックスを作成し、活用する習慣をつければ、物事を早く、簡単に、しかも法則性にのっとってモレなくおさえることができる。
何でもマトリックスである。
クエスチョニングのすすめ
アンサリングが「 問題に答えること 」であるのに対し、クエスチョニングは「 未知の状況に答えられる( アンサリング )ように問題という形につくり上げていくこと 」である。
アンサリングでは「 問題 」の出題時点で範囲、制約条件などが明らかになっており、限定した枠組みの中だけで物事を考えていけば良い。しかも、通常は問題の中に解くためのヒント・条件などが必ず入っている。
一方、問題をつくるには、自分で問題の範囲、制約条件などの枠組みを設定するところから始めなければならないから、「 下絵が描かれた塗り絵に色を塗る 」のと「 真っ白なキャンバスに絵を描く 」ほどの違いがある。
コンサルティングでは「 何が問題か分からないのが問題 」という企業に出会うことがある。何かおかしい、どうにかしなければならない、という状況認識はあっても、具体的に何が問題か分からないから手のつけようがない。
課題さえ与えてくれればどうにか取組むこともできるが、それがないからどうして良いか分からない。
「 出された問題、与えられた課題に対処すること 」しかやったことがなければ、ゼロからすべてを組み立てることは難しい。成績の良かった子がある時急に何もできなくなり、成績の悪かった子が生き生きとして何かに取り組むということが起こってくる。どこかで評価が180度逆転する。だからクエスチョニングのトレーニングは早ければ早い方が良い。
日本全国、老いも若きも「クエスチョニングのすすめ」である。