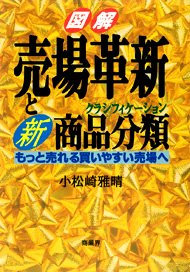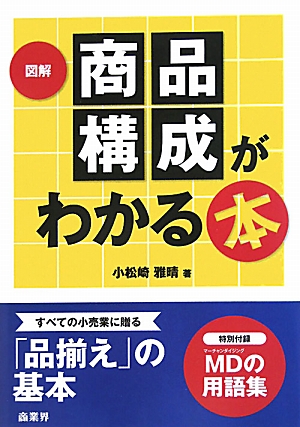◆7月13日、住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(平成28年1月1日現在)が公表された。それによれば東京23区内には約920万人が暮らす。東京都は社会増ばかりか自然増も加わり、この1年間で118千人も人口が増えている。先回の国勢調査では5年間で東京都35.4万人、うち23区32.7万人増えているから、このペースで2020年東京オリンピックを迎えれば、次の国勢調査までに東京都だけで60万人以上の人口が増えてもおかしくはない。 平成27年国勢調査 人口速報集計結果では、この5年間に全国で94.7万人減少しているにもかかわらず、東京圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)では、その5年間に鳥取県の人口(57.4万人)に匹敵する人口(50. 8万人)が増加している。 東京臨海副都心など超高層マンション(集計上、一つの目安として20階以上 株式会社不動産経済研究所)が建設されると平均して一棟当たり300~500戸、50階以上の超超高層マンションになると、一棟当たり800~1000戸もの規模になる。 首都圏だけで2015年~2019年までに178棟、77,824戸の完成が予定されており、うち東京オリンピックへ向けて50階以上の超超高層マンションだけでも西新宿、勝どき、晴海などに14棟、13000戸も計画されている(分譲済み含む)。 単純に世帯人員が2人とすれば、一棟につき1000~2000人の人口が増えることになり、何棟かできれば町や村と同規模の住民が新たに加わることになる。 また、都内には千葉県、埼玉県、神奈川県などから毎日300万人弱が通勤通学で通ってくる。さらに国内外からのビジネス客、観光客も多いから山手線の29駅(JR、私鉄、地下鉄など)の中には東京駅、品川駅、秋葉原駅、新宿駅、渋谷駅、池袋駅など1日の乗降客数・乗り換え客数が100万人を超える駅がいくつもある。1つの駅だけでも毎日1つの県の人口が行き来しているようなものであり、山手線29駅(JR、私鉄、地下鉄など)を合計すれば延べ2100万人と四国・九州を合わせた人口にも匹敵する。 マンションばかりでなく、超超高層オフィスビルの増加によって、周辺エリアから通勤で通う人も急激に増加し、しかも局所的に人が集中する。昼夜人口比率が極端に高まるエリアでは、新たに様々な人が集まることで多様なニーズによるマーケットの急拡大が起こる。 一方、全体で約100万人減っているのに東京圏は50万人増えているということはそれ以外の多くの道府県で150万人の人が減少していることになる。人口が増えているのは、平成27年国勢調査では8都県ということになっているが、住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(平成28年1月1日現在)では、滋賀県がマイナスに転じているから、人口が増加しているのは、東京圏1都3県と福岡県、愛知県、沖縄県の7都県の実である。 ただし、「日本の地域別将来推計人口 —平成22(2010)~52(2040)年— 平成25年(2013年)3月推計」の値と平成27年(2015年)国勢調査 人口速報集計結果を比較してみると、人口の減り方が推計値よりも小さくなっている道府県は多く、増加すると推計されている県の増え方も推計値より大きくなっている傾向にある。 これらを整理したのが 図表1 都道府県別 平成27年国勢調査と日本の地域別将来推計人口(2013年3月推計) 2015年人口の差 である。
グラフでは、右上(2010年~2015年までの5年間で人口が増え、なおかつ2015年実績値は「日本の地域別将来推計人口(平成25(2013)年3月 推計)国立社会保障・人口問題研究所」推計値より多い)、右下(2010年~2015年までの5年間で人口が増えているが、2015年の実績値は同推計値よりも少ない)、左上(2010年~2015年までの5年間で人口が減少したが、2015年実績値は同推計値よりも多い)、左下(2010年~2015年までの5年間で人口が減少し、なおかつ2015年の実績値が同推計値よりも少ない)という4つのエリアに分けて、都道府県の状況を整理してある。
★東京都ははるか右上に位置し、値が大きいためにグラフのメモリの関係でカットしてある。(5年間の人口増加354,317人、推計値との差164,281人)
詳細はまた機会を改めて詳細に説明するが、それぞれの都道府県について市区町村のポジションを同様にグラフ化してみても、人口集中が局所的に起こっていることが分かる。
◆「日本の地域別将来推計人口 —平成22(2010)~52(2040)年— 平成25年(2013年)3月推計」から見る人口が減少する都市と増加する都市の見極め方
平成27年国勢調査 人口速報集計結果では、平成27年10月1日現在の人口は1億2711万人(平成22年比▲94.7万人)、市町村単位では、1,719のうち実に8割以上(1,416、82.4%)の市町村で人口が減少し、5%以上減少した市町村も48.2%と半数近くにのぼる。うち10%以上減少も227(13.2%)ある(いずれも平成22年比)から、日本全体としては、人口が増える市区町村は珍しい存在ということになる。
一般的に考えれば、人口規模の大きい都市が周辺の中小規模の都市から人口を吸収するから人口減少の仕方は少なく、規模が小さければ小さいほど減少の仕方が大きいと考えがちである。
しかし、「日本の地域別将来推計人口 —平成22(2010)~52(2040)年— 平成25年(2013年)3月推計」について、将来の人口増減に影響を与えると思われる要素をいろいろと分析してみたところ、人口規模が大きい市区町村でも大幅に人口が減少するところがある一方、人口1万人規模の市区町村でも人口が将来増えると推計されているところがあることが分かった。
キーを握っているのは図表2 2015年65歳以上人口率で層別した8パターンの状況、図表3 2015年65歳以上人口率別 2015年総人口と2025年総人口指数 からも分かるように、現在の65歳以上人口率である。
以前にも3万人、5万人、7万人、10万人、15万人、20万人、25万人、30万人と8つの規模の都市の中から2040年の総人口指数(2010年=100)が100超(人口が増える)と60~70(人口減少幅が大きい)の都市をランダムに選んで比較してみたことがあるが、都市の規模からでは人口減少について明確な法則を見出すことはできなかった。
それに対し、65歳以上人口率が18.0%以下(12.4-18.0% 23都市)、20.0%(19.5-20.4% 31都市)、25.0%(24.5-25.4% 90都市)、30.0%(29.5-30.4% 90都市)、35.0%(34.5-35.4% 77都市)、40.0%(39.5-40.4% 40都市)、45.0%(45.4-45.4% 23都市)、50.0%(50.1-60.9% 17都市)というほぼ値が一定範囲内にある8パターン、391都市について調べてみると、
図表3のような散布図になった。
横軸に総人口指数(2010年=100)、縦軸に総人口(人)をとって、散布図を作成してみる。仮に人口規模が大きい方が人口の減り方が小さい、あるいは増加し、人口規模が小さい市区町村の方が減少の仕方が大きいとなると、各市区町村は左下から右上に向かって正比例するように並ぶはずである。
しかし、実際には総人口指数が同じであっても、縦に長くばらついてプロットされている(特に65歳以上人口率が20-25%で縦に長い)。人口規模が大きく違っても総人口率が同じということが見て取れる。また、例えば50,000~100,000人規模の市区町村というように同規模の市区町村(横に見る)を見ると総人口指数は80-120くらいというように大きくばらついているから、人口の減り方は人口規模とほとんど関係していないことが分かる。
要するに65歳以上人口率が将来の人口の減り方に大きく影響していると考えてよいということになる。
ただし、ここで見ているのは、2015年に対して2025年がどういう状況にあるかというあくまでも10年後までの予測である。その先にどんな状況が待っているかをさらに進めてシミュレーションすれば、現在65歳以上人口率が低い市区町村は、人口は減らないが将来は急激に高齢者が増え、その後一定数値に収束する。一方、現在65歳以上人口率が高い市区町村は、人口は減るが高齢者は大きく増えることはなく、ほぼ一定の年齢構成に収束して人口が減少していく。
サイクルが20年くらいずれていると見てもよいだろう。
◆人口が減少する都市と減らない都市を見極めてどうするのか?
全ての市区町村について、ほぼ人口の減り方について見極めをすることはできると考えてよいだろう。問題は、見極めたうえでどうするのかという対応の仕方である。
多くのチェーンストアがドミナントを形成しているからある地域の人口が急激に減少したり、あるいは急激に高齢化したりすれば、ドミナント全体が立ちいかなくなる。それは単一地域でも複数の県にまたがっていても同じである。
団塊の世代が約500万人おり、2020年には70歳を超え、すぐに健康寿命を超えるから、状況の大きな変化は一気にやってくる。
「茹でガエル」の話のようにならないようにするためには、すでに動き出していないと間に合わない。「経営」が試されていると考えるべきである。